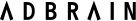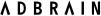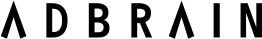-
第20の皿 うまい汁を吸う、焼き麩入りオニオングラタンスープ
平日に食べるスープを、休日にまとめて作るようにしている。
オニオングラタンスープ(以下、オニグラ)もたまに作るが、
唯一困るのが、スープに浮かせるバゲットだ。1杯に1切れだけ必要なバゲットを、1本買うのも効率が悪く、ましてや切るのが面倒だ。
買った時にお店で切ってもらってすぐに冷凍し、1回分ずつ取り出せばよいのだが、
家の冷凍庫は、自家製冷凍食品で常にいっぱいで、バゲットを入れる余地はない。そこで、目を付けたのが、焼き麩である。
大きめの「くるま麩」と呼ばれるタイプが、バゲットの代わりとして、この上なく重宝する。
成分は同じ小麦粉だし、最初から切ってあるのもうれしい。
乾物なので保存性が高く、常備できるのもありがたい。
そして何より優れているのは、汁を吸うのが大の得意であることだ。バゲットはそのままでも食べられる立派な食品だが、焼き麩は単体では成立しない。
うまい汁を吸って食品業界を渡り歩く、寄生専門食材なのだ。
「麩のうまさは、料理が決める」というか、「俺をおいしくしてみろ」と作り手を挑発する、
誠に厄介な腕試し食材と言えよう。それだけにこの焼き麩は、汁を吸わせたら本当にうまい。
バゲットだと汁を吸い過ぎて、食べ進めるうちにどろどろに溶け出してしまうが、
焼き麩の場合、ほどよく吸って、食感はもっちり。
溶けたチーズとの相性もよく、まるでオニグラのために存在するのかと思えるほどだ。オニオングラタンスープ(4皿分)
たまねぎ 2個(薄切り)
ブラウンマッシュルーム 4個(スライス)
スライスチーズ 4枚(溶けるタイプ)
くるま麩 4切れオリーブオイル 大さじ1
白ワイン 大さじ3
水 1000cc
コンソメの素 2個
マジョラム 小さじ1/2
塩 少々
こしょう 少々
しょうゆ 大さじ1- 薄切りにしたたまねぎを耐熱容器に入れてラップを掛け、レンジ加熱する(1000Wで3分)。
- 鍋にオリーブオイルを入れ、たまねぎが飴色になるまで弱火でじっくり炒める。
- マッシュルームを軽く炒めたら白ワインを加え、煮立たせてアルコール分を飛ばす。
- 水と調味料を入れて煮立たせ、とろ火にして30分ほど煮込む。
- カップに注ぎ、麩を入れてからチーズを載せ、レンジ加熱する(1000Wで3分)。
うまい汁のもとは、とことん炒めた、たまねぎの味。
このため、工程のほとんどがたまねぎを炒める時間となるが、
それを大幅に短縮するのが、事前のレンジ加熱である。
生から炒めると飴色まで1時間かかるが、レンジを使えば、
30分くらいで甘い香りが漂い、さらに炒めるとカラメルのような匂いがしてくる。面倒な作業だが、焼き麩にうまい汁を吸わせるため、
たまねぎを丹精込めて飴色に育てるのだ。
-
第19の皿 おかわりはセルフで、肉じゃがカレー
さる会合で訪れたその店は、ひっそりとした住宅地の一角にあった。
地下鉄が開通するまで「陸の孤島」と呼ばれ続けたエリアで、
その名を返上してもなお、当時のイメージを色濃く残している。
こうした街にある人気店はたいがい「隠れ家」と呼ばれるが、
このお店もまさにそんな風情を漂わせていた。和食を中心とした居酒屋なのだが、運ばれて来るどの皿も素晴らしい。
刺し盛り、肉じゃが、ラタトゥイユ、茶碗蒸しなど、奇をてらったメニューはないが、
どの皿もていねいに作られていて、味がいい。
やがて、コース料理を締めくくる、ごはんを選ぶ時間となった。卵掛けごはん、麦とろ、お茶漬け、肉じゃがカレー。
このお店のことだから、どれもうまいに違いないだろうが、ひとつしか選べない。
となると、すでに食べている肉じゃがは、まず外すべきか・・・。
そう考えていると、見透かしたかのようにお店の人が、
「先ほどお出しした肉じゃがとは、味がまったく違います」とアドバイス。
そう言われたら、違いを確認せずにはいられないのが人情というものだ。こうして、めでたくチョイスされた肉じゃがカレーは、
通常の半分くらいの大きさのご飯茶碗に盛られていた。
味は、和風ドライカレーの趣で、煮物ならではの甘みがたまらなくやさしい。
具がすべて溶け込んでペースト状になっており、料理の肉じゃがとは確かに異なっている。味のおいしさと量の少なさに、ついおかわりが欲しくなるが、
コース料理のシメのごはんで所望するわけにもいかない。
あっという間に空になったお碗を見つめながら、味の記憶を心に詰め込む。
これをおみやげとして持ち帰り、再現して「セルフおかわり」を果たすのだ。肉じゃがカレー(ごはん茶碗2膳分)
肉じゃが(市販の惣菜) 1パック
たまねぎ 1/4個(みじん切り)オリーブオイル 大さじ1
薄力粉 大さじ1
片栗粉 小さじ1/2
カレー粉 小さじ1ごはん 2膳分
ドライパセリ 少々
- 肉じゃがをフードプロセッサー低速で粗くミンチ、もしくはマッシャーで潰す。
- フライパンにオリーブオイルを引き、たまねぎをよく炒める。
- 薄力粉、片栗粉、カレー粉を加え、サラサラになるまでじっくり炒める。
- 1を入れ、とろ火で10分加熱する。
- お碗に盛ったごはんに載せ、お好みでドライパセリを振り掛ける。
我が家では、市販の惣菜ではなく、わざわざ肉じゃがを作って一部を取り分けた。
食べてみると、本家には及ばずとも、家庭料理には十分すぎる味に仕上がっていた。
こうしてセルフおかわりを実現したわけだが、この味はやみつきになる。
結局、残りの肉じゃがは、すべてカレーに化けてしまった。
-
第18の皿 真相は藪の中のハヤシライス
ハヤシライスは、ミステリーである。
その不思議な名前には由来が諸説あり、発祥も定まっていないのだという。いちばん有力な説は、「ハッシュドビーフ with ライス」から、
「ハッシュド」が「ハッシ」→「ハイシ」→・・・と訛っていった、とするもの。
旧海軍のレシピ集にも「ハッシュドポテト」を「ハヤシ」と表記した箇所があり、
この説が正しいとする根拠として挙げられているとか。次に有名なのが、東京・日本橋の老舗書店「丸善」を興した、
早矢仕有的(はやし・ゆうてき)さんの発案説。
親交のあった外国人の友をもてなした料理だとも、
医師でもあった彼が考えた理想の病院食とも、
丁稚たちに振る舞った夜食とも伝えられ、
現在でも丸の内本店や日本橋店などにある直営のカフェで
「早矢仕ライス」の名で提供されている。さらに、「ハヤシ」の由来として誰もが真っ先に想像する、「林さん」説がある。
洋食店の林シェフが、ビーフシチューをごはんに掛けた賄い飯として考案した、というものだ。
その林さんは、老舗洋食店・上野精養軒のコックだった、
という説もあるが、真偽のほどはよくわかっていない。
だが、このお店は、林さんの話とは別の理由で「ハヤシライスの元祖」として名高い。
この店を経て、のちに”天皇の料理番”と呼ばれた秋山徳蔵氏による
「宮内庁風ハッシュドビーフ with ライス」のレシピを
神田・松栄亭とともに精養軒が受け継いだ、という歴史があるのだ。他にも、門司港にある大衆食堂が急ぎの乗船客用に作った「早いライス」説から、
牛肉が一般的ではなかった時代に「そんなもん食べると早死にするぞ」の意味から付いた
「早死ライス」という物騒なものまで、さまざまな説が存在している。ハヤシライス
〈4皿分〉牛小間切れ肉 200g(塩・こしょう・薄力粉を振っておく)
ブラウンマッシュルーム 1パック(スライス)
たまねぎ 1個(薄切り)
オリーブオイル 少々〈ドミグラスソース〉
たまねぎ 1個(薄切り)
バター 15g
薄力粉 大さじ2
赤ワイン 200cc
白ワイン 100cc
水 300cc
ココアパウダー(無糖) 大さじ1
コンソメの素 2個
トマトケチャップ 大さじ4
ウスターソース 大さじ2
ナツメグ 小さじ1
ローリエ 2枚- オリーブオイルを熱した鍋で牛肉、たまねぎ1個、マッシュルームの順で1種類ずつ炒め、取り出しておく。
- 鍋にもう1個のたまねぎとバターを入れ、飴色になるまでとことん炒める。その後、薄力粉を加えて炒め合わせる。
- 赤ワイン、白ワインを加え煮立たせてから調味料を入れ、ふたをしてとろ火で30分煮込む。
- 1を戻してさらに30分煮込み、皿に盛ったごはんに掛けていただく。
ごはんは、白飯でもよいが、やはりバターライスで食べたい。
生米を透き通るまでバターで炒めてから、ローリエ1枚を加えて通常の水加減で炊けばよい。さて、この料理の名前の由来だが、私は「ハッシュドビーフ with ライス」説を支持したい。
ハッシュドの訛りの進化は最終的に、「切る」の忌み言葉として用いた
「はやす(=生やす)」という古語と合体することで、ハヤシの名でめでたく定着したという。
そして偶然にも、英語のハッシュ(hush)も、「細かく切る」という意味。
和洋どちらの言葉も同じ意味を持っていたという事実は、
両者の融合で生まれた「洋食」を代表する料理の名にふさわしいと思えるからだ。ドミグラスソースとごはんの取り合わせは、まさに「日本の洋食」。
本来はパンとでしか味わえないハッシュドビーフを、お米とも楽しむことができるのは、
日本人の特権である。
-
第17の皿 真冬にアツアツ、白菜獅子頭
台湾は台北の、中心部から少し外れたところに、
家庭料理を売りにした店がある。
スタッフは、すべて女性なのだが、全員が2〜30年ほど前の「若い女性」。
ステンレスで設えた厨房は清潔で広く、みんな白い割烹着姿なものだから、
どこか給食室のような雰囲気が漂っていた。コースメニューはなく、もやしの炒めやチリウインナーなど、
作り置きの前菜をつまみながら、料理を待つ。
はまぐりの炒め、しいたけと豆腐入り鍋、たけのことそらまめの炒め、
野沢菜&えび入りラーメン、卵入り炒飯など、
家庭料理の店だから、高級なものは一切入っていない。
一般家庭で使われるおなじみの食材ばかりで、
ちゃんとした「お店の味」を作り出しているのだ。この店で頼む料理には、何ひとつハズレがない。
なので、宿泊するホテルからMRT(地下鉄・モノレール)を二度乗り換え、
徒歩を含め片道30分を掛けて、合計3回通った。
通常、旅行の短い滞在中は、なるべく多くの店を回りたいものだから、
同じ店を続けて利用することは、めったにない。
だが、他の店でハズレを引くくらいなら、この店でアタリを引き続けたい。
メニューにある料理を、なるべく多く試したくなる店なのだった。そんなこの店で、行く度に必ず頼んだ料理がひとつある。
白菜と肉団子だけを1人前用の小さな土鍋で
グツグツと煮込んだ、シンプルな一皿。
「白菜獅子頭」と呼ばれている店の名物料理は、
白菜の甘みがとてもやさしい、滋味あふれるおいしさである。白菜獅子頭
白菜 1/4株(ざく切り)
薄力粉 大さじ1
ごま油 大さじ1〈肉団子〉
豚ひき肉 300g
長ねぎ 1/2本(みじん切り)
卵 1個
片栗粉 大さじ1
おろししょうが 小さじ1
塩 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
オイスターソース 小さじ1〈スープ〉
水 200cc
塩 小さじ1
鶏ガラスープの素 大さじ1
酒 大さじ2
白こしょう 少々- ボウルに肉団子の材料を入れて、よくこねる。
- 4分割してそれぞれを野球ボール大に丸め、空気を抜いてから薄力粉をまぶす。
- ごま油を引いた小鍋に入れ、肉団子の表面がカリッとするまで焼く。
- 小鍋にスープの材料と白菜を加え、ふたをして30分ほど弱火で煮込む。
調理法や味付けは例によって推測だが、試行錯誤の末、
記憶している味にはかなり近づいたと思っている。
肉団子は、面倒なのとカロリーオフのため、
少量の油で揚げ焼きにしたが、実際には揚げているはず。その揚げ立てをしっかり煮込んで、アツアツの状態でいただくわけだ。
亜熱帯気候の台湾では、冷房の効いた店内で食べることになるが、
白菜鍋の食べ方としては、やや風情に欠ける。
本家には悪いが、日本の真冬にこそふさわしい、温かさである。
-
第16の皿 ゴーヤの代わりではなく、ピーマンチャンプルー
さて、冬も真っ盛りである。
冬には冬のおいしいものがたくさんあるが、時折ふっと、
いちばん遠い時季の食べ物が頭をよぎることがある。
当たり前だが「久しく食べていないなあ」と恋しくなるのだ。旬のものは安くておいしいので、店頭に並んでいるうちに集中的に食べ続ける。
ゴーヤが出回る夏にしか作れないゴーヤチャンプルーなどは最たる物で、
暑い季節にしか味わえない、文字通り夏の風物詩となっていた。
だが、よくよく考えれば他の食材は、豆腐、豚肉、卵など、通年売られているものばかり。
これ、ゴーヤの代わりさえあれば、夏じゃなくてもいけるのではないか。そこで、目を付けたのが、ピーマンである。
もちろん、ピーマンも夏から秋口が旬なのだが、
ハウス栽培で「冬春ピーマン」という種類が作られている。
高知県や宮崎県など、南の地方が主な産地で、
そのおかげで1年中ピーマンが店頭に並ぶというわけだ。
ピーマンはナス科、ゴーヤはウリ科なので
両者からそれぞれ「同じに見るな」と苦情が来るかもしれないが、
色といい苦みといい、これほどゴーヤの代役として似合うものはない、と思ったのだ。ピーマンチャンプルー
ピーマン 8個(縦方向に細切り)
木綿豆腐 2丁(しっかり水切りをしておく)
卵 2個
豚こま切れ肉 100g
きくらげ 1つかみオリーブオイル 大さじ2
酒 大さじ2
鶏ガラスープの素 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
白こしょう 少々
ごま油 少々- オリーブオイルを引いたフライパンで豆腐を炒め、両面に焼き色が付いたら一旦取り出す。
- 豚肉を炒め、火が通ったら一旦取り出す。
- ピーマンを入れ、皮に焼き色が付くまで炒める。
- 酒で溶いた鶏ガラスープの素を絡め、豆腐と豚肉をフライパンに戻し、きくらげを入れる。
- 卵を全体に回し入れ、半熟状になったらしょうゆと白こしょう、ごま油で味を調える。
実際、食べてみると、ゴーヤの代役と決めつけたことをつくづく反省する。
ことに、露地物が出回る夏のピーマンは、ともに旬を迎えたゴーヤにも負けない。
2010年などは日照不足でゴーヤが小ぶりだったため、
夏のチャンプルーもピーマンには大いに助けられたものだ。このピーマンチャンプルーに、カラーピーマンやパプリカを加えると、
彩りもあざやかで目にも楽しい。
どんより曇った冬の日の食卓にも、
夏の太陽を思わせるまばゆさである。