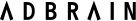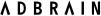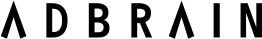-
第35の皿 真夏の楽しみ、コーンサラダ
海派と山派のどちらかと問われ、
その二択しかないことに困惑するインドア派にとって、
夏はあまり楽しみの多くないシーズンである。この季節の楽しみは、そのほとんどが「暑さ」を前提にしていて、
そんな気候の中でどう過ごすかが基本になっている。
花火大会や盆踊りなど、「納涼」と銘打たれたイベントも多いが、
これらを楽しむためにも、結局は暑い中を出歩かなくてはならない。
「江戸っ子の粋とは、やせ我慢のことである」という言葉がある。
確かに、夏を楽しむには根性が必要だが、
その持ち合わせのない人間にとっては、限りなく高いハードルなのである。そこへ行くと、引きこもり系こそが夏に楽しめる、奇跡的な娯楽が「昼寝」である。
そのベストシチュエーションと言えば、やはり「プールからの帰宅後」であろう。
プール上がりのけだるい身を横たえた瞬間に、すーっと眠りに落ちる。
夜の睡眠とは違う、一種独特のあの心地よさは、子どもの頃には何度も味わったものだが、
今再び味わうには、やっぱり暑い中をプールまで出掛けなければならない。
もう一生無理かもしれないなあと、昼間から横になりながら、ぼんやりと考えている。そんな、相性の悪い夏ではあるが、この季節にしか食べられないものも多いので、
文句を言ってばかりもいられない。
そこで今回の料理は、真夏でなければ楽しめないもの、
ということで、生のとうもろこしを使った料理を。コーンサラダ
とうもろこし 1本
マヨネーズ 大さじ2
黒こしょう 少々- とうもろこしをゆでる。
- フルーツナイフで実をこそげ、ボウルに移してマヨネーズと黒こしょうで和える。
- 冷蔵庫で少し冷やす。
外食やデパ地下の定番とも言えるコーンサラダも、
旬の生とうもろこしから手作りすると本当においしい。
これをパンに載せてトーストしたものも、また格別だ。夜の睡眠は生存のためのものだが、しなくても構わない昼寝は、娯楽そのもの。
ゆでたてをそのまま食べてもおいしいとうもろこしも、
実をこそげてマヨネーズで和えれば、食べる楽しみが増す。
冷たくしておいしい、夏のエンタメである。
-
第34の皿 丑の日の煮穴子
日本のコピーライター第1号は誰なのか、ご存じだろうか。
その人物は、夏に鰻を食べる習慣を定着させ、
季節の風物詩にまで押し上げたと言われている。
鰻は本来、秋から冬が旬なので、夏の売り上げはさっぱり。
どうにも困った鰻屋の主人がその人に相談したところ、
「本日丑の日」と書いた紙を店先に貼るように勧められたという。
これが当たりに当たって、お店は大繁盛。
それを見た他の鰻屋が続々真似るようになった、という話である。かねてより、丑の日には「う」の付く物を食べると夏負けしないという言い伝えがある。
それまでは梅干しや瓜が食べられていたそうだが、
それらに比べて鰻は、ビタミンA・B群が豊富で滋養強壮作用に優れているため、
暑い夏の食べ物として見直されたということなのだろう。このエピソードをもって、「本日丑の日」は本邦初の商業コピーであり、
その書き手こそがコピーライターの草分けである、とされているのだ。
その人物の名は、平賀源内。蘭学者にして医学者、発明家にして事業家、
戯作家、浄瑠璃作家、画家、俳人、日本初の博覧会プロデューサー。
肩書きコレクターと呼べるほどの才能にあふれた、
江戸時代のスーパーマルチクリエーターの彼だが、
同じ業界の偉大なる先達でもあったわけだ。「丑の日に鰻」は、現在まで200年以上も続いている超ロングヒットキャンペーン。
いやはや、スケールが違いすぎるにも程がある。
翻って、平成のコピーライターは、大先輩に敬意を表しつつ、
値段が高くて食べられない鰻に代わって、穴子を調理してみる。煮穴子
刻み穴子 1パック
酒 大さじ2
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
水飴 小さじ1粉山椒 お好みで
- フライパンに調味料を入れて煮立たせる。
- 穴子を加えて煮る。
- お好みで粉山椒を振り掛ける。
刻み穴子は、穴子の白焼きを1cm幅に刻んであるもので、
たれが付属していることが多いが、このたれは使わずに自前の調味料で作る。
熱いたれに絡めて粉山椒を振れば、鰻の蒲焼きより上とは言わないが、
これはこれでなかなかのものである。昨今、鰻を食べようと思えば、ふところはたちまち涼しくなるが、
穴子は比較的お財布にやさしい。
家計の夏負けを防いでくれるのである。
-
第33の皿 食卓の句読点、Q漬け
「箸休め」と呼ばれる料理がある。
食べ応えのある主役クラスのおかずを引き立たせる役割の惣菜のことである。
コース料理なら「お口直し」に相当するものだろうか。
家庭料理だと一皿ずつ出て来るわけではないから、
最初から食卓の片隅にひっそりと置かれている。
そこで、メインおかずの合間にちょっとつまんで、
味覚のリフレッシュを果たすというわけだ。箸休めの代表選手は、やはり漬け物であろう。
食べる際に出る「ポリポリ」という音も、
サイドディッシュにふさわしい重みのなさだ。
なくても困らないが、あったらうれしい。
なくても成立するが、あった方が望ましい。
まさに「食卓の句読点」、
いや、「テンマル」のテンだから、読点と言うべきか。さて今回は、市販でおなじみの「きゅうりのしょうゆ漬け」を
手作りしてみるという自家製実験である。
商品のパッケージで紹介されている原材料や調理法を、
家庭料理に置き換えてアレンジするのだ。
試行錯誤の末、何とかレシピが確定したこの料理を「Q漬け」と名付けた。
こう書くと、元ネタが推測できるかもしれないが、どうかスルーしていただきたい。Q漬け
きゅうり 3本(7mm幅にやや斜め切り)
しょうが 20g(針状に刻む)しょうゆ 大さじ2
みりん 大さじ1
酒 大さじ1
すし酢 大さじ2
レモン果汁 小さじ1
赤唐辛子 1/2本(みじん切り)
白ごま 大さじ2- 刻んだきゅうりに塩(分量外)を振り、10分後に搾って水気を切る。
- フライパンに調味料と針しょうがを入れ、煮立たせて火を止める。
- 1を入れて弱火に掛け、時々混ぜながら10分ほど煮る。
- 保存容器に移し、冷蔵庫で寝かせる。
きゅうりに水分が残ると味が薄まり、また傷みやすくもなるので、煮る前に全力で搾る。
そうすると調味料が入りやすくなり、しっかりと味が乗るようだ。ちなみに、このQ漬けは、あまり箸休めにはならない。
ひとたび食べ出すと、なかなか箸が休まらないのである。
-
第32の皿 みんなが主役の八宝菜
先日、同窓会に参加して来た。
懐かしい顔に長い歳月をまぶした、まあ歳相応に見える人がほとんどだったが、
遙かに年齢を上回る貫禄を蓄えた人や、
その逆に当時の制服を着せたくなるくらい顔も体型も変わらない人も中にはいて、
これが全員同い年なわけだから、生命の神秘を見る思いである。会の参加者は皆、「いい顔」をしていた。
全員が笑顔でいられる会合というのは、そう多くはあるまい。
「皆が笑顔」という集まりは、結婚式などもそうなのだが、
あれは、主役の2人を皆が祝う、という図式であって、
全員が心からの笑顔かというと、実はそうでもない。
寿ぐ気持ちはあるにしても、義理で参加した人もいるだろうし、
主役である新郎新婦もやることが多すぎて、100%幸せに浸れるわけではない。同窓会は、参加者全員が平等な立場である。
ある意味、全員が主役とも言える。
顔を見るうちに思い出したニックネームで呼び合うと、
時間が一気に学生時代にまで遡る。
変わり果てたと思っていた同級生たちも、だんだんあの頃の顔に戻って見えてくる。
まるで魔法にかかったような、不思議な数時間だった。さて今回は、食材みんなが主役の料理ということで、八宝菜である。
皿の中にさまざまな食材がひしめきあって、まるで1クラスのようではないか。
八宝菜
白菜 1/4把(ざく切り)
にんじん 1/2本(短冊切り)
しいたけ 1パック(細切り)
グリーンアスパラ 1束(4cm幅くらいに)豚小間切れ肉 100g
むきえび 1パック
いか(胴の部分) 1杯(2×5cm幅に)
かまぼこ 小1本(半月状か細切り)たけのこ水煮 1/2本(スライス)
うずら卵水煮 6個
ぎんなん水煮 25粒くらい
ヤングコーン水煮 1パック(縦に2分割)
乾燥きくらげ 少々(熱湯で戻す)サラダ油 大さじ3
にんにく 2かけ(みじん切り)
おろししょうが 少々
酒 大さじ2
鶏ガラスープの素 大さじ1
ほたて貝柱水煮缶 1缶(汁ごと入れる)
塩 少々
こしょう 少々
片栗粉 大さじ1(水大さじ3で溶く)- 豚肉、えび、いかに酒と塩、こしょう(いずれも分量外)を振り、片栗粉をまぶす。
- フライパンで豚肉を炒め、取り出しておく。
- サラダ油を加えてにんにく、しょうがを香りが出るまで熱し、刻んだ野菜を炒める。
- 3に火が通ったら、残りの食材と、酒と鶏ガラスープの素、ほたて貝柱水煮缶を入れて味をなじませる。
- 全体にしんなりしたら、塩、こしょうで味を調え、最後に水溶き片栗粉を回し入れる。
勉強のできる子やピアノが弾ける子、
運動会のヒーローや習字のうまい子など、
さまざまな個性が集まって、1クラス。やわらかなものや歯触りのいいもの、
苦みのあるものや食べ応えのあるものなど、
みんなが持ち味を出し合って、八宝菜。それぞれが輝きを持った、まさに「宝」の集団である。

-
第31の皿 思い出はセピア色、いか墨のパスタ
色が褪せて薄い褐色となった、モノクロの古い写真。
遠く過ぎ去った昔が焼き付けられた写真は
よく「セピア色の思い出」などと形容される。
そのせいか、セピアという言葉の響きは、
どこかノスタルジックでちょっぴり感傷的な気持ちを誘うものだった。
・・・セピアの語源を聞くまでは。セピアとは、「コウイカ」を意味するラテン語で、
その墨から作った暗褐色の顔料や、いか墨そのものを指す言葉である。
このインクで描く絵や文字は、日光などで色が褪せる。
こうして生まれた薄い褐色こそが、セピア色の正体なのだ。いや別にセピア色は、正体を隠して皆を騙そうとしていたわけではないから、
「正体なのだ」などという糾弾は、完全な言いがかりである。
だがしかし、「いか墨色の思い出」という言葉に
郷愁やセンチメンタルを感じていた時間を返してほしいという思いは否めない。
昔、「一世風靡セピア」というグループがあったが、
こちらに関しても同じように残念な気持ちでいっぱいである。そんな、いか墨だが、食べ物としてはパスタが有名だ。
パスタの本場イタリアの古都ヴェネツィアの代表的な料理として知られている。いか墨のパスタ(2人前)
パスタ 160g
やりいか 1杯(皮をむいて輪切り)
いか墨ペースト(市販品) 5gオリーブオイル 大さじ2
にんにく 2かけ(みじん切り)
赤唐辛子 1本(みじん切り)アンチョビ ひれ2枚
白ワイン 大さじ4
こしょう 少々パスタのゆで汁 少々
- にんにく、赤唐辛子をオリーブオイルとともに弱火でじっくり炒める。
- いか墨ペーストとアンチョビを加え、白ワインでのばす。
- いかを加え、軽く温める。パスタのゆで汁を加える。
- ゆでたパスタを絡め、こしょうで調味する。
本当は、新鮮ないかを捌いて墨袋を取り出し・・・と出来ればよいのだろうが、
市販の「いか墨チューブ」でも十分おいしくできる。
「いか墨、いか内蔵、塩、酒」のみで作られているそのチューブを使うと、
すでに塩気があるので調味料としての塩は不要である。セピア色の思い出。
今後は、このパスタのことしか思い出さなくなりそうだ。