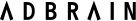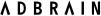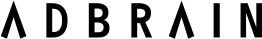-
第60の皿 星に願いを、梅おくら
季節の中で「終わり」があるのは、夏だけである。
春も秋も冬も、終わりを実感することはあまりなく、
気が付いたら次の季節に移行しているイメージ。
だが、夏が過ぎゆく時だけ、人は、季節の終わりを感じるのである。これは、「夏にしか出来ないこと」が、
他の季節に比べて格段に多いからではないかと思う。
海やプールなどの水遊び、花火やキャンプなどのレジャー、ビアガーデン。
高校野球も、センバツ大会が行われる春ではなく、やはり夏の風物詩である。
風鈴やすだれ、蚊取り線香、扇風機など、夏にしか使わないグッズの片付けも、
季節の終わりを実感する瞬間である。食べ物も、夏にしか食べられないものが多い。
たとえハウス栽培のものが春や秋に食べられるとしても、
「暑い時季に食べないと意味がない(うまくない)」ものが多いのだ。
かき氷、すいか、桃、ぶどう、冷やしトマト、とうもろこし、
枝豆、みょうが、そうめん、冷や麦に冷やし中華、
ガスパチョや冷たいポタージュ。おくら、もそのひとつだ。
今年の夏も、毎週のようにおくらを買い求め、そして食べ続けた。梅おくら
おくら 20本
梅干し 2〜3個ぽん酢しょうゆ 大さじ2
鰹節削り節 1つかみ
すり白ごま 少々- ゆでたおくらを1cm幅に刻み、ほぐした梅干し、調味料と和える。
シンプルなメニューである。
旬のおくらと、クエン酸豊富な梅干し。
夏は毎年これで乗り切っていると言っても過言ではない。おくらの切り口は、まるで星のよう。
なんともファンタジーな野菜である。
来年の夏も、おいしいおくらと出合えますように。
緑色の星に、そっと願いを込めてみた。
-
第59の皿 庶民の知恵で、焼き飯
炒飯と焼き飯。
「地域によって呼び名が変わるだけで、基本的に同じ物」
という説もあるが、個人的にはまったくの別物だと思っている。炒飯は、基本的にはプロの料理である。
おたまと中華鍋、ガスバーナーの強い火力で作るお店の炒飯は、
家庭料理とは比べ物にならないおいしさだ。焼き飯は、家庭料理である。
関西の粉もの文化を発祥とするらしく、
余ったごはんをどうやっておいしく食べるかということから始まった料理。
メニューとして掲げているお店もあるが、
大衆食堂や居酒屋など、アットホームなお店が多い。両者の違いは、調理法にも現れている。
卵とごはんをほぼ同時に入れて強火で一気に仕上げる炒飯は、
プロが作る超絶品から、素人が作る目の覚めるような激マズまで、さまざま。
一方の焼き飯は、誰が作っても、そこそこうまい。
卵を入れる前にごはんを炒め切るので、常に火がしっかり入るからだ。焼き飯(2人前)
ごはん 1合
豚バラ肉 250gのうち50g(短冊切り)※200gは別の料理に
ピーマン 1個(1cm角)
たまねぎ 1/2個(みじん切り)
卵 2個(溶いておく)油 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
黒こしょう 少々- フライパンに油を引き、たまねぎ、ピーマンの順に炒め、取り出しておく。
- フライパンに豚肉を入れてよく炒め、脂を残して豚肉を取り出す。
- 豚肉の脂を残したフライパンにごはんを入れ、焦げ目が付くくらいまで炒める。しょうゆ大さじ1を加えてさらに炒め、1と豚肉50g分を戻して混ぜ合わせる。
- ごはんを端に寄せ、空いたスペースに油を引き、溶き卵を入れて半熟くらいになったらごはんを載せ、卵をほぐすように混ぜる。卵に火が通ったらしょうゆ大さじ1を回し入れ、こしょうを振って味を調える。
ごはんをサクサクしたおいしさに仕上げるには、
豚の脂から抽出したラードを使うのが望ましい。
だが、ラードをわざわざ買ってきて常備するのも、健康的観点から抵抗がある。
そこで編み出したのが、多めの豚バラ肉をまとめて炒めて、脂を抽出する作戦だ。
焼き飯で使う以外の大半の肉は、野菜炒めなどに流用するのである。焦げたごはんとしょうゆの香ばしいおいしさに、
スプーンを口に運ぶ手が止まらない。
夏の休日の昼ごはんにぴったりの、食欲全開メニューである。
-
第58の皿 夏はアイスで、みょうがのみそ汁
「みょうが宿」という落語がある。
旅籠の夫婦が宿泊客から一晩大金を預かり、一計を案じる。
物忘れをしてお金を置いてってくれたらという思いで、
漬物からごはんからみそ汁まで、フルコースかというくらい
みょうが尽くしの料理を振る舞う。
しかし翌日、客は忘れずにお金を受け取り、出発してしまう。
「あれだけ食べさせたのにおかしいな」と首を傾げる夫婦は、
実は客から宿賃をもらうのを忘れていた。
強欲なものだから、昨夜残ったみょうがをたくさん食べてしまって・・・
というオチである。みょうがを食べると物忘れをするという俗説だが、もちろん根拠はない。
むしろ近年、その高い香りを放つ成分に集中力を増す効果が
あることがわかっているそうで、まったくもって言いがかりも甚だしい。お釈迦様の弟子の一人がとんでもなく記憶力に乏しい人物で、
自分の名前を忘れてしまうほどだったという。
そこで名札を首からぶら下げられたのだが、その事実すら忘れてしまう始末。
この名札のことを名荷(みょうが)といい、これと同音だったものだから、
このような濡れ衣を着せられることになったとか。そのみょうが、今が旬真っ盛りである。
みょうがの冷たいみそ汁
みょうが 6本(小口切り)
しめじ 1パック水 1000cc
和風だしの素(煮干し系) 1パック
みそ 大さじ3- 水を張った鍋を沸騰寸前まで沸かし、刻んだみょうがとほぐしたしめじを入れて火を弱め、あくが出たらすくっておく。
- みそだしを入れた器にゆで汁を加えて溶き、鍋に入れて弱火で軽く煮る。
- 粗熱が取れたら冷蔵庫に入れ、よく冷やす。
ある時、みょうがを具にみそ汁を作り、余った分を冷蔵庫に入れておいたのだが、
取り出して冷たいまま飲んだら、温かいものよりうまかった。
以来、我が家の夏の定番のひとつとなった。たっぷり刻んだみょうがの、清涼でさわやかな香り。
忘れさせられることはただひとつ、夏の暑さだけである。
-
第57の皿 この未熟もの、アボカドのパスタ
フルーツなのに野菜売り場に置かれている、ボーダーレスな食材。
それが、アボカドである。
英単語の綴りはavocadoだが、カタカナにすると濁音の位置が混乱するのか、
「アボガド」「アボガト」「アボカト」など、非常に間違われやすい名前でもある。並み居る植物食材の中で、アボカドほど品質が安定しないものは珍しい。
未熟・過熟は当たり前。
ちょうど熟れ頃のものを掴めるかどうか、
非常にギャンブル性の高い食材と言わざるをえない。過熟も困るが、天然のアボカドディップと思えばいい。
問題は、未熟だった時である。
開けてしまったものはどうしようもないし、
使う目的があって買ったものだから、どうにかしてこれを活かしたい。リカバリー法として考えたのは、角切りにして焼くこと。
火を通したところで完熟になるわけもないが、
「アボカド風味のじゃがいも」のような食感が生まれ、
別の用途を持った食材として復帰することができるのだ。今回のレシピは、開けてみた状態によって臨機応変に作り方を変える、
アボカドのパスタである。アボカドの和風ペペロンチーノ(2人前)
アボカド 1個
ほたて貝柱(刺身用) 1パック(1個を4分割=十字切り)
エリンギ 1パック(上下2分割して、スライス)
にんにく 1かけ(みじん切り)パスタ 200g
オリーブオイル(加熱用) 大さじ2
梅昆布茶 小さじ1
豆乳 大さじ4(牛乳でも可)
レモン汁 小さじ1/2
パスタのゆで汁 大さじ10白こしょう 少々
ゆずこしょう 小さじ1/4
オリーブオイル(生食用) 大さじ11. アボカドの皮をむいて種を取り、刻む。
a)生食でOKのやわらかさなら、ざっくり切り、
工程3のタイミングでフライパンへ。
b)生食できない未熟果だった場合は、角切りにして、
オイルを引いたフライパンに入れ、
弱火で10分ほど焼き色が付くまで炒める。2. フライパンで、オリーブオイルとにんにくを香りが出るまで炒め、
エリンギを加えて火を通す。3. 火を止めて、アボカド(1-aの場合)と調味料を混ぜ合わせ、軽く炒める。
パスタ投入から2〜3分経過したら、ゆで汁を加えてソースをのばす。4. ゆで上がったパスタを入れ、白こしょうを振ってから弱火で和える。
5. パスタを皿に取り分け、ゆずこしょうを載せ、アボカド(1-bの場合)と
ほたてを散らし、オリーブオイルを振り掛ける。
お好みでしょうゆをひとたらししても。要は、完熟ならクリーミーなソースとして使い、
未熟なら食材の一種として転用するのである。ギャンブルは、勝ったり負けたり負けたり負けたりするものだが、
アボカド勝負に関しては、なんとか引き分けには持ち込めるようになった。
-
第56の皿 BSから、フランセジーニャ
ドラマを毎週見る気力が薄れ、
バラエティ番組の笑いのツボがわからなくなってきた。
そんな世代の行き着く先が、BS放送である。
メインは、旅番組。
ゴールデンタイムのBSの番組表は
「紀行」「温泉」「鉄道」「ヨーロッパ」「大人」
「遺産」「世界」「旅」「歩き」「バス」「街」
などのキーワードに満ちていて、
これらの単語の適当なシャッフルで番組名が出来ているかのよう。地上波の旅番組の、いわゆる「旅人」方式だと、
視聴は旅人役のタレントの好感度に左右されるが、
BSの旅番組は、俳優によるナレーションが基本フォーマット。
たとえ主人公として旅をする設定であっても、
実際に本人が登場することはないから、画面の安定感がこの上ない。
逆に言えば、音声を消して番組を流した場合、
どの番組かを当てるのが極めて難しいとも言える。BSは、レギュラー番組でも新作の翌週に再放送を流すのがいい。
見たものを片っ端から忘れていく世代が多く見るBSならではである。
ある番組では最近、1年間のレギュラー放送終了後の翌週から、
第1回に戻って毎週の再放送を開始した。
これはいくら何でも、と思ったが、
やっぱり初めて見たかのように楽しめてしまうのだから、
今や立派なBS視聴者と言えるだろう。旅番組は、料理の参考にもなる。
世界の珍しい料理を取り上げつつも、
作り方を詳しく紹介するわけではないから、
見よう見まねでオリジナル料理を作り出すことができる。
たとえば、こんな料理。フランセジーニャ(2人前)
食パン(6枚切り) 4枚
溶けるスライスチーズ 4枚
ベーコン 2枚(ハーフサイズなら4枚)
生ハム 2枚(約20g)
卵 2個〈ソース〉
たまねぎ 1/2個(みじん切り)
にんにく 1かけ(みじん切り)
トマトケチャップ 大さじ4
タバスコ 5たらし
チリパウダー 小さじ1
ビール 100cc
ブランデー 大さじ4
薄力粉 大さじ1
水 大さじ3
オリーブオイル 大さじ1- フライパンにオリーブオイルを引き、にんにく、たまねぎを炒めてハンドミキサーの容器に入れ、なめらかになるまで回す。
- 1をフライパンに戻し、調味料を加えてソースを作る。
- 耐熱皿にパンを1枚置き、ベーコン、チーズ、生ハムの順に載せ、さらにパンで挟み、生卵を割り入れ、チーズを載せる。
- 2のソースを掛け、オーブン(余熱あり・200℃で15分)で焼く。
ポルトガルのポルト地方の料理だそうで、意味は「フランス娘」。
フランスに移民したポルトガル人が、
クロックムッシュやマダムを食べて発想したもので、
なんとこれはサンドウィッチのカテゴリーに入るのだとか。トマトソースは、辛いものが定番らしいので、タバスコを使ってみた。
挟む物は、スライスした牛肉やソーセージ、
えび、卵など、割と何でもアリのようだ。
ソースには、ビールもしくはポルトワインを使うのが決まり。
このボリュームの上に、現地ではフライドポテトまで添えるのだという。果たして、これが正しい味なのかどうかは、
永遠の謎であるが、BSが橋渡ししてくれた、未知なる食。
忘れた頃に、また作りたくなるおいしさである。