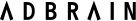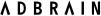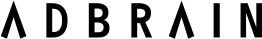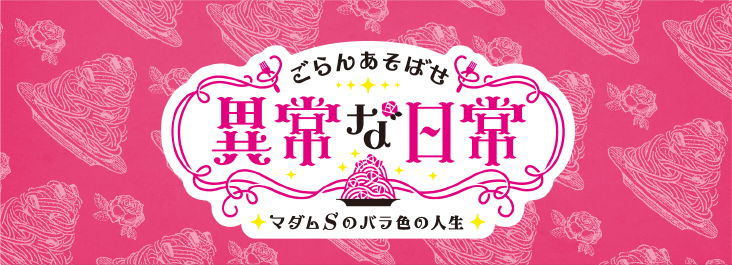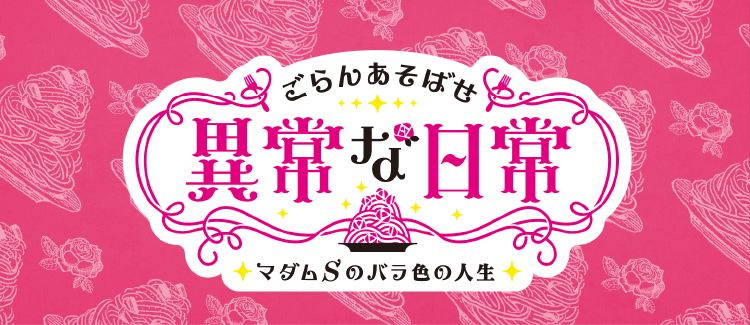-
振りたい回
早いもので師走になってしまいました。
今年も色々なことがあったような気がするのに、
年末になってもよく思い出せないのはなぜなのでしょう。今年、プロバスケットボールの「Bリーグ」というものが開幕しました。
その昔、Jリーグが開幕した時、一度だけ試合を観に行ったことがあります。
ジェフ市原と鹿島アントラーズの試合でした。
サッカーがそんなに好きではないはずの母と、
母の同僚の家族と行った気がします。
今思い出せるのは、スタジアムの上から見た人の小ささと、
両チームの旗を買ってもらったことくらいです。その頃のわたしはジェフ市原のファンで、さらに城彰二選手のファンでした。
まだサッカー選手が今ほどあか抜けていなかった時代。
恋人を「アモーレ」と呼んでもいなかった時代。
わたしは、ポケットサイズの選手名鑑を買って、
城彰二選手のページを眺めていました。
ふと思ったのですが、
もしかしたら城彰二が好きだったのは母かもしれません。
でも、最近聞いた好きな選手は「ネイマール」でした。
好きな理由としては、「顔がイケメンだから」だそうです。
Jリーグのチームの旗は、おそらく試合前に買ってもらったのでしょう。
試合中、なんとなく選手に向かって振ってみたりしたと思います。わたしは、子どもの頃から「棒に類するもの」が好きでした。
観光地の土産物屋に売っている十手から、
おじいちゃんがチラシをくるくる巻いて作ってくれた細い紙の剣から、
道に落ちているちょうどいい長さの木の枝から、
とにかくなんでも好きでした。Jリーグのチームの旗も、
細いプラスチック製の棒が旗の持ち手になっていて、
嬉しかった記憶があります。
帰ってから、家の柱に両チームの旗をがびょうで留めて飾っていました。たまにサッカーの試合をテレビで見ていると、
ゴールを決めた瞬間に旗がいっせいに上がりますよね。
あれを見ると、どこか胸がくすぐられます。
人の身長の何倍もある、視界をすべて遮るであろう大きな旗。
あと、あれもなぜだか胸躍ります。
日本酒のテレビCMに出てくる、大漁旗。
応援団の旗を振る人が好きだった、というのもあるかもしれません。旗って、かっこよく見えますよね。
棒状のなにかが人体に添えられると、
ビジュアル的におさまりがいいのではと思いました。宝塚では「旗」を振ることはほとんどありませんが、
トップスターが退団する公演の千秋楽では、
サヨナラショーと呼ばれるショーの終盤に
みんなでオリジナルのサイリウムを振る習慣があります。
アイドルのコンサートではウチワ、
最近のライブではタオルでしょうか。
人は隙あらば何かを振りたい性があるのかもしれません。今年もあっという間でした。
コピペを読んでくださり、ありがとうございます。みなさま、どうぞ良いお年を。

-
強烈な回
ドナルド・トランプ大統領が存在する暗鬱な世界に、
今、わたしたちは生きています。
Love trumps hate.「愛は憎しみに勝つ」
愛と憎しみに挟まれ苦しむトランプのアメリカのことを、
わたしはとても他人事とは思えません。
敗れたヒラリー・クリントンの言葉はネットで読むことができます。
ぜひ読んでください。
よく「舞台」というものを観に行くのですが、
そこで、めまいのするような強烈な体験をしたことが何回かあります。
今日はそんな話です。宝塚や歌舞伎、文楽といった
これまでこのブログで話をしてきたものを除くと、
その体験は3つほどあります。まず、中国障害者芸術団の「千手観音」。
ふたつめに、松尾スズキを見た「裏切りの街」。
そして、最近行った「るたんフェスティバル」。ひとつめで覚えているのが、
観に行ったその日は雨だったということと、
わたしは遅刻して行ったということです。今はなき「新宿コマ劇場」に初めて足を踏み入れたのが、この時でした。
詳細はもうぼんやりとも思い出せません。
ただ、コマ劇場の内装の淀んだ空気や、
うす暗いロビーに毒々しく映えていたくすんだ赤色が、
大事なワンシーンのようにまぶたに浮かんできます。とても後ろの席でした。
腰を下ろすと、舞台ではその時、
片腕のない男の子が見事な身体能力を発揮して、
全身を柔軟に使ってポーズをとって静止していました。
熱い拍手喝采がおくられています。「…まだ見る?」
そう聞かれて、わたしはふと我に返り、もう出ようか、と答えました。
目的だったはずの千手観音が
もう終わってしまったのかどうなのかもわからないまま、
わたしは再び席を立ち、
熱狂と言っていい独特な雰囲気が渦まく会場の扉を開け、
ひんやりとしたロビーへ出ました。コマ劇場には、30分もいなかったでしょう。
それでも疲労の重みを肩に感じ、
何かからピンとはじかれるような気持ちで肌寒い雨の新宿へ出ました。
劇場に充満する空気に、
なじむことができなかったのだと思います。帰り道、新宿の町は無言で歩いていても、
勝手に話しかけてくるようでした。
でも、そのどこへも向かわない乾いた喧騒のほうが、
わたしにはむしろ心地よいものだったのを思い出します。ふたつめの「裏切りの街」という舞台は、
松尾スズキが出演していました。
確か、この時に初めて松尾スズキという人が
実際に動いているのを観たのです。PARCO劇場の、これもかなり後ろの席でした。
舞台上でガラガラガラとうがいをしていた松尾スズキが、
あまりに強烈なものを放っていて、
わたしは頭が混乱しました。
禍々しいもの、見てはいけないようなもの…。
現実におそろしい裂け目を作るような人でした。みっつめは、ごく最近です。
会社からほど近いホールで、
シャンソンのコンサートがありました。
お誘いいただき行ったのですが、
これが実に興味深く、また忘れられない体験でした。わたしのシャンソンに関する知識はゼロに等しく、
よく観る宝塚の舞台で使われている曲に耳なじみがある程度。
初めて聴く歌がほとんどでした。
第1部と第2部に分かれていて、
第1部のトリで歌ったのは、わたしの敬愛する安奈淳さん。
圧巻でした。
驚くべき表現の力。
もちろん、ほかの出演者の方も、
みなさん歌が上手いのです。
でも、上手い以上の「何か」が、安奈淳さんの小柄な身体から放たれている。
その劇的な求心力に、磁場が歪んでいくような何か。それは、第2部でより顕著でした。
強烈な個性が、次々に登場します。
よく映画で、主人公が知らずに迷い込んでしまう
奇妙な地下やバーがありますよね。
時代も時間もそこにいる人々もどことなく不吉で、
日の光が届かない不思議な場所。
あの日のヤクルトホールは、
そんな異世界と地続きだった気がします。
自分もそこにのみこまれてしまったと錯覚するほどでした。シャンソンの奥深さは、
歌う人の人生がそのまま出てしまうところなのだと思います。
やはり、第2部の人生経験値高めの方々は、
こちらから求めずともその人の人生がぐいぐいと押し寄せる。
人生は、チーズと一緒です。
熟成すればするほど、鼻がもげそうなくらい強烈な匂いを放つ。
日本語のシャンソンというのは、
演歌とも歌謡曲とも異なる独自の「クサみ」を持つ芸術なのだと、
ドレスアップし濃いめのお化粧を施した
淑女たちを見ながら感じ入りました。自分が観たいものしか観ない、聴きたいものしか聴かない。
人生は短いのだから、仕方ないのかもしれません。でも、誘われたら行ってみるものですよ。
美味しい熟成チーズと、
のどを唸らせるワインに出会える可能性もそこにあるのだから。 -
信頼の回
いま、日本で最も影響力を持つ人はだれなのでしょうか。
なかなか難しい問いです。
リオ・オリンピックの頃は(もう遠い昔のように感じられますが)、
メダリストたちの影響力がとても大きかったように思います。インフルエンサーという言葉が流行りだす前から、
「この人が言うことなら信じられる」という人は存在していました。最近「タモリさんのピーマン」というレシピをクックパッドで発見して、
それを実践してみているわたしにとって、
「タモリさんの」「タモリさんが認めた」「タモリさんが訪れた」
という枕詞は非常に魅力的だなと思います。
だって本当に美味しいんですよ、タモリさんのピーマン。今年の夏、博多に小旅行に行ったときも、
「タモリさんおすすめ」のごぼう天うどんのお店に行きたくて
1ヶ月くらいずっとそのお店の食べログのページを見続けていたのですが、
残念ながら時間がなく…行くことは叶いませんでした。
でも、地元の方に紹介してもらったチェーン店で食べた
ごぼう天うどんもとっても美味しくて、
「博多への移住」というワードが脳裏をかすめました。先頃の三連休にも名古屋に行ったのですが、
SNSで見かけた美味しそうなカレーうどん屋さんにどうしても行きたくて、
無理やり同行者を連れて入ったそのお店にも、
偶然ですがタモリさんの写真が飾ってありました。名店にタモリあり。
その店のカレーうどんは見た目が美しくて、
ルーの味はスパイシーながら品があり、
厚揚げとネギとこまぎれの豚とうどんがルーと素晴らしく絡み合い、
お店を出た瞬間に、
むしろ食べおわった瞬間に、
「また食べたい!」という強い衝動に駆られてしまったほどです。
あぁ…思い出すだけでよだれが。どんなに食べログの評価が高くても、
「タモリさんが行きつけ」の一言にはかなわないでしょう。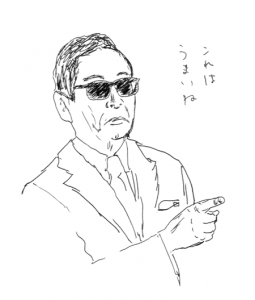
タモリさんが町をブラブラするブラタモリが好きなので、
その食エンターテイメント版として、「タベタモリ」も制作してほしいです。ミシュランの星を気にするようになった頃から、
だれしも自分だけの名店・ジブンミシュランがあると思うのですが、
そんなものをうっちゃって一度は行きたい、
それが「タモリさんが行くお店」です。
タモリさんへの信頼は絶大です。ところで、
わたしはいつから「タモリさん」と、
さん付けで呼ぶようになったのでしょうか。
昔はタモさん、と言っていたような気がします。
もっとおまえ誰だ感がある呼び方ですね。今日の夕ご飯はタモさんのピーマンを作って、
タモリさんの偉大さを噛みしめたいと思います。 -
「ジョナサンズ」の回
あなたはなにかを「解散」したことがありますか?
以前、父親から「解散!」と告げられて
家族が解散した芸人の本が大ヒットしましたが、
わたし自身はなにかを解散したことはありません。“国民的グループ”は年内の解散を発表しました。
「解散」という字から受ける衝撃はまことに強いものです。内閣が解散したり、衆議院が解散すれば、それに伴う形で選挙がある。
でも、最も大き関心をあつめている今回の「解散」には、
そのあとの選挙がない。
日本人は概して「解散」に弱いのだと思います。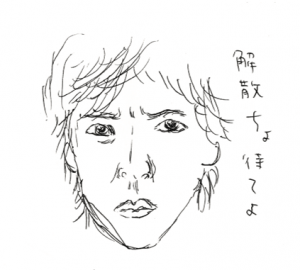
(今回はトレースではなく写真を見ながら描いてみました。)
同じような意味合いで「卒業」もありますが、
昨今の「卒業」というのは母体はまだ現存しており、
メンバーだけが新陳代謝していくようなことが多いため、
その母体を愛している人間にとっては
メンバーの卒業はつらくとも、
思いを寄せる対象が依然として残るので傷は浅いような気がします。「解散」
なかなかどうして、寂しい気持ちにさせられる言葉です。冒頭の質問に戻りますが、
わたしはなにかを「解散」したことはありません。ただ、よく思い返してみると、似たようなことはありました。
中学生の頃、ことあるごとに
「ジョナサン」というファミレスに集まっていた女子グループ。
わたしも、そのグループのメンバーの一人でした。今でこそ、人が何かしらの様々なグループに属することは普通になりました。
SNSなどでのネットワーク上で同じ趣味の人とつながったり、
同じミュージシャンを好きなもの同士でつながったり、
好きなゲームをするもの同士でつながったり。
でも、このように「つながる」ことが容易になるもっと前、
インターネットの海にまだ放たれていなかった
中学生もまた、自分たちをグループ化して名づけ、
カテゴライズすることで仲良し度を確かめるようなことがあったのです。わたしの属していたグループ名は、その名も「ジョナサンズ」。
ジョナサンで集まっていたから、ジョナサンズですね。
ひねりもなにもなくてここに載せることも黒歴史を公開するようで恥ずかしいですが、
ジョナサンズだったのです。ジョナサンズは、女子5人ほどのグループでした。
活動内容(!)はもはや忘却の彼方なのですが、
ただ集まって、しゃべって、クラスの噂話などをするだけだった気がします。
それこそ国民的アイドルグループで誰がいちばん好きか、
というような話題で盛り上がったかもしれない。
それに、もしかしたらクラスの「出し物」みたいなものを
主導したりしたのかもしれませんが、まったく憶えていません。
何もやっていなかったのだと思います。そして、高校生になり、自然と「解散」しました。
解散理由は音楽性の違い、価値観の相違など、
まぁひと言で言うと…特になかったと思います。
それぞれ別の高校へ進学することになり、
「ジョナサンズ」である必要がなくなったんですね。
そりゃそうですよね。中学卒業後、
「久しぶりにジョナサンズで会おうよ」というお誘いも幾度かあったような気がしますが、
顔を出すことはありませんでした。個別で誰かと会ったような記憶もあります。
でも、新興宗教の名前をぽろっと出されたり、
結婚して早くに子どもができて夫は…など
久しぶりに会って聞く話題としては気が重く、
それからは誰とも会わなくなりました。人は、永遠になにかのグループにいる、
ということはできないように思います。
その時をとどめておきたいとグループを作っても、
時の流れは残酷なもので、人も、心も、関係も絶えず変化していく。
どこか歯車が錆びつき、うまく回らなくなっていく。
それぞれの人生がいろいろな意味で複雑化するうち、
純粋に「懐かしいから」という理由だけでは会いづらくなっていくのです。わたしも、そういうふうに考えるような年になったのです。
そう思うと「解散」はむしろ、必然的な営みなのでしょう。
グループであったその時間をかけがえのないものにするために、
それをいつか一人で懐かしむことができるように、
わたしたちはいずれ「解散」しなければならないのかもしれません。 -
夏が来た回
リオオリンピックが始まっていますね。
わたしのイチオシは「吊り輪」です。
自分の筋肉だけで自分の体重を支えて水平になるのがやばいです。
ものすごいです。
あと、やっぱり内山選手のワキに注目してしまいます。
色白だから余計にそこに目がいってしまうんです。
金メダルおめでとうございます。さて、最近、このオリンピックでお休み中なのですが、
朝ずっとあるラジオを聴いていました。
その名も「夏休み子ども科学電話相談」。Twitterなどで去年ツイートを見かけていて、
なんだか面白そうだなぁと思っていたので
今年初めてチャンネルを合わせてみました。
朝、通勤電車の中で聴くとあまりに面白くて
本を読む手が止まってしまい、悩ましい状態です。子どもたちの素朴な疑問・質問にその分野の専門家が答えるという、
しごく単純なラジオ番組なのですが、これがなかなか奥深い。子どもたちの質問の多くは、
大人たちが考えつかないものなのです。「風はどこから吹いてくるのですか?」
「どこからが空なのですか?」
「人間はサルだったって本当ですか?」
もちろん、誰しもが一度は考えることかもしれません。
でも、私たちは検索して答えを見つけてしまったり、
日々の忙しさによって疑問に思ったことさえ忘れてしまう。子どもたちはちがうんですね。
「なんでだろう、なぜそうなるの」という気持ちをいつもホットに持っていられる。
それは「好奇心」ということだと思うのですが、
子どもたちの観察力は本当にすごいんです。
わからないことをわからないからといって拒否するのではなく、
それをまず心に受け入れるんですね。
目で見て、手で触れて、鼻で嗅いでみる。
地面はずっと近くて、自然はすぐそばにあるのです。
そのことに、大人である私たちが気づかされる。
私たちが生きているのは、地球の上で、
人間だけではない動物や植物やあらゆる生物がいて、
たくさんの命が、そこに息づいているのだと。ラジオなので、声と声のやりとりなんですが、
子どもたちの白玉のように柔らかな声が耳にくすぐったいです。
子どもたちに一生懸命に説明する先生たちの声も、
同じように優しくて、すごく楽しそう。
先生たちはプロフェッショナルなので、
子どもたちの質問には必ず、答えてくれます。
でも、「それはわかっていないんだ」とか
「僕も不思議に思っているんだよ」とか、
解明できていないことや諸説あることは
素直にそれを認めて、教えてくれるのです。
あぁ先生も子どもだったのだなぁ、と感じる瞬間です。「ちょっと言うてみて、ヘモグロビン」
「ヘモグ…」
「ヘ モ グ ロ ビ ン」
「ヘモグロビンー!」実際の場面ではヘモグロビンではありませんでしたが、
子どもに現象や物質の呼称を復唱させようとする先生がいて面白いです。大人になったとしても、わからないことはある。
研究し続けても、まだ到達できないこともある。
それでも、「なんでだろう、なぜそうなるの」という気持ちで
あきらめずに答えにアプローチしていくこと、
それをできる人だけが、子どもたちの心に答えることができる。大人も、「好奇心」がすり減っていないか、
感性のみずみずしさを試されているのですね。“大きすぎるおともだち”であるわたしはもう電話をかけられませんが、
もし子どもだったら…「タイムマシンは完成されるのでしょうか?」
という質問をしてみたいです。
先生、どうかよろしくお願いします。