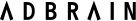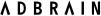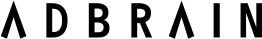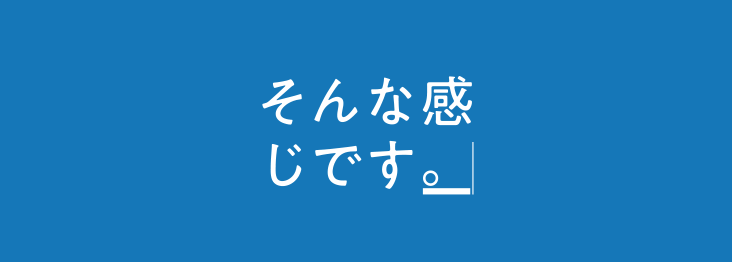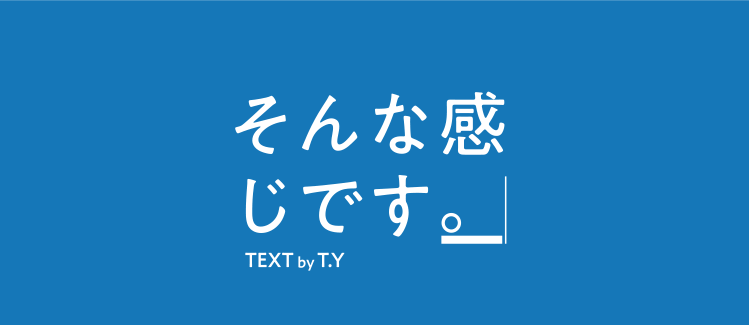-
木刀を経験したことがあるか
僕が学校に通っていた頃は、憧れのお土産といえば木刀でした。
木刀。文字通り、木でできた刀ですね。
別に地方の特産品なわけじゃありません。
剣道部員でもないかぎり、日常生活で使うことは皆無。
買う前から、いらないのが完全にわかっている。
しかも、確実に自分用だから、
他の人に渡す用のお土産を別途買わなくちゃいけない。
冷静に考えるほどに、お土産に買うにはリスクが高すぎる。
それなのに、嗚呼それなのに、
男子学生にとっては、というか僕にとっては、
どうしても惹かれてしまうアイテムの一つでした。人生の中で、何度か修学旅行に行きました。
そして、ほぼ必ずお土産屋さんで木刀を見かけていました。
買うチャンスはいくらでもあったのです。
でも、僕には買えなかった。
どうせ買っても先生に没収されるし、
もしかしたらみんなに笑われるかも。
頭に次々と浮かび上がってくるデメリットの嵐に、
僕はいつも負けてしまったのです。
他の同級生も、惹かれながらも結局諦めるやつばかりでした。しかし、そんな僕らをしりめに、
幾多のデメリットを飛び越えて木刀を買う猛者が
中学生の頃に現れたのです。
同じ部活に入っているO君でした。集合場所にO君が戻ってきた瞬間、
僕は心の中で「あっ!」と叫びました。
自由行動の前には持っていなかった、
明らかに不自然な細長い物体が右手に握られている。
あ、あいつ…やり(買い)やがったな……!
他の同級生も、当然、木刀に気づきます。
周りから「すげえな」「バカじゃないの」と言われるO君は、
明らかに嬉しそうで満足そうな顔をしていました。そんなO君の誇らしげタイムはあっという間に終焉を迎えます。
担任の先生に木刀を没収されてしまったのです。誰もがこうなるとわかっていたと思います。
O君だって、没収されるなんてわかりきっていたはず。
それなのに、彼は木刀を買った。
木刀という“ロマン”を、たとえ短い時間でも所有する道を選んだO君が、
僕にはとてもまぶしく輝いて見えました。
たしかに、ムダなお土産だったかもしれません
(持ち帰れてないから、お土産にすらなっていないかも)。
けれど、そのムダを経験したおかげで、これからの人生を
「お土産に木刀を買ったことがある人間」
というレアな存在として歩んでいくことができるわけで。
それが当時の僕にはとても羨ましかった。
と同時に、すごく不思議にも思っていました。
あいつ剣道部のくせに、なんでわざわざ木刀なんて買ったんだ?と。某漫画の影響か、今でも木刀はそこそこ人気のお土産のようです。
ヤ○ー知○袋を覗いてみると、中学生らしき人が
お土産に木刀を買いたいと相談していました。
回答欄は「やめておけ」「お金を大切にしろ」など
否定的な意見ばかりでした。
しかし、僕はあえて言いたい。
買ってもいいんだよ。
別に実用的じゃなくてもムダでもいいじゃないですか。
お土産は、ロマンなのですから。 -
制服の○○
中学の時は学ランを、高校の時はブレザーを着ていました。
毎日同じ服を着なければいけない。
しかも、決まった着方をしなくちゃいけない。
なんだか不自由で窮屈だなー、いやだなーと当時思っていました。
(たかが服装のことなのに、まるで鬼の首をとったように
注意してくる先生の表情が負の感情に拍車をかけていた気がする)
ちなみに窮屈と言いましたが、実際は
わりとゆったりとしたサイズ感で着ていました。
理由は、まあ、そういうことです。身長的なね。大学進学を期に一人暮らしを始め、
制服ともおさらばしたわけです。
毎日好きな服を、好きなように着られる!
はじめはウキウキしていたんですが、やがて
ある面倒なことに気がつきます。洗濯です。
あたりまえですが、自分で着たものは自分で洗濯しなきゃいけない。
服をたくさん着るほど、洗濯の回数も増える。
とくに苦労したのがシャツ。
襟や袖ってこんなに汚れるのか、と唖然としました。
ただ洗濯機に入れただけじゃ汚れが落ちきらなくて、
専用の液体をつけて直接こすったりしなきゃいけない。
なんて面倒なんだ、シャツの洗濯…。
社会人1年目は営業だったので、毎日白いシャツを着ていたのですが、
その頃は洗濯がもう本当に苦痛でした。そういえば、中高は毎日白いシャツを着ていました。
つまり、我が母はほぼ毎日シャツの汚れと格闘していたわけです。
大変だっただろうなと思います。
「首と手首まわりをしっかり洗いやがれ!」
と怒られていたのも、今となっては納得です。制服の下の白シャツ、せめて襟と袖の裏は
色つきのものOKにできないものでしょうか。
そうしたら、世のこどもがいる家庭の負担が
けっこう軽減できると思うのですが。
もしくは、思いきって柄シャツを…
アロハとかハワイの正装ですし…いや、やりすぎか。あれ、おかしいな。
制服がテーマということなので、
過去の学校生活の話を書こうと思っていたのに、
いつの間にか洗濯の話になっていました。
まあ、そんな感じもたまにはいいですよね。 -
自主的定期
学生時代と比べると、めっきり雑誌を買わなくなってしまいました。
単行本や文庫の購入頻度はさほど変わっていないけれど、
雑誌はもう、目に見えて減った。単純に雑誌を読める時間が少なくなった…
ということもあるかもしれません。
平日の大半を占める勤務時間中に読めばいいのでは?
いや、他の本は平気でも、なぜか雑誌は読みづらいんです。
じゃあ休日は?
いやいや、他にやりたいことがあったりするんですよ。
残るは会社に行くまでの通勤時間ということになりますが、
電車の中で雑誌を読むのはどうにも気恥ずかしくって。
誰もおまえが何読んでるかなんて見てないよ!
という指摘はもっともなんですが、まあ気になるんだからしょうがない。
そんな感じでヘリクツを並べ
雑誌から離れていたわけですが、はたと気づきました。このままでは、いつか雑誌どころか
本そのものを読まなくなってしまうのでは?…さすがにそれはマズイ。
職種的にという前に、社会人としてもマズイです。というわけで、ものは試しで、
最近は雑誌を定期的に買ってみることにしています。
具体的には、毎週土曜日にコンビニまたは本屋に行き、
気になった雑誌をランダムで購入しています。
読むかどうかの心配はひとまず置いておいて、
まずは買う習慣づけをする作戦です。最初は続くかなあと心配でしたが、
今のところ続けられています。
なんだかんだ言って、毎週土曜日に
お楽しみが待っている感じがして、ちょっとワクワクするんですよ。
先週はこれ買ったから、今日はこっちを買ってみようかな…
と考えるのが意外と楽しい。ただ、好奇心を信じすぎてしまうと、大抵失敗してしまいます。
この前は「どうせなら今まで一度も買ったことないものにしよう!」
と息巻いて某クルマ情報誌を買ったんですが、
部屋につくなり興味を失ってしまって、文字通り1ページを開いていません…。完全な思いつきだったけど、
意外とうまくいっている自主的定期購読。
これからも、しばらく続けてみたいと思います。しかしですよ、いざ買おう!と決めて棚を眺めてみると、
あらためて雑誌ってさまざまな種類があるんですね。
日本雑誌広告協会というところが出している資料を見ても、
その数がとんでもないことがわかります。
これだけ数があると、選ぶだけでもタイヘンです。
おすすめの雑誌をピックアップしてくれるアプリとかないんですかね。 -
遊園地といえば○○○?
人生、これができたらもっと楽しめそうだなあ…
と考えることがいくつかあります。例えば、お酒をもっと飲むことができれば。
世の中には美味しいお酒がゴマンとあるのに、
すぐに酔っ払ってしまう自分には、それを味わう余裕がない。
一度でいいから酔いつぶれてみたい。吐いてみたい。
などと言う人も、世の中にはいるようで。
その体質がなんとも羨ましいものです。それから、今回はこっちが本題なのですが、
絶叫マシーンが得意だったらよかった。
まったく乗れない、というわけではありません。
乗ってしまえば、楽しいし、爽快感がサイコーなのも知っています。
けれど、どうしても恐怖心が芽生えてしまうのです。親の話によると、元々は絶叫マシーンに乗るのが
むしろ好きだったようです。
ただ、どこかのタイミングで急に嫌がりだしたらしい。
幼い頃の自分に、いったい何があったのか。小学6年生の時点では、もう嫌だった記憶があります。
家族旅行で東京ディズニーランドに行ったのですが、
絶叫マシーンばかりで大変な目にあいました。
なかでも一番おそろしかったのは、スペースマウンテン。
列に並んでいる時に見た看板の中に
「ハイスピード」というワードを発見して、
えらく狼狽、戦慄したことを覚えています。どうしてみんな、わざわざ怖い目にあうために何時間も並ぶのだろう…?
列に並んでいる人達がなぜ笑っていられるのか。
絶叫マシーンに乗るたびにぐったりしていた自分には
不思議でしょうがありませんでした。遊園地=絶叫マシーンなのでしょうか。
いや、僕はあえてNOと言いたい。
ザ・遊園地アトラクション、それは観覧車でしょう。観覧車はいいですね。
載っている間ゆっくりを景色を楽しめます。
まるで空中のオアシス。
慌ただしく騒がしい遊園地の中で、
ゆったりできる落ち着いた時間は貴重です。
目玉になるような特徴的な楽しさはないかもしれない。
けれど、小さなこどもでも乗れて、家族で楽しめるのもポイント。
あと、なんといっても見た目がもう
遊園地っぽさ満点なのが良い。ただ、一つだけ観覧車に文句を言いたい。
世間には床が透明なシースルーゴンドラなるものが
存在しているみたいですが、それほんとに必要ですか?
上空十数メートルで透明な箱に閉じ込められるとか、
もはや絶叫マシーンでは?
かんべんしてくれ…ください。前回は、夏は海にでも行こうかと書きましたが、
仙台に観覧車乗りに行くのもいいんじゃないかと思ってきました。
ここね。
ありがたいことに、イーグルス首位ですしね。 -
海が○○○○
普段は使わないような言葉の組み合わせが好きです。
例えば、数年前の宣伝会議賞グランプリの部長が目にしみる。 (シービック / デオナチュレ男シリーズ)
単語と動詞の距離感が秀逸ですね。
「部長が臭い」と直球で言うより
伝えたいことがずっと理解できるし、チャーミング。
見た人の印象にも残りやすい。このような独特な言葉の組み合わせ方は、
なにも広告コピーだけのものじゃありません。
映画のタイトルや歌詞でも使われています。さて。今月のお題は「海」。
どんなことを書こうかな…とぼんやり考えていたら、
ふと、学生の時に見たジブリのアニメ『海がきこえる』を思い出しました。正直なところ、どんな物語だったのかはうろ覚えです。
高知から上京してきた大学生の主人公が、
地元で同窓会に参加したりするうちに、
高校の頃東京から転校してきた女子との記憶を思い出す…
という内容だったような。ジブリっぽくない(偏見)絵柄でめずらしく感じた。
自分も主人公と同じく地方から上京してきた大学生だった。
というのも見るきっかけだったと思います。
けれども、なにより僕が気になったのはタイトル。
「海」が「きこえる」って、どういうことだ?おそらく「海」は主人公の地元・高知の海で、
地元を思い出すことを「きこえる」と表現しているのでしょう。
そんなに難しいことを表しているわけじゃない。
けれども、想像力を刺激するような響きがあるし、
ぶわーっと感情が広がっていく趣きがあった。
海よりは山に慣れ親しんで育った自分でも、
なんだか懐かしい気持ちになってくる。
当時の自分がどこまで思い至っていたかはわからないけれど、
とにかく強烈にぐっときたのは覚えています。
もしかしたら、タイトルの印象が強すぎたから、
物語の記憶があいまいなのかもしれません。タイミングがあえば、
今年の夏に帰省した時は海でも見てこようかな。そういえば、地球から海がなくなったらどうなるんですかね?
元は海底だったところから比べると、
人間が住んでいる土地は軒並み高地になってしまいますよね。
そうなると、気圧ってどうなるのか?
富士山やエベレストの標高がたいへんなことになるのでは?というような完全な余談を最後にして、
今回は終わりにしたいと思います。ではまた。