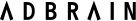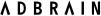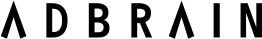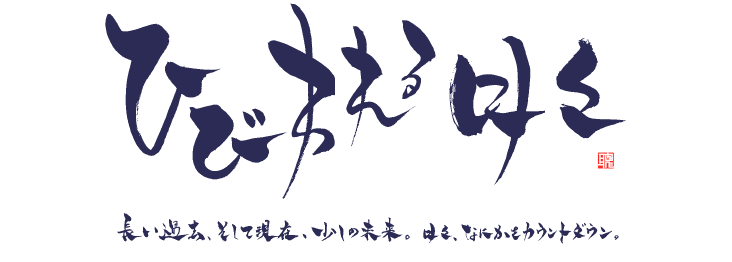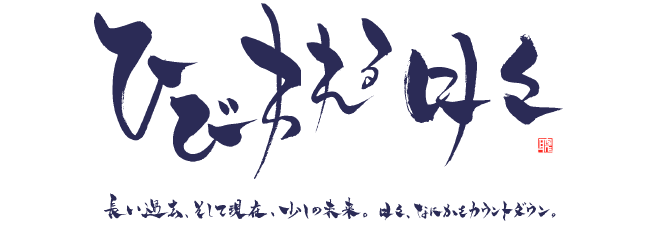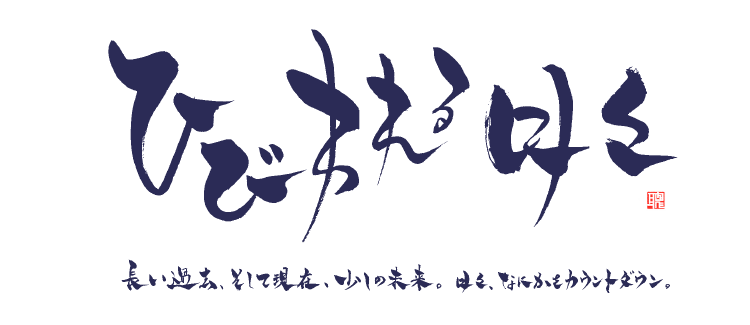-
走る日々
ちょっと羽目を外して飲みすぎて、足元がおぼつかなくなって、
転んで膝を擦りむきました。いい年をして。
血がにじむ膝に消毒液を塗ると、傷口に染みてすーすーしますよね。
そんな時に言います、「あー、はしる」、と。
あのちょっとうずくような身もだえするような感じは、
「しみるー」では伝わりません。「はしる」です。
「あー、はしるわー」なんです。私が育った町の方言です。
標準語では伝わりにくい、方言が持つ、独特のニュアンスがあります。
毎週楽しみに「走る」人の行方を見守っている、
大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』。
脚本の宮藤官九郎は2013年に手掛けた朝ドラ『あまちゃん』でも
「じぇじぇじぇ」という、
喜怒哀楽のどのニュアンスにも使い勝手のいい東北の方言を取り入れたように、
今回も既に印象的な言葉を電波に乗せています。
中村勘九郎演じる、主人公の金栗四三、
彼は生まれ育った熊本の言葉を話します。
「とつけむにゃあ」。初めて聞きました。
とんでもない、という意味の形容詞のようですが、
田舎育ちの彼にとっては大都会・東京も、
役所広司演じる恩人である加納治五郎も、
天狗倶楽部の三島弥彦が住む豪邸も
綾瀬はるかの絶対的なかわいさも、すべて「とつけむにゃあ」のです。
そして、毎回「すーすーはーはー」と呼吸しながら走りに走って、
とうとうストックホルムへ。
日本人初のオリンピックのマラソン選手になる彼もまた、
「とつけむにゃあ」男です。
『いだてん~東京オリムピック噺~』、
まだ前半が始まったばかりですが、
大河ドラマとしては視聴率があまりよくないらしく、
明治と昭和を行ったり来たりする展開に視聴者がついてこれないだの、
主人公が有名人でないからいけないだの、
古今亭志ん生を演じるビートたけしの滑舌が悪いだの、
来年開催される東京オリンピックのプロパガンダじゃないのかだの、
何かと外野がうるさいようです。
ちなみに、わたしがこうして熱く語っていることは、
『いだてん~東京オリムピック噺~』のプロパガンダです。
とにかく、今からでもまだ間に合います。
観て、おもしろいから。これからもっとおもしろくなるから。
阿部サダヲももっと出るから。
必死ですか、そうですか。
この大河ドラマの制作が発表された3年前に書いたブログの
一部を以下に引用します。
《そんなすっかりNHK世代になったわたしに、朗報が飛び込んできました。
それは2019年、
3年後の大河ドラマの脚本を宮藤官九郎が手がける、というもの。
『あまちゃん』の大ヒットで、みなさまのNHKにも認められた
クドカンが手がける大河ドラマに期待しないわけにはいきません。
しかも取り上げるのは戦国武将でも、天下人でも、幕末の志士でもなく、
2020年の東京開催を控えた「オリンピック」史のようなもの、らしいです。
もうこれだけで、わたしのアタマの中は妄想だらけです。
阿部サダヲを主役に、その息子を菅田将暉が演じ、
後は古田新太とか星野源とかピエール瀧とかそこら辺、
それから歌舞伎界から誰か若手を起用、
大体5人ぐらいを主軸にして、
タイトルは『五輪ジャー(仮)』でどうでしょうか。》
毎度同じようなことばかり書いていますが、意外と当たっていることもあり、
宮藤官九郎信者であるわたしは、
『いだてん~東京オリムピック噺~』の視聴率が走り出すことを
切に願っています。
しかしわたし自身は、電車の扉が目の前で閉まりそうになろうが、
待ち合わせに遅刻しようが、もう走り出すことはあまりありません。
いつからか、転ぶことを恐れるようになりました。
もちろん肉体的にですが、よく考えると精神的にもそうなのかもしれません。
この年になると、肉体と精神、
いずれの傷にも効く薬が少なくなってきたように思います。
「あー、はしるわー」と身もだえながらも、
塗ればすぐに治る消毒液があるといいのに。
-
31の日々
あっという間に2月になってしまいましたが、
どうやら平成の30年間を生き延びたようで、
平成31年、2019年を無事に迎えることができました。
とはいえ、いつからか新年を迎えるたびに思い出す
「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」と、
いう歌があります。
一休さんとして知られる僧、一休宗純が詠んだと言われる歌で、
新しい年を迎えたと言って門松を立ててよろこんでいるけれど、
年をとるということは裏返せば死へ向かっているということで、
めでたいことばかりではない、どうせいつかはみんな冥土へ行くんだぞ、
といったお屠蘇気分に冷や水をぶっかけるような皮肉が、
平成31年と数を同じくする、
この三十一文字(みそひともじ)の中に込められています。
天皇陛下の退位が決まって、平成という時代が終わるということを、
頭の中では理解していたつもりでした。
しかし、しみじみとそれを感じたのは
昨年12月23日の平成最後の天皇誕生日での会見で、
陛下のお言葉を聞いた時でした。
「天皇としての旅を終えようとしている今」、
「自らも国民の一人であった皇后が、私の人生の旅に加わり」、
旅という言葉を使ったこれらのお言葉は、
凡百のコピーライターには到底書くことのできない
深く重みのある表現だったと思います。
私のようなものが言うのもおこがましいですが。
4月1日に新元号が発表され、
平成31年は、この4月30日をもって終わることが決まっています。
昭和が64年の1月に唐突に終わってしまったことを覚えている人間にとっては、
この平成最後の31年、そのまた最後の4カ月間というのは、
高校から大学に入る時の春休み、自分が何者でもなかった時の
ふわふわした気分を思い出させてくれます。
いよいよリアリティを持って“平成最後の”という枕詞が使われるようになり、
メディアでもこの30年間をまとめるような番組や特集がたくさん組まれ、
平成を見送る熱はどんどん高まっていくことでしょう。
そのひとつの到達点は、昨年の大晦日12月31日の、
“平成最後の”「NHK紅白歌合戦」だったのではないでしょうか。
わたしたちは久しぶりにリアルタイムで紅白を観ようと、
風呂にも入り、年越しそばも食べ、万全の態勢で臨みました。
出演順をネットで確認しながら、
前半は全体的に背景の映像やダンサーたちが邪魔で
「画面からあふれる情報量が多い。メインの歌手やその歌声が頭に入ってこない」と
文句を言いながらも、なんだかんだ楽しいお祭り騒ぎとして堪能。
そして楽しみにしていた後半、椎名林檎と宮本浩次のデュエット、
松任谷由実のスペシャルメドレー(バックバンドの豪華さも必見)、
星野源、米津玄師、MISIAの圧巻の流れ。
そして紅組でも白組でもない、
言わば平成のトリとして出てきたサザンオールスターズ、
とそこに堂々と絡んでいった松任谷由実。
平成という時代の忘年会を締めたのは、嵐でもAKBでもなく、
昭和のおじさんとおばさんでした。
しかし、そのおじさんとおばさんは桑田とユーミン。
平成って本当にあったんでしょうか。この30年間はなんだったんでしょうか。
幻だったんじゃないでしょうか。
では、最後にわたしも三十一文字。
SMAPも安室も出ない紅白で
トリ務めしはサザンとユーミン
そしてこのブログを書き終わってから、嵐の活動休止が発表されました。
何もかも終わっていきますね。
2019年、平成のうちにユーミン、
次の元号になったらサザンのライブに行きます。
-
カウントダウンの日々
先日、自宅の最寄り駅に降り立ったら、
改札を出たところに見馴れぬオブジェができていました。
ラグビーボールをかたどったそのオブジェには
「ラグビーワールドカップ2019™ 開催まであと277日」と記されていて、
日にちの部分は数字がカウントダウンされていく仕様になっていました。
私が住んでいる街にはトップリーグの強豪、
“東芝ブレイブルーパス”と“サントリーサンゴリアス”があり、
2019に向けて「ラグビーのまち 府中」として
さまざまな活動をしていくようです。
ルールもよくわからないし、さして興味のないわたしのようなものでも、
住民だけに刷り込まれており、既にとある試合のチケットを入手しています。
来年は桜のジャージを着て、
どこかのスタジアムで声を張り上げていることでしょう。
さすが年季の入ったミーハーです、我ながら。
そしてどこだかはわからないですが、
「2020年の東京オリンピックまであと何日」というカウントダウンボードも
日本中のどこかにあるのでしょう。おそらく至るところにあるのでしょう。
思えば昭和の子どもたちを震え上がらせた
「1999年7の月に恐怖の大王が降ってくる」という
“ノストラダムスの大予言”の当時から、あらゆることに期限という名の、
ゴールやらスタートやらを設けて生きてきました。
「1999年にはもうおばさんになっているからきっと楽しいことなんてない。
だから世界が終わってもかまわない」、と思っていた愚かで残酷な子どもの頃。
あれから何年もたち、得体の知れない恐怖の大王は降ってはきませんでしたが、
世界中でさまざまな自然災害や人的災害があり、
わたしもおばさんになって久しく、まあそれでもそこそこの楽しいことと、
思いがけないしんどいことを繰り返しながら暮らしています。
そして先月このブログで「太陽の塔」について触れたら、
2025年の大阪万博の開催までもが決まってしまいました。
もはやわたしがブログで取り上げたから招致できた、
と言っても過言ではありませんが、
また2025年に向けて、新たなカウントダウンが始まりました。
昭和の、国を挙げての二大イベントの軌跡を繰り返すことが、
平成の次に来る世にふさわしいかどうかはさておき、
おそらく人生で2度、
大阪万博に参加できることは素直に喜ばしいことだとは思っています。
しかし7年後というのは、
この年齢になるとなかなか体調的にもリスクのありそうな期間です。
折しも、手元には平成最後の健康診断の結果が。
あちこち調子が悪くて、人生すらもカウントダウンが始まるのかと覚悟していたら、
持病以外には特に問題もなく、
ということは毎日の不調はただの加齢や劣化であるということ。
素直に健康を喜べばいいのに、ほんの少しがっかりしました。現金なものです。
時は師走。
平成最後の年越しのカウントダウンもやってくるし、
これから何度も平成最後という枕詞を耳にすることになるでしょう。
まあ、思えば生きていくということは、
あちらへ行くまでのカウントダウンに他なりません。
最後に、
ノストラダムスの大予言は当たらなかったようですが、わたしもひとつ予言を。
平成の次の元号の最初の文字は、
アルファベットの「N」からはじまると思います。
明治がM、大正がT、昭和がS、平成がH、
それらと被らないための消去法です。
平成という時代そのものもカウントダウンに入りました。
どうぞみなさま、よいお年を。よい平成を。
それにしてもなんですか、高輪ゲートウェイって。
-
太陽の日々
2020年の東京オリンピック開催まで、2年を切ってしまいました。
先日、代々木の新国立競技場のあたりを通ったら、
ちょっと前まで足場の鉄骨だらけだった外観も
その完成型がイメージできるくらいには仕上がっていて、
何だって出来上がっていくんだなあ、
そしていつかは終わっていくんだなあ、となぜか諸行無常の心境になりました。まだ、始まってもいないのに。
ついでに「どんな仕事だって、いつかは終わる。そこに納期がある限り」と、
ハードな業務に疲弊して、自分を鼓舞していた若い頃も思い出しました。なにかともめていた築地市場の豊洲移転も、ひとまずは着地したように、
2020年もやって来て、つつがなくオリンピックも終わるのでしょう。終わるといいと思います。
日本で最初のオリンピックが東京で開催された1964年のことは、
さすがに覚えてはいませんが、戦後の高度成長期だったこの時期の
国をあげてのもう一つの大きなイベントのことは記憶にあります。1970年の「日本万国博覧会」通称“大阪万博”へは
子どもの頃に家族で赴きました。広島に住んでいたわたしたち家族と東京にいた親戚家族が、
夏休みに大阪で合流して万博を観に行く、
というのは子ども心にも一大イベント。しかし会期中におよそ6500万人が訪れた
(当時の日本の人口は約1億人)というだけあって、
ひどく暑かったことと、ただただ大勢の人を目にしたこと、
妹とお揃いの胸に迷子札のついた黄色いワンピースを着て、
家族とはぐれないように必死で後を追って歩いたことだけが記憶にあり、
アメリカ館、ソ連館といったパビリオンのことは、
中に入ったかどうかも覚えていません。それでも、当時その前で撮影した家族写真が残っている、
岡本太郎作「太陽の塔」のことは忘れられません。そして今年2018年夏、その色あせたカラー写真の記憶は、
くっきりとデジタルリマスター化されました。この9月、わたしたち夫婦は48年ぶりに「太陽の塔」の真下に
立っていました。わたしより2歳年上の主人も当時、名古屋から万博に行っているクチです。
今年の3月から、太陽の塔は内部公開されていて、
その見学ツアーに参加したんです。高さ40mのその異形に近づいたのは、背後からでした。
過去を象徴するという「黒い太陽」にまず圧倒され、
“おー”“すごい”“でかい”“かっこいい”という、
語彙の乏しい感想が漏れるばかりでした。前に回っても“おー”“すごい”(以下同)。
金色に輝き未来を表す頭部の「黄金の顔」、
腹部にある現在を表現した「太陽の顔」、
3つの顔の周りをぐるぐる回って、
さまざまな角度から眺め、写真を何枚も撮りました。ほどなくして内部公開ツアーの予約時間に。
わたしは事前情報なしに参加したので、
内部の展示空間にある「生命の樹」のこともまったく知りませんでした。地上から黄金の顔の方に向かって伸びて行く樹や枝に
アメーバなどの原生生物から、爬虫類、恐竜、人類にいたるまでの
生物の模型が連なっている様は圧巻としか言いようがなく、
まさに芸術が爆発していました。岡本太郎、頭おかしい(賛辞です)。そしてあの左右にひろがった腕の中も空洞になっていて、
指先の方まで階段がしつらえてあり、
万博当時はそこを通って外の空中広場に出られたそうです。この造形を48年前に完成させた岡本太郎に敬服し、
また48年後に修復した関係者に敬意を表しました。実は何年か前に、太陽の塔を見て来たという知り合いに、
その魅力を熱く語られたことがあったんですが、その時は
「へーそうなんだ、おもしろそうだねー。子どもの頃に万博は行ったけどさー」、
と大したリアクションもできませんでした。すいませんでした。今なら、その人が口角泡を飛ばして語っていた、
語りたくなった気持ちが心からわかります。あの造形を目の当たりにしたら、何かに魅入られ、
ちょっと興奮状態になります。そしてその状態は意外と長く続きます。
今ならわたしも誰にでもその話をします。どうぞ聞きにきてください。
そしてわたし以上に魅入られた主人は、東京に帰ってからも、
公開中のドキュメンタリー映画「太陽の塔」を観に行き、
川崎にある「岡本太郎美術館」を訪れる計画を立てています。岡本太郎の生き方や太陽の塔の造形は、エネルギッシュで、
どこかプリミティブでもあり、
女性より男性をひきつけるような気がします。そう言えば、以前その魅力を熱く語ってくれた人も男性でした。
ネットで予約する内部公開がいつまで開催されているのかわかりませんが、
ぜひ行ってみてください。強くおすすめします。行くのなら太陽が沈む前、消費税が10%になる前がいいと思います。
Users who have LIKED this post:
-
証明の日々
「チケット注文 9割が自動プログラムから 買い占め転売狙いか」
猛暑や豪雨など相次ぐ自然災害に喘いでいた8月の終わりに、
こんなニュースを目にしました。
大手チケット販売サイトに、転売目的の買い占めと疑われる
botのアクセスが横行していることを取り上げたものです。
観劇クラスタであるわたしにとって、
チケット獲得のための先行予約サイトへのエントリーは
もはやライフワークです。
結果を知らせるメールを開くことは、
なにかの試験の合格発表を思わせる緊張感を伴い、
「残念ながらチケットをご用意することができませんでした」の1行に泣き、
「以下のチケットをご用意いたしました」の1行にまた涙するのです。
それがプラチナ、と評されるチケットであればあるほど、
喜びも悲しみも大きなものになります。
それだけに転売ヤーによる買い占めには憤りもありますが、
一方で、買う側のどんなにお金を出しても観たい舞台やライブがある、
というファン心理にも首がもげるほどうなずくことができます。
そんな背景もあってか、ライブ会場などで年々厳しくなるのが本人確認。
つい先日も、2024年以降に建て替えの決まった老舗ホール・中野サンプラザに
山下達郎のライブを観に出かけました。
その数日前からわたしのメールアドレスには
“絶対に顔写真付きの身分証明書を持ってこい。
もし忘れたらどんなにゴネても会場には入れてやらないからな。
わかったな。観られなくても文句言うなよ”
というような主旨のメールが何通か届いていました。
運転免許証を持っていないわたしの身分を証明してくれる
顔写真付きの証明書はパスポートしかありません。
何かの時に、と8年前に取得して以来、
なぜか1度も国際空港の出入国ゲートを通過したことのない赤いパスポートは、
もはやライブ会場の入場ゲートを通るためだけに存在しています。
65歳の後期高齢者になってしまった、と山下達郎本人がMCでも言っていましたが、
年齢も衰えも感じさせない3時間を超えるライブ。
歌声も演奏も素晴らしいもので、熱心なファンでもなかったわたしですが、
誰もが知っているヒット曲はもちろん、
たとえタイトルを知らなくてもあの頃街角に流れていた
耳なじみのある曲を生で聴いて、
当時着ていた自分のシャツの柄まで思い出すような時代の空気を
感じることができました。
終演後、立ち寄った店で、余韻をアルコールとともに反芻しながら、
“しかし今日はパスポートを持っている。
酔っぱらって失くしたりしたら大変だ”と、どこか冷静でもありました。
この7月には中国・四国地方を中心とした西日本を豪雨が襲い、
特に広島県の呉市、岡山県の倉敷市真備地区で被害が拡大。
その後も8月の猛暑を経て、
9月6日には大阪を中心に台風21号が猛威を振るい、
暴風に煽られたタンカーが橋げたに衝突したせいで
関西国際空港が陸の孤島と化し、何千人もの人たちが取り残されたままに
なりました。
さらにその救出もままならない9月6日の未明には、
北海道厚真町を震源に震度7の揺れを観測した北海道胆振東部地震が発生。
何を最初と数えればいいのかもわかりませんが、
まだ一つ目の傷も癒えていないのに、平成30年の夏、列島は傷だらけになりました。
被害に遭われた方には心からお見舞い申し上げます。
パスポートを持って呑気にライブを観に行ける幸せは失いたくないですが、
ここ何年かは、
いつどこで何が起こってもおかしくないと肝に銘じて生きています。
いつ誰が被災者になるかわかりません。
罹災証明書、という身分証明書を持つ日が自分にも来るかもしれない。
もうデフォルトとも言える、L字型に区切られたNHKのテレビ画面を見ながら、
粛々と暮らしています。
そして観劇クラスタと名乗っておきながら、
この度引退を発表したジャニーズ滝沢秀明の「滝沢歌舞伎」を
観に行かなかったことも後悔しています。
いつ誰が引退するかもわからないのです。
しかしわたしが言うのも何ですが、運営側にまわるという、
彼の選択は賢明だと思います。
組織というのは、できる30代が動かしていくものなのでしょう。
どこに行けるのかもわからないパスポートを眺めながら、
いろいろあった夏を惜しんでいます。
BGMは山下達郎の「さよなら夏の日」で。
Users who have LIKED this post: