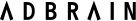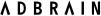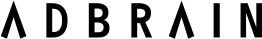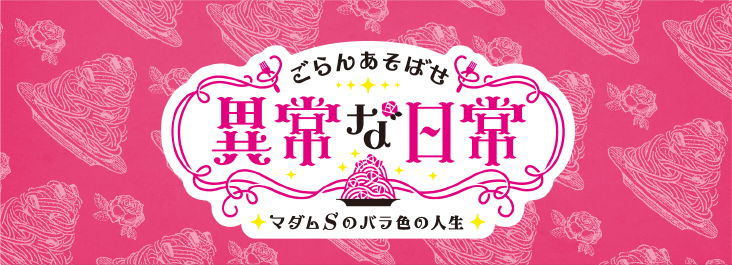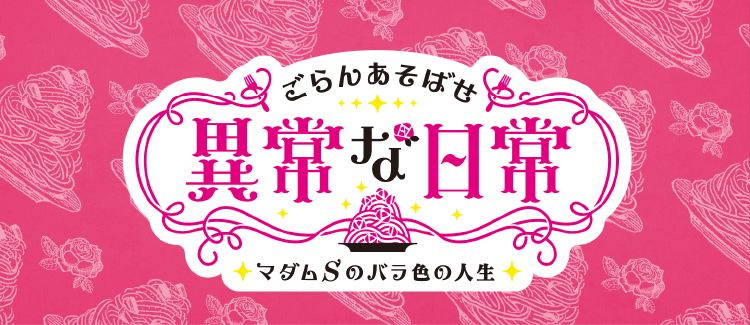-
グレートな回

『風に吹かれて』の歌詞を引用しても大丈夫なようです。
よかったです。
ボブディランの歌詞を読むと、苦しい気持ちになります。
平和でありたい、そう強く思う日々です。最近は、夏のような暑い日もありましたね。
会社に入る前のことですが、母とオーストラリアへ旅行に行きました。
グレートバリアリーフで泳ぎたい。
わたしではありません。母の希望です。
母はとても旅が好きなので、
国内外問わずわたしをよく連れて行ってくれました。幼い頃、
毎年夏はプールと言えばとしまえん、
海と言えば三浦海岸でした。
そんなわたしたち母娘が、グレートなバリアリーフに。グレートバリアリーフまでは、
ジェットコースターみたいに上下する中型の船に乗って向かいました。
途中、孫悟空が乗っていそうな(?)立派な亀と並走する瞬間があり、
激しい船酔いのなかで、
まわりの金髪の人たちが亀よ!亀だ!と嬉しそうだったのを覚えています。しばらくして、
ここがグレートバリアリーフです!という青々とした海の真ん中に船は到着。
どうやって泳ぐのかと思ったのですが、
船の横腹に20m四方くらいの囲いをつくり、
その中でレッツスイミング!ということになっていました。普段、三浦海岸でも浅瀬でしか泳いでこなかったわたしにとって、
底の見えない青緑色の海で浮かぶことはかなり勇気の要ることでした。
せっかく世界遺産に来たんだから!と
めっちゃ嬉しそうな母が先にどぼーんとグレートバリアリーフに入り、
ニコニコして手招きします。
バッドタイミングなことにわたしはお腹を壊しており、
息も絶え絶えでしたが、清水の舞台から飛び降りるつもりでどぼーん。グレートバリアリーフの海水温は、低かった。
水着とお腹の間を満たすひやっとした感覚に、
ハロウ?と英語で挨拶されたのにうまいこと返せない時のような、
なんだか気恥ずかしい気分でした。仕切りの綱には海藻類が茂り、
いかにも外国産という顔つきのフィッシュたちがパクパクつついていました。
グレートな晴天。素晴らしいグレートバリアリーフ日和です。
太陽さえも英語で話しかけてくるようなポジティブな輝きYEAR。平泳ぎで果敢に囲いの中を泳ぎ回る母を残し、
お腹の悲痛な訴えを聞いて海から上がったわたし。
正味10分程度で、世界遺産を後にしてしまいました。やはり顔色が悪かったのか、
絵に描いたような水兵さんルックのオーストラリア人男性が
「HEY、お嬢さん、HAHAHA、大丈夫かい?」
と話しかけてくれました。
あ、えっと、お腹いたいです、でもオーケーです…と弱々しい声で返すと、
「こっちで休んだらどうだい?」と、
甲板に置いてあるベンチに案内してくれました。
グレート優しい…ジェントルマンすぎるぜ水兵さんよ…。
お言葉に甘えてねそべっていました。海の中から、大丈夫〜?と心配そうに見守る母。
あ、お気になさらずです…と弱々しい微笑みを浮かべる娘。母はたっぷり泳いで、楽しんでいたようでした。
海外に出ても調子を崩すことのほとんどない母。
いつまでも、パワフルでグレートな母でいてほしいです。 -
背中を見る回
ようやく、暖かくなってきました。
嬉しいですね。
春は、なんとなく不思議な力を感じます。
知らないだれかにそっと背中を押されるような。
あ、怖い話ではないですよ。
いままで眠りについていた生き物たちが目を覚まして、
世界が活気づくからでしょうか。昔、母と旅行に行った時のことです。
日本で言う新幹線の「タリス(Thalys)」の一等車で、
ベルギーから、オランダへ向かいました。
母とわたし2人分の荷物がぎゅうぎゅうに詰まった重いスーツケースを
荷物棚に上げようとしたのですが、
引きずるならまだしも、女の手で上げられる重量ではなく途方にくれていました。
すると、オランダ人のまだ若い青年と母の目が合いました。
なんとなくの様子で困っていることが伝わったのか、
彼がひょいと、赤ん坊を宙に浮かせてあやすかのように
いとも簡単にスーツケースを棚に押し上げてくれました。
その手つきの鮮やかさから、
彼が力持ちであることはもとより、
見ず知らずの誰かを助けることが日常的なこととして伝わってきました。
年格好から判断するに20代そこそこのように見えましたが、
背の高いスレンダーな女性と一緒だったので恋人との旅なのでしょう。
お礼を言うと彼はどういたしまして、と言葉で返すかわりに
片手をサッとあげ、あとはペットボトルの水を飲んだり、恋人と話をしたりして、
こちらへ意識を向けてくることはありませんでした。
困っていたら助ける、お礼を言う、別れる。
その一連の流れは決められたルールのように滞りなく進み、
何事もなく終わっていきました。もちろん、一等車が割高な座席であることを考えれば、
そういう意味では持ち前の品の良さにくわえて、
他人を助ける余裕がある人が乗車しているということかもしれません。
オランダ人とおぼしき青年は背がとても高く、
わたしはその身長に圧倒されました。
オランダ人は世界のなかでも平均身長の高さが図抜けています。
彼はおそらく典型的なオランダ人男性だったと思いますが、
重いスーツケースを軽々と持ち上げて
なんでもないというふうに自分の日常へ戻っていく
彼の広い背中は、どこまでも広がるオランダの肥沃な国土のようでした。わたしは宝塚が好きなのですが、
ふだんは舞台上で観るだけの男役さんが地上に降り立つ瞬間があります。
「客席降り」と呼ばれる場面です。
宝塚ではお芝居とショー(レビュー)の二本立てを上演することが多いのですが、
ショーの一場面にその「客席降り」がある場合が多いです。
その名の通り「スターさんが客席に降りてくる」ことを指します。
もし通路側に座ったりすると、本当にすぐそばまで彼女たちが来てくれるんですね。わたしは最近、全国ツアーという宝塚の巡業公演のようなものを観に行き、
運良く通路側に座っておりました。
すると、ある男役さんがタキシードで客席に降りてきて、
わたしのほんの30センチ先を歩いてきたのです。
今までも、通路側でスターさんを間近で見たことはあったと思うのですが、
その時は、まるで初めて客席降りを目の当たりにしたかのようにドキドキしました。
スターさんの「背中」に、わたしはひどく動揺しました。
動揺というか、息を止めて見ていました。
自分が座っている、スターさんは立っている(しかも背が高い)という
状況なので、自然と見上げるかっこうになります。
黒々としたタキシードを着込んだその背中は
まるで男性のような骨格に見え、一瞬ドキっとします。
でも同時に、確かにその人が女性の骨の細さを持っていることも、
わかるのです。突然、その風格のある背中から、どうっと風が吹いてきました。
スターの風だ、とわたしは思いました(真面目に語っています)。
スタイルがいいだけ、姿勢がいいだけ、顔がいいだけ、有名人の娘であるだけ、
では、あのような風がそれも背中から吹いたりしません。
宝塚の男役というフィクションを何年も何年も研究し、
自分なりに磨いてきた酸いも甘いも噛み分けた背中だからこそ、
観ている人を闇に誘うような色気のある風を吹かすことができるのです。
「瀬戸かずや」という花組の男役です。
興味があれば、ぜひ調べてみてください。先日、噂の『ララランド』を観ました。
ライアン・ゴズリングの背中、いやもはやボディ全体が驚くべきイケメンさでしたね。
あんなに色っぽく黒シャツを着こなせるのは、
宝塚の男役とライアン・ゴズリングだけでは…?と思わせられました。
とても楽しかったです。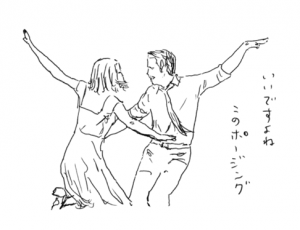
-
限りある回
「初物は三年長生き、って言うからね」
母親はよくそう言っていました。
時には真剣な表情で、時にはにんまりと笑って。一緒に買い物に行くと、
その時に必要な野菜やお肉や魚といったものとは別に、
決まって果物コーナーを見て、そのあと必ずお菓子コーナーも見ました。母親は、世の母親の例に漏れず甘いもの好き。
春は柏餅だ、秋には柿だマロンケーキだ、と
その時々に新発売されるお菓子を買うことが好きなので、
娘のわたしもその恩恵に預かってきました。
「旬のもの」は母親のなかでとても大切なカテゴリーであるらしく、
ともすれば野菜も魚もそれが優先されました。
旬のものは、たいてい売り場の目立つところに置かれていて、
だから輝いて見えたものです。大人になってから一人で買い物をするようになると、
自然と旬のものに目がいき、手に取るようになり、
「初物は三年長生き、って言うんだよ」
と、受け売りの言葉が口をついて出ました。
ふふふ、と一人で笑いがこみあげました。
確かに、旬のものはおいしいのです。
まず、色がいい。食べると、味がいい。
脂がノッているんですよね。
寿命に関しての真偽はわかりませんが、
イキのいい「旬」をいただいていると思うと、
体もなんだか元気になりそうな気がします。旬だ、ということにかこつけて、
ちょっと高いものでも買ってみる。
そういう生活のなかの習慣や態度は、
わたしは母親から受け継いだのだなぁと思います。自分で生活のための買い物をするようになると、
それこそ毎日野菜の値段が変わったり、
野菜の大きさが変わったりしていることにも気づき、
売り場を歩きながら、
先人たちはよくこれだけ「食べられる」ものを見つけたものだなぁ、
これを毒味して食べられるものに格上げしてくれた
昔の人は偉いなぁ、ありがたいなぁという気持ちになります。シーズナルなものは、商戦として使われることが常なので
それにおどらされているように思われますが、
1年中好きなものを食べられる今の世の中、
実際に自分の口に入るもので
移り変わっていく季節を感じることはむしろ健康的だと思うのです。春にたけのこ、夏にスイカ、秋にサンマ、冬にイチゴが食べたくなるように、
その季節になるとなんだか食べたくなるものは、
商業的な盛り上げの効果もあるかもしれませんが、
その季節こそ一番おいしく感じるものであり、理にかなっている。「味気ない」という言葉がありますよね。
面白くて趣のある日本語だなと思います。
味には、それにまつわる思い出があり、一緒に血肉となる。
味気ない人、にだけはなりたくないなと思います。
味のある顔だね、という言葉も、
立派な褒め言葉として心に留めておきたい今日この頃です。さて、小腹も空いたところですので、
コンビニで春限定スイーツを買ってくるとします。そういえば、キングもゴールを決めていました。
キングに限界などない….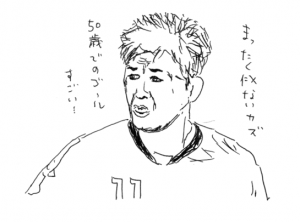
-
露天風呂の回
温泉が好き!という特集を眺めることも
秘境の宿、という特集を読むことも
特に好きではないわたしです。
「温泉いきた〜い」というだれかの他愛のない言葉に、
「いいね〜」と適当に答えるも、
特にいいとは思っていないわたしです。
この、温泉欲のなさ。また、リゾート地へ行ってぼうっとする、
というようなことにもあまり興味がわきません。
日常から離れてなにも考えずに波の音を聴く…
2時間もしたら飽きてスマホをいじってしまいそうです。でも、学生時代にはそれなりに「女子大生」らしく
温泉旅行へ行ったりしました。
なぜ大学生は温泉旅行に行くのだろう。
そんなに疲れてないだろうに。
あ、偏見でしたねすみません(笑)。高校時代の友人たちと、冬の青森へ旅行に行った時のことです。
だれかの旅の話は95%くらいは退屈だと思うので適当に読み流してください。確か、鈍行を乗り継いで行ったような気がします。
青函トンネルを電車で通り、鼓膜がぎゃんとしたのです。
何を目的に行ったのかというと、「海を目の前にのぞめる温泉」でした。
冬の青森はもちろん雪で、寒かったです。
ただ、「海を目の前にのぞめる露天風呂」だけのために、
電車揺られ、とあるホテルへ向かいました。露天風呂は、もちろん外にあります。
ホテルの建物を出ると道幅1メートルくらいの道が海へ向かって伸びており、
その行き止まりに木製の衝立が立っている場所がありました。
そう、そこがお目当ての露天風呂です。
男女混浴だった気がするのですが、
まあるい温泉の両側に着替え場所として、その衝立が用意されていました。
あまりにも貧相な衝立を前にして、びびるわたしと友人たち。
そこで裸になる勇気はさすがになかったので、わたしたちはホテル内で着替えました。
バスタオル姿で寒風吹きすさぶ道を小走りで走ります。
まるで昭和のコントのようにその温泉へまっしぐら。
残念なことにほとんど詳細は思い出せないのですが(笑)、
とにかく無事に「海を目の前にのぞめる露天風呂」に入ることができました。眼前に広がる海が日本海なのか太平洋なのか東シナ海なのかもわからないまま、
岩に打ち寄せる白波を友人たちと眺めました。
その波の荒々しいこと。
まるで「東映」のオープニング映像です。
お風呂の温度は高くて、10分もつかると頭がくらくらしました。
楽しかったです。
楽しそうにお風呂につかる写真が残されているので、そう思うことにします。冷たい雪が降るなか、
そんなに好きではない露天風呂のためにほぼ裸で走ったあの時。久しぶりに、あの頃の友人たちと行ってみたいです。
いつぞやも描いた(トレースした)気がしますが、
雪と言えば。
-
閉める回
タイトルは閉める回ですが、
あけましておめでとうございます。
コピーライターなのに筆無精なわたしに年賀状をくださった
心優しい皆様、ありがとうございました。
年賀状にかえて(かえるのかい)ここにお礼とご挨拶を申し上げます。コピーライターに何年ぶりでしょう。
新しい仲間が加わり、変化の多い年になるのかなと漠然と思っています。
古株のわたしもどうぞよろしくお願いいたします。さてさて、正月太りの話題はこの辺にして。
突然ですが、鍵っ子でした。
両親が共働きだったため、
小学生の頃に「家の鍵」を持たされたわけです。母から渡された自分だけの鍵は、ひんやりしていて、
銀色に光っていました。
母は、なくさないようにと、鍵をいれる小物を一緒にくれました。
ピカソを模したエンブレムが施された、人口革の青色のキーケース。
美術館のピカソ展とか、多分そんなことろで買ったものだったと思います。
デコボコしたキュビズムの革の輪郭は、
だんだん手になじんで丸くなっていきました。じゃりじゃりとかガチンガチンとか、
鍵とほかの金属の当たる音が好きではなかったので、
キーケースには鍵しかつけませんでした。
手のひらにちょうどおさまってしまうほどの大きさで、
いつも握りしめていたので、
今でもそのキーケースを触ると
自分が小さな子どもに戻ってしまったような気がします。両親の帰りを待つ時間は、楽しかったようで、
やっぱりどこか寂しさもありました。親たちが帰ってきてやっと、
自分が「家にいる」ことが実感できたのかもしれません。
不思議ですけれど、自分一人だけが家にいても、
家にいる感覚が希薄で、自分はどこにもいないようなおぼえろげな不安がありました。
家のほうも、ガヤガヤとした複雑な音を立てる、
どしりとした重量のある大人たちがそろってから
やっと「家」として重い腰を上げて、生き生きと動きだすように感じられました。父は、家の鍵をかけたか何回も扉を引っ張って確認するたちなので、
わたしも自然にそうなりました。
子どもは親を自然と真似るものなのですね。
あの、引っ張っても動かないし開かないという感覚で
ようやく「よしOK」と思うのです。
家のほうはいい迷惑だったと思います。昔、小学生の時だったか、
帰ったら家がなくなっていたという内容の本を読んで、
わたしは本当におそろしくなりました。
学校から帰ってきて、家のあるはずの場所に家がなかったら?「お父さんがいっぱい」という本でした。
タイトルにもあるように、
家に帰ったら同じお父さんが何人も何人も登場するという
身の毛もよだつような話がシュールに淡々と語られる本です。
興味があったらぜひ読んでみてください。
その本を読んだときは、真剣に悩みました。本は、恐ろしいものです。
だって「お父さんが無限に増えていっぱいになる可能性」を
わたしの頭に植え付けてしまったから。
「お父さんがいっぱいになる可能性があるんだ」と知った時、
目の前に広がっていた完全な世界にひびが入ってしまったのです。
わたしは、本だけが人生を変えることができると思っているのですが、
そのインパクトを最初に経験したのはこの時だったように思います。
為政者がこぞって焚書を行ったのも、
書かれた文字の影響力を知っていたからでしょう。
言葉は、恐ろしくて、それゆえにひどく魅力的です。本を読み終えた日、
家に帰ってお父さんが一人だけだったので、ほっと胸をなでおろしました。
よかった、と心から安心しました。でも、ピンポーンとチャイムが鳴って、
誰だろうと思って玄関に行ってみるとそこには……ね、読みたくなるでしょ?
寒い日が続きます。
家にそっと鍵をおろして、読書に没頭するのもいいものですよね。
今年はもっと本を読む年にしたいです。大晦日にPPAPを突然踊りだした母も相当面白かったですが、
年始のお笑い番組の中ではこのコンビが最高でした。