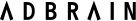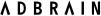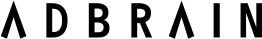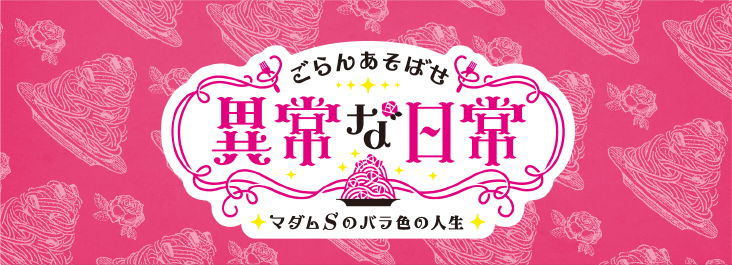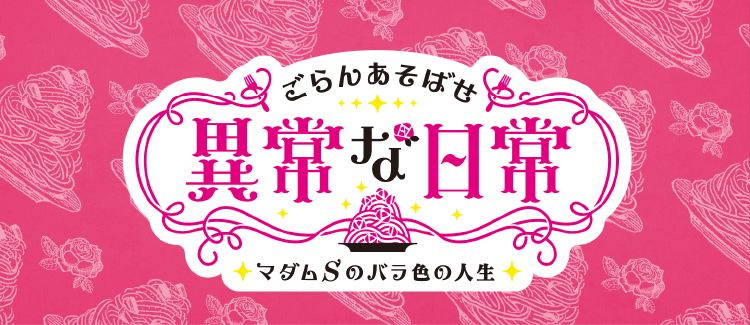-
「中島みゆきみたいな感じ?」
安室奈美恵引退の報を受けて、
弊社の1年目の子に安室奈美恵ってどんな存在?と聞いたら
「昔の人っぽい」という返答があり、
中島みゆきみたいな感じ?とさらに聞くと
「ああ〜!!」となにかを納得されたのはもう先月のこと。引退、卒業。
自分で引き際を決める、やめることを決める。
それこそ自由の権利を公使することであると誰かが言っていました。
安室ちゃんは自由を公使したのだな…と感傷的になる
コムロ世代のわたしなのでした。引退となれば「ラストの」という冠がつくものが多くなります。
ラストライブツアー、ラスト紅白、ラストドームライブ、ラスト武道館、
ラストアルバム、ラストソング…
そのすべてに居合わせたいと願うのがファンというもの。
すべての「ラスト贔屓」を見届けるために、
お金も時間も持てるものを注ぎ込むしかありません。わたしの好きな宝塚では長い人でもだいたい20年程で
みな卒業していきます。(例外もありますが)
歌舞伎だと、例えば中村勘三郎の若かりし頃を見ていた人が、
その息子中村勘九郎、中村七之助の初舞台を見て、
さらに中村勘九郎の息子たち哲之くん、七緒八くんの初舞台も見て、
しまいには哲之くん、七緒八くんの息子の初舞台を…と、
マトリョーシカのように続いていく歌舞伎の血の系譜、
40年とか50年とかある長大なその系譜を追っていく人もいるわけなので、
そうなると一生かかって見守っていくような、本当に息の長い話になります。ご贔屓がいれば尚のこと楽しいわけですが、
わたしは歌舞伎には特定のご贔屓はいません。
ただ、その世界そのものを好きになることが多いんですね。
宝塚も歌舞伎も文楽も、その世界にしかない独特の様式美を持ち、
それは伝統として脈々と受け継がれ、現在もいびつな美しさを保ちながら存在する。
そのためには専用劇場が必要なのでしょう。
歌舞伎座、宝塚大劇場、国立劇場…
そういう“ハコ”もまとめて好きになるとしたら、
ご贔屓がいなくとも月に1度は観に行くような
細く長い客になるでしょう。
ハコ推し、と言ってもいいでしょうか。世の中には、多くの種類のハコがあります。
球場というハコにそれほど興味がないのは
家族で野球観戦に行ったことがないからでしょうか。
わたしが実家にいた頃、父は巨人嫌いの巨人ファンでした。
その頃ピッチャーだった桑田の帽子のかぶり方が嫌いで、
いつも「あいつはなぜ帽子をまっすぐかぶらないんだ」と怒っていました。
だめだな巨人はと悪態をつきながら枝豆を食べたり、
勝ちました〜と嬉しそうに笑いながらビールを飲んでいました。
なのに、巨人ファンなの?と聞くとそうじゃない巨人は好きじゃない、と言うんです。
おとなのツンデレは面倒くさいです。わたしは、デパートのようなハコのほうが好きです。
いいものが置いてある、美味しいものが揃っている。
そういうワクワクがあるハレの場所。
GINZA SIXに何回か行きましたが、吹き抜けが素敵で、
どこか箱庭のようでもあって、夢のあるよい場所だなと思いました。以前、バルセロナに旅行をした際に
「カンプ・ノウ」というFCバルセロナのホームである
サッカースタジアムを見学したことがありますが、
サッカー信仰心のない母とわたしにとって
この聖地巡礼は完全に宝の持ち腐れでした。
空っぽのカンプ・ノウはそれはそれは広大なもので、
この空間が何万という人で埋め尽くされるのかと思うと
背筋がひゅっと寒くなる思いでした。
だいたいの人数を把握できる劇場のようなハコのほうが、
わたしはまだ気安く過ごせそうな気がします。安室ちゃんのラストコンサートは、プラチナチケットすぎて
定価で発売されたとしても、おそらく高値で取り引きされてしまうでしょう。
安室ちゃん、引退したらテレビには出てくれなさそうです。
山本リンダのように、
還暦を過ぎてもなお特番で往年のヒット曲を歌って
度肝を抜いてほしい気もするのですが…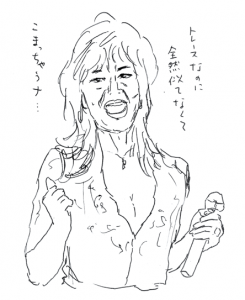
-
「これ、どこのお土産?」
「赤福」「とおりもん」「ままどおる」「もみじまんじゅう」
これはほんの一部ですが、
土地の銘菓をお土産にもらうとテンションが上がりますよね。
銘菓のあるなしで「地元のブランド力」も変わってきます。話題の桐生選手はどんなお土産を買ってくるのでしょうか。
もちろん日本人初の9秒台が最大にして最高のお土産ですが、
個人的にはダジャレのTシャツを買うようなタイプだと、
人として完璧じゃないところが逆に好感度が上がっていい気がします。
母は、小さいわたしをよく旅行に連れて行ってくれる人で、
旅先でお土産屋さんをのぞくのも好きな人でした。小学生の頃、男の子になりたかった(!)わたしは、
お城のある観光地へ行くと「十手」や「小刀」をお土産にしたがりました。
母からよしなさいと言われても聞かず駄々をこね続け、
とうとう手に入れた「十手」と「小刀」を肌身離さず持っていました。
「小刀」は金属製の鞘で重さもわりとあり、
中の刃はもちろんレプリカでしたがギラギラと光っていました。
武士が刀を構える姿がかっこいいと思っていて、よく真似していたのです。
「十手」を好になったのは、
水戸黄門や大岡越前が好きだったおじいちゃんと一緒に
夕方のテレビ放映をよく見ていたからだと思います。
「ズシュ」「ビシュ」などの奇声を発する娘に、
母は一抹の不安を覚えたに違いありません。あとよく、ちょうちんを買っていました。
「姫路城」とか「仙台」とかの観光名所や地名のちょうちん。
あれは、家の梁に取り付けられるようになっていて、
色もなかなかカラフルで目に楽しいのです。
ただ思い出としては少々自己主張が強く、
部屋で存在感を発揮してしまうため
ほどなく取り外され、捨てられてしまいました。大人になってから
スノードームをお土産にするカルチャーがあることを知りました。
「ザ・ダサいお土産」という認識しかなかったスノードーム。
なんとなく中身のクオリティも甘くて
ぼんやりしたおばさんのようなお土産だなと思っていたスノードーム。
そんなスノードームが、一部のおしゃれ人にとっては
インテリア雑貨的な価値を持っていることに驚いたものです。センスのないお土産をくれる人はセンスがないが、
センスがある人がくれるセンスのあるお土産のおしゃれさはたまに鼻につく。長文失礼しました。
センスってなんだよって話ですよね。
横文字使いやがってこんちくしょおプッと放屁したいくらいです。
うそです。スノードームをくれる人が
見た目から文句なくおしゃれで雑貨屋さんめぐりは特に趣味じゃないけど
インスタやってますインスタ映え〜みたいな人(どんな人)だったら
きっとどんなものも素敵なお土産に見えるのでしょう。
でも、なんの変哲もない風体の人からもらう
なんのひねりもない「草加せんべい」だっておいしいですよ!?
(おっと埼玉disはそこまでだ)父は、都市名の入ったTシャツが好きなので
ニューヨーク旅行の時に「買ってきてくれ」と頼まれたのです。
そうだお土産を買わねば!と焦って思い出したのはなんと帰国日の前夜。
冷たい雨の降る夜でした。
タイムズスクエアにひしめきあう多くのスーベニアショップは、
カタコトの日本語で話しかけてくる怪しげな人が多く、
わたしは「ディズカウントプリーズ」と繰り返しましたが
ノーノーイッツオーレディディスカウントの一点張りに根負けし値切れず言い値で購入。
New Yorkという文字とマンハッタンの街並みと自由の女神像
がプリントされた、実にちゃちな素材の長袖Tシャツ…。
ヨレヨレのタグにはcotton100と印字されていましたが
手触りはさほど良いとは思えませんでした。
そして帰国後。
Tシャツを無造作に着た父から真面目な顔で一言「Gut(良い)」と言われ、
そういえば父は変なものを面白がる人だった、とホッとしました。
そして、わたしは大事なことを思い出しました。
お土産は、喜んでくれたり面白がってくれる人によって、
その価値も変わるのだということを。
お土産そのものが持つ「みやげ価値」と、
もらった人が面白がることで付加される「おまけ価値」の2つによって
お土産の総価値は決まるのです。そう言えば今時期にピッタリなはずの長袖Tシャツですが、
実際着てくれているのを見たことがないので
今度父を問いつめたいと思います。 -
「制服は洗濯できない。」
◯◯の回というタイトルに飽きてきたので、
タイトルに規則性を設けずフリーダムにすることにしました。
どうです、アイドルグループのNEWシングルの曲名にピッタリじゃないですか。
秋元康さん、いかがでしょうか。
今でこそ洗濯機や乾燥機は高性能なので
家でも制服を洗濯することもできるかもしれませんし
あるいはファブリーズで除菌することもできるそんな時代ですが、
わたしが制服を着ていた頃家にあったのは、
まだまだ昭和の香り漂うあせた色の乾燥機でした。
ゆえに制服はクリーニングに出すしかなかったのですね。みなさんは、『あぶない刑事』(1986年)というテレビドラマをご存知でしょうか。
わたしは子どもの頃、再放送かなにかを見ていました。
刑事というあぶない職業の人たちが着る服を、
柴田恭兵と舘ひろしによって「スーツ」と認識していましたが、
織田裕二によってそれが 「カーキ色のトレンチコート」へ変わった瞬間がありました。
『踊る大捜査線』(1997年)ですね。
刑事が着る服はなんでもいいんだな、というのが印象に残りました。
街にいる制服姿の警察官よりなんだか自由で、
ゆえに「テレビドラマ的展開」がありそうな私服の彼ら。
『沙粧妙子 最後の事件』(1995年)では服装よりなにより、
薬の副作用で意識が酩酊する浅野温子のうめき声のほうが印象的でした。
この意識酩酊系シリアス刑事ドラマは
後の『ケイゾク』(1999年)等に引き継がれていくのだと思いますが、
もはや刑事はどんな格好でも刑事、というよりむしろ、
“外側”の刑事らしさや硬派さ(あるいは異端としての軟派さ)はなりをひそめ、
刑事の入り組んだ人間関係や人生体験そのものに
ショッキングで刺激の強い事件性が含まれているドラマが流行りました。
今また刑事=「スーツ」に戻ったのはおそらく
『相棒』(2000年。2002年から連続ドラマ化)の水谷豊のせいでしょう。成長に従って刑事ものドラマにだんだん飽きていたわたしの前に、
『きらきらひかる』(1998年)というドラマが突如現れました。
遺体を検案し、その死因の真相を究明する女性監察医の物語です。
このドラマがとても好きでした。
主なキャストである深津絵里、鈴木京香、小林聡美、松雪泰子の四人は、
ふだんは監察医として白衣を着ていました。
(あ、松雪泰子だけは刑事なのでスーツでしたが。)
これがものすごく新鮮だったんですね。いわゆる“スタイリッシュ”だったのです。
刑事ものの変化形とも言える本作では、
物語の中心にいて事件を解決するのは常に女性でした。
ドラマの最後に必ずレストランで食事をとるシーンがあり、
わたしは羨望をもってこのシーンを見ていました。
オトナになったら仕事終わりに気の置けない友人たちと
おしゃれなレストランで仕事の話をしながらディナーをする、
そんなおしゃれな未来がどこかに待っているのだと。
その時、自分はキャラクター的には深津絵里なのだろうか、
それとも小林聡美なのだろうかと、考えなくてもいいことを考えていました。
大学生になり某書店でアルバイトをしていた時、
古くて狭くて暗いロッカーで私服から規定の白シャツに着替えていましたが、
バイトの後おしゃれなレストランでディナーすることは一回もありませんでした。スティーブン・スピルバーグは、毎日同じ色のシャツを着ていたそうです。
スピルバーグ監督がそうするなら
服を選ぶ労力や時間をほかのクリエイティブに変えたいからとかなんとか、
生産的な意図もありそうだなと思えますが、常人にはとても真似できそうにないです。わたし自身は、スーツや白衣といった制服を着る職業には就かなかったわけですが、
母親は仕事用の揃いのスーツを何着も持っていたので、
その柔らかな肩パッドの入ったスーツを着て「ON」スイッチを入れる姿が
子ども心にまぶしく、かっこよかった記憶があります。
となると、わたしは常にスイッチ「OFF」だと思われる気もしますが、
いやいや、人は見かけによらずとはこのこと。
今日もそこらへんにあったTシャツを着ていても、
瞬時に「ON/OFF」を切り替えているのです。
なんせ、制服と違ってTシャツは洗濯できます。
暑いですからね。世界陸上もアツいです。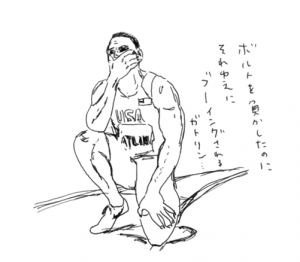
-
従兄の回
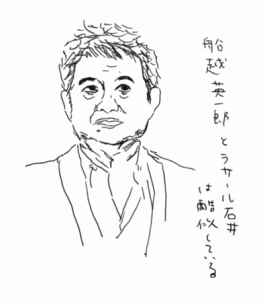
毎日、暑いですね。
男兄弟もいないのに、小さい頃は少年マンガをよく読んでいました。
ドラゴンボールもスラムダンクも連載していた「ジャンプ」を、
この続きがどうなるのかワクワクしながら発売日を待っていました。
今のようにSNSなんてなかった時代です。
だれともシェアしませんでした。
わたしにはネタバレという概念自体がありませんでした。
雑誌のコマを撮って画像を貼り
うまいことを言って大喜利をすることもなかったし、
二次創作も知りませんでした。
近くの駄菓子屋さんに置いてあったジャンプは、
200円未満で買える別の世界への入り口だったのです。わたしの中で「ジャンプ」は従兄の思い出とセットです。
近所に住んでいた従兄に170円を持たされてジャンプを買いに行かされました。
いわゆるパシリですが、まぁわたしも読みたかったのでよしとします。
でも、その週は170円ではなく190円のちょっと高い増刊号だったんです。
当然買えなくてわたしは従兄の家に戻りました。
すると、従兄が「170円で買ってこい」と。
従兄、横暴すぎやしませんか。従兄は、不良を自称する背の低い男の子でした。
「オレが卒業してから◯◯(学校名)から不良はいなくなったな」
と、よく言っていました。夏休みになると日中従兄の家に預けられたせいもあって、
従兄はわたしを手下にしようと、あれこれ命令をしてきます。
長渕剛が好きだった従兄は、ビデオを居間で流して、
「一緒に歌え」と強要。とんだ不良です。
わたしはその武道館コンサートだか、ドームコンサートだかの
長渕剛の映像を見ながら、見よう見まねで歌ってみました。
従兄は映像の中の長渕剛の熱唱に涙ぐんでいました。
わたしの歌、要る?従兄が遊んでいたファミコンを、わたしもやらせてもらっていました。
今でもふとやりたいな、と思うのは、
その当時遊んだ記憶のあるソフトなんですよね。
「さんまの名探偵」は面白かったです。
従兄は、その当時の男の子が憧れたものを追いかける人で、
ボクシンググローブをしてシュッシュってやっていたり、
背の低さを活かして騎手になろうとして
「ダービースタリオン」という競馬ゲームをやりこんだり、
長渕剛を愛していたり、
F1レースが好きでF1のゲームをしたり、
ポマード(当時の整髪料のことですね)を撫でつけていたり、
とにかく、彼のなかで「イカしている」ものを
手当たり次第触っておくという感じでした。結局、ボクサーにも、騎手にも、F1レーサーにも、
彼はならずに、地元の企業に就職したと聞きました。
不良だった従兄も今は家庭を築き、いっぱしの大人になったのです。
いつかの法事で見かけたことがありますが、
小さな背中を丸めたいい年のおじさんになっていました。
その時の、かどが取れて人生に疲れた顔で煙草を吸う従兄が、
まだ、あの、長渕剛に涙していた夏休みの時間の中にいるような気がして、
不思議な気持ちになりました。従兄の思い出は、なんだか煙草の煙みたいにけむたくて、めんどうで、嫌です。
だから、今更会いたい気持ちは全然ありません。
長渕剛を歌いながら元気に生きていてほしいなと思います。
わたし、いい従姉妹ですよね。 -
「回る回」
千葉にある夢の国にはもう何年も行っていないけれど
乗り物のなかではメリーゴーランドが好きです。
でも、コーヒーカップはべつに好きではない。
回るならなんでもいいのかというとそうでもないんですね。観覧車も、好きです。
どこか楽天的でさえあるあの遅さでゆっくり回るのがいい。
メリーゴーランドは、ちょっと腰高の馬に乗れるのがいい。
馬が単純に上下するだけ、それが楽しいのです。「回転木馬」というバレエを観に行ったことがあります。
ドイツのハンブルグ・バレエ団が来日した時にかかった演目の一つでした。
「白鳥の湖」などに代表されるクラシックバレエと違い、
映画が原作という本作は、演劇性が高く、濃密な人間のドラマが展開されます。
それは夫婦の問題であり、親子の問題であり、
労働の問題であり、貧困の問題であり、
人間が抱える悲しみをめぐる美しくてドラマチックな物語でした。人が集う遊園地に昼の顔と夜の顔があることを知ったのは、
思春期だったと思います。
そう、由貴香織里の描いた『残酷な童話たち』というマンガでした。
昼間、家族や恋人たちの笑顔があふれる場所だからこそ、
人気のなくなった夜に漂う気配はどこか暗く、不吉でさえある。
ピエロの泣き顔とも笑顔ともつかない独特な表情は、
おとぎ話の中に監禁された、手足の自由のない子どもだからかもしれない。
遊園地という場所は、表にけっして出てこない
「裏」側への興味をそそられた最初の場所だった気がします。カーニバルや祝祭という空間の二面性を強く意識したのは、
寺山修司のことを知ってからでした。
彼の創る世界は、大学生だったわたしに、野蛮で、血の匂いがあふれ、
淫らで、エロティックな「裏側」=アングラこそが
世界の真実であると強烈に印象づけました。
いつからか、わたしにとって遊園地はただ純粋に遊ぶための場所ではなく、
裏側を覗き込むような場所へと変わってしまっていました。『エスケイプ・フロム・トゥモロー』という映画を観に行った時は、
かなり後悔しました。
夢の国を侮辱してけしからん!とかそういうことではなくて、
単純に映像や内容が怖かったので、
やっぱりホラー映画なんて見るもんじゃないと思ったのです。めっきり遊園地に出向かなくなったわたしが
唯一足繁く通う場所は、劇場になりました。
よく、どうして何度も同じ舞台を見るのか、と不思議そうに聞かれます。わたしはある時から、
「遊園地に何回も行く人と一緒だよ」と答えるようになりました。
3時間もの間動かない座席に座り続け、表舞台をただ見るだけなのに?
いえいえ、舞台は一回として同じ舞台はありません。
毎回新しい仕掛けが出てくるアトラクションに乗るようなもの。
上級者ともなると隠れキャラクターを探したり、
一見華やかそうに見えるその舞台裏を想像して、
永遠に楽しむことができるのです。最近では、座席が360度回転する劇場も出現しました。
となると、
作り物の固い席にまたがり、回りながら宝塚を見る、
そんなメリーゴーランド・タカラヅカシアターが誕生する可能性も、
よもや夢ではないかもしれません。
それまでは、走馬灯を見ないように長生きしたいものですね。野際陽子さんがお亡くなりになったと知り、
「ずっとあなたが好きだった」を見返してみたくなりました。
ご冥福をお祈りいたします。