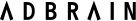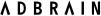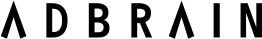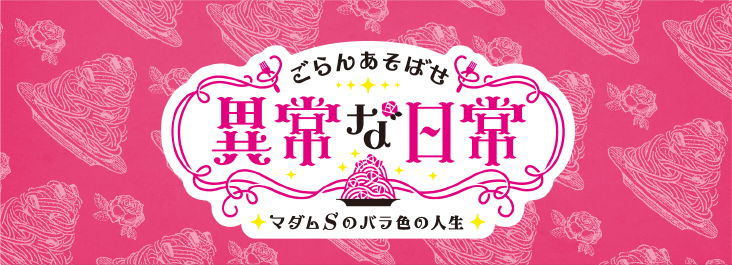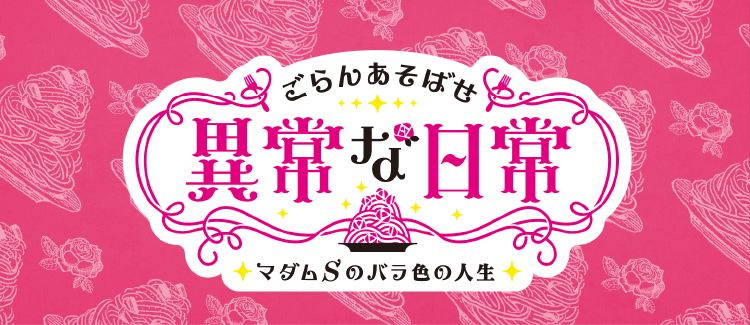-
アイドルというビューティー 秋葉原の回①
個人的に長かったGW。
みなさんどうしてましたか。
わたしは連休が長すぎて若干持て余してました!
天気もよくて、遊んでばかりいたね~。世の中の流れが速くて、
小雪が結婚したこととかもはや去年のような気が・・・
つい何週間か前のことですよね。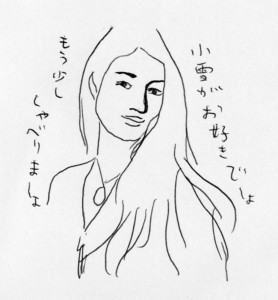
さて、GW中に、はじめて秋葉原に行ったので
そのことを今回は2~3回にわけて紹介します。なんで秋葉原?
というのは、知人のつてであるアイドルのライブを観られることになったんです。そのアイドルとは―「SDN48」。
AKB48のお姉さん的存在、という位置づけのアイドルグループですが、
・・・わりとみんな年下だよね!AKB48ってどんだけ若いんですか!
例えば・・・
あっちゃんこと前田敦子は19歳。1991年7月10日生まれ
ゆうここと大島優子は22歳。1988年10月17日生まれ20代前半だね!
一方、SDN48の人気ナンバー1は、野呂さんという子です。
ノンティーこと野呂佳代は27歳。1983年10月28日生まれわたしと同年代です。
AKBを生で見たことはないんですが、
SDNの人たちはもうみんな若くって元気でね~。
キラキラしてました。男性目線はどうなんでしょう。
「キョンキョン」や「聖子ちゃん」のように
いつまでも、半永久的に「アイドル」として認められている場合、
年がいくつになっても「アイドル」なんですよね?
だから、サユリストにしたら、吉永小百合だって現役「アイドル」ですよね?でも残念ながら、
「おれの青春はキョンキョン一色だったよ」とか、
「聖子ちゃんのことしか考えられなくて受験に失敗したよ・・・」とか、
「さゆり・・・いつまでも変わらなねえな、あんたも」とか、
自らのアイドル遍歴を熱く語ってくれる人があまりいなのですが、
本当にみんな好きだったんですよね?
今度ぜひ、みなさんの青春を支配したアイドルについて聞いてみたいです!松田聖子は、気がついたときにはわたしにとって
「ママなのに娘と同じくらいに見える謎な人」だったりしたので、
わたしのアイドル遍歴はかなり浅めです。あと、やっぱりモー娘。がね、わたしにとってはアイドルなんだよね~。
個人として把握できるのはゴマキの時期くらいまでですが・・・。
ミキティが入った頃にはなんとなく興味が薄れていった感じ。
でも好きだったなぁ。
「日本の未来はウォウウォウウォウウォウ世界がうらやむイェイイェイイェイェイ」
カラオケでものすごく歌った記憶が。関係ないですが、この間病院に行ったら、主治医の先生に
「まあ、若いっちゃ若いからね」
と言われ、複雑な気持ちにさせられました。「若い」と断定される年ではすでになくなっている!
過ぎ去った年月の重みを感じます。そうそう、ライブの話でした。
秋葉原の駅前では、オタ芸を汗だくで練習するグループに遭遇。
幸先よいスタートです。
秋葉原のドンキの9階にある「AKB48劇場」。
そこで、夜8時からSDN48のライブがありました。
GWまっただ中の祝日。
「SDN」のライブは、年齢制限があり、18歳未満は見られません。
受付で身分証明証の提示を求められます。
受付を済ませて整理番号付きの入場券をもらい、狭い廊下をすすんでいきます。
この狭い廊下には、メンバーの顔写真があったり、
なぜか「たっちゅ 2007.4.15」のように書かれた金属プレートが貼られた壁が。
100回通った人だけがそこに貼ることのできる金属のプレートだそう。
ここに自分のハンドルネームが刻まれることは、ファンにとって最大の勲章です。
友達の名前を見つけて興奮している男性ファンもいて、ファン同士の熱い戦いもありそうです。
廊下をすすむと、小さなロビーがあります。
手荷物は持ち込み禁止。ロッカーに荷物を入れ、手ぶらでないとだめです。
さて、開場時間が近づくにつれ、
ロビーは彩度低めの服でキメた、垢抜けない感じの素朴な男子たちで埋め尽くされます。
ファンの年齢層はやや高め。男性が9割。1割が女性とカップルです。
男性ファンの中でも、グループで来ている人はわりと大学生~20代後半くらい。
独りで寡黙にスタートを待つ人の方が、オタク度は高そう。
純粋な男子が大勢集まって発散される特殊な熱気と興奮で、劇場ロビーはただならぬ空気に・・・。「わーすげえラッキー」と、知人がサイリウムをわたしにくれました。
サイリウムって、コンサートとかで振る、あのペンライトですね。
なにやら小さな紙が・・・?
{ 小原春香生誕祭2011★企画について } と題された紙。
今日は、メンバーの春ちゃんこと小原春香さんの23歳を祝う生誕祭だとか。
生誕祭委員と称するファンが独自に企画し、劇場の許可をもらって行うイベントです。
その紙には、4ポイントくらいのちっちゃな文字で、
2色のサイリウムを使う曲、アンコールの掛け声は「春ちゃん」で、など細かく指示されています。
企画番号が①②ではなく、⑪⑫だったことの意味がわかりません。
でも文面はいたって丁寧。
「至らぬ点が多々あるとは思いますが」「ぜひご協力お願い致します」など
生誕祭委員はとても腰が低くて謙虚です。そして、いよいよ開場!
・・・ですが、入場は整理番号ではなく、なんと抽選順。
1グループ整理番号で25人ずつくらいにわけられ、
抽選で、入場できる順番が決められます。
劇場内は自由席なので、早く入れたもん勝ち。
これ、かなりドキドキします!
知人は、「今日は早めに(順番が)来る気がする」と、いささか興奮気味。
そんなにうまくいくのかなと半信半疑でしたが、
なんと3巡目に呼ばれたんです!ひゃっほう!
びっくりしたね!!!
すぐ中に入ることができたので、3列目のほぼセンターの「1ずれ」に座れました。
知人はドセンターの「0ずれ」。メンバーから見て真正面の位置らしい。
最高にいい席!に座っただけでファンから怒号が・・・なんてことはないです。安心してください。席に座ったら、基本的にライブ中もずっとそのまま。
ただ、知人から「ケガをした人もいる」と聞かされていたので
どんな激しいオタ芸でケガを・・・?と、気が気じゃなかったです。でも、さずがに座りながらオタ芸をやらかすファンはいなくて、
着席した人はみんなSDNのフリをするくらい。わたしの席から見える最前列には「コピリスト(名称うろ覚えです)」というファンがいて、
その男性ファンは「フリを完コピ」しているそう。
たしかに、舞台上のSDNメンバーと見比べても一糸乱れぬフリ。キメるタイミングも完璧。
その他のファンを圧倒していた気がします。
わたしも、そのコピリストにならって、フリをまねしてみました。
うん、なんか盛り上がる!!!今回のライブは「魅惑のガーター」公演らしく、
露出度の高い衣装でみんな踊って歌ってたいへんな感じでした!!
SDNは「18禁」を売りにしていることもあり、全体的にセクシーでエロいよね!!
アイドルってすごい・・・
やっぱりアイドルは男性ファンに向けて演出されているものなので、
男子目線だとツボがよくわかります。
目線もすごくとんでくるし、みんなお客さんを煽る煽る。思い出深いのは、
魅惑的な「ガーター姿」で踊っていた加藤さんという子が、
そのガーターをはずして、クルクルまわして「ほしい~?」みたいにファンを煽る時があって、
その時ちょうどセンターに加藤さんが来てたんですね、
前列の若者が、ものすっごい手を伸ばしてたんですね。
で、加藤さんがポーイっと投げた「ガーター」は、やった!嬉しがるその若者の手に・・・
いかず、わたしの隣に座っていた「0ずれ」の知人の手にすっぽりおさまりました。
さすが「0」ずれ!加藤さんの生ガーター・・・笑。
爆笑問題の田中が、
サザンのライブだか、俊ちゃんのライブだか、秀樹のライブだか、
とにかくだれかのライブで、その人がふりまく汗を口をあけてのんで
「おれ汗のんだぜ」とみんなで自慢しあっていたというエピソードをテレビで話してましたが、
ファンにとっては汗さえね、嬉しいんですね!AKB劇場は本当にこじんまりした劇場で、メンバーとの距離がものすごく近い。
最前列だともう手を伸ばしたら触れられるくらい近いところで、メンバーが踊ってます。
さすがにそんなマナー違反をするファンはいませんでした。ファンを規制するのはやっぱりファン。
「DD」と呼ばれるファンは、「誰でも大好き」な奴だということで、
発言権もなく、メンバーからも「あいつDDだから」と冷たくされるとか。せっかく毎公演足を運んでも「DD」呼ばわりされてはファンとしては浮かばれないね・・・。
逆に「推しメン(推してるメンバー)」を決めると楽しめる、ということだったので、
わたしも今回初めて行ったライブで「この人は!」と思った「推しメン」を紹介します。まず、「なちゅ」です。
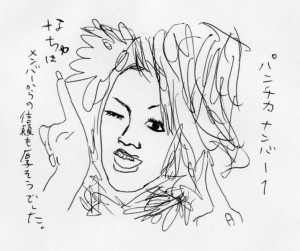
元は渋谷でギャルの総長をやっていたという経歴の持ち主だけあって、
トークの仕切りがハンパなくうまいです。
お客さんにフリを教えるときも、なちゅ型ロボットがしゃべっているのかと思うくらい
よどみなく、ギャルメイクでオーラがすごかったです。つぎに、「れいちぇる」。
この人は33歳で、舞台上にはじめて現れたときは、
他のメンバーとのギャップで見ているほうがドキドキしました。
ちょうどその週の日曜日が母の日だったので、母の日の話題になると
「〇〇からはプレゼントもらったけど、△△からはもらってない」など
年上ということをいいことに、みんなからプレゼントをもらおうと欲張る場面も。
メンバーからは「お母さん」と呼ばれ、若干仕返しをされている感も否めませんでしたが・・・。さいごに、「ふじこ」。
ライブの中盤にトークがあるのですが、この「ふじこ」と、「れいちぇる」だったんです。
もちろん司会は「なちゅ」。
この子はけっこう新人みたいで、マイク慣れしていなくて、
音が割れるくらい異様に大きい声を出していました。
中学生かも・・・と思いましたが、
1989年生まれの21歳ってことで普通に成人されてました。
自己紹介のときのファンからの声援も大きく、将来が期待されてそうです。と、まあ、このように、メンバーの区別がついてくると、ライブももっと楽しい、と。
長くなりましたが、来週どこかでまた更新するんで!
えーと、「小原春香生誕祭2011★企画」のことと、「愛、チュセヨ」のことと、
全体の感想を少しだけ。あじゃぱー!
-
自粛しないビューティー 3月11日の回
はじめに。
今回の震災で被災されたすべての方に、
心よりお見舞い申し上げます。
そして、今回の原発事故で被害を受けたすべての方に、
心よりお見舞い申し上げます。一日も早く、一人でも多くの方が、
大切な人と一緒にふたたび生活を、人生を生きていけますように。
ここで、祈り、願っています。最近、
「ホロコーストの後、すべての文章は野蛮である」
そんな言葉を思い出してました。
でも記憶があやふやで、間違っていました。「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」
正しくはこうでした。アドルノという社会学者の言葉です。アウシュヴィッツと今回の地震はまったく違うけれど、
わたしは、いま、こうしてブログを書くということが
ある意味で「野蛮」なことかもしれないという気がしています。
でも、わたしはあの日を東京で体験した人間として、
今月は、震災のことを、たくさん書きます。大震災のあと、ACのCMだけが流れていた時間。
はじめての体験でした。どこにチャンネルあわせても「AC~」。
ああ、いま、非常時なんだと、強く思う。
あの時の精神状態を振り返ると、
日常という空間から少しだけ切り離されてしまったような、
まわりの空気とうまくなじめない、ふわふわした自分を感じていました。
テレビから伝えられる現実に、心もあたまもまるで追いつかない。あれから1か月が経ち、わたしは「いつも」に戻りつつあります。
いや、以前と違う「いつも」をはじめている、というほうが正しい。
もう、地震の前には戻れないのだから。
それでも、「ポポポポーン!」というフレーズを口ずさんだりしてます。
夜9時前なのに、ひっそり静まりかえった暗い街。
一日中、電気が消されて薄暗い駅の構内。いろいろ、思いました。
地震後に見た最初の舞台、宝塚。
やっぱり電気、使いまくってる!!!でもね、
東京電力管内でおこなわれる舞台をすべてやめたら
水の買い占めもなくなって、原発の問題も解決して、避難所の暮らしがよくなって、
ちっちゃな子がいるお母さんの心配が消えるの?
わたしは、そうは思わない。わかります、舞台は日常生活の延長じゃないし、
いまはその日常生活さえ壊されてるってことはわかります。でも、たとえば、被災地で卒業式をやるって、野球部がセンバツに出るって、
すごく大事なことだったと思うんです。
わたしたちは、生活をする、だけじゃなくて
豊かに生きる、ってことも全然していくべきで。
むしろ、こんな状況だからこそ、人生をとことん豊かにするべきなんです。できない人がいるから、自分もやらない方がいい?
それは、正しいようで、違和感がある。イビツな感じがする。
わたしたちが同じような苦難を同じように味わっても、
被災された方の気持ちが、救われるわけじゃない。深く、静かに哀悼の念を抱きながら、自分のいる場所で、
自分の日常をよりよく、より豊かに生きるべきだと思います。ニュージーランドの大地震のとき、
避難所に、ケーキが届けられたってニュースを聞いた。
わたしは家族で、「ニュージーランドすげえ!」と感心したんです。ケーキは、水や毛布みたいに緊急に必要とされる物資ではないでしょう。
でも、ケーキ、なんだか、うれしくないですか?
ケーキが届いたら、いまの状況が、少しだけ前にすすんだ気がしません?
ふっと力が抜けて、ほっとして、気分がハッピーになって、明るくなって。
それって、生きていてもいいかなって思えるってことです。
この時届いた甘くておいしい「ケーキ」は、希望だと思うんです。
背中を押してくれるあったかいなにかが、必要なんです。
ほんとうの意味での豊かさって、こういうことじゃん!!!だから、
過剰に強制される「いまそんな状況じゃない」的な自粛ムード?
それが嫌なんです。自粛とか性格的にムリなんです。わたしは舞台が好きで、あの非日常感がたまらなく好きで、
いつまでも、生きている限りずっと観たいと思ってる。
たしかに被災した方や、被害にあった方にとってみれば、
「被災」や「被害」がとんでもない非日常なわけで、
舞台という「虚構」が、この凄まじい「現実」を覆せるわけじゃない。
舞台を見ても、失ったものが元に戻るわけじゃない。つまり、電気をくうだけで、なにも助けにはならないじゃないか。
やめてしまえ。中止だ。自粛しろ。って、声高に、とくに偉い人が、ここぞとばかりに言いそう。
でも、わたしは断固、舞台を支持します!わたし自身が、心の底から楽しみたいから。
日常を、よりすばらしいものにしたいから。
宝塚をみて、3時間とても幸せな気分になったよ。わたしに言えることは、これだけ。

・・・影響されやすいんで、わたし。
日本一あきらめない女、真矢みき。
彼女を見ているとなぜか力が湧く、そんなあなたにささげます。

トレースしても似てないってどういうことですか。
でも、あきらめないでやってみました。
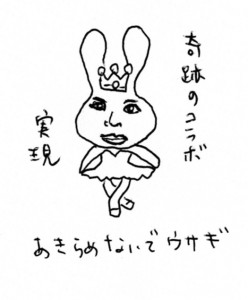
最後に、
いまも悲しみと苦しみを抱えて過ごされているすべての方に、
少しでも早く、穏やかで、やさしい時間がおとずれますように。
ここで、祈り、願っています。 -
本場というビューティー 名画の回
シュルレアリスム展―パリ、ポンピドゥセンター所蔵作品による― (国立新美術館)
レンブラント 光の探求/闇の誘惑 (国立西洋美術館)
シュテーデル美術館所蔵フェルメール 《地理学者》とオランダ・フランドル絵画展 (Bunkamuraザ・ミュージアム)・・・とまあ、行きたい展覧会はやまほどあるわけですがね。
ちょっと前にゴッホ展やってたときも
っていうかゴッホ展っていつもやってる!?
ゴッホ展が来るたびに「またゴッホかい」と思わなくもないです。
好きだけどさ、ゴッホ!わたし、見たときに脳天かち割られるくらい衝撃的だった絵、
足がすくんだ絵っていうのがありまして。
いくつか、あるんですけど。まず、レンブラントの『夜警』。
アムステルダムの国立美術館で見たんです。
びっっっっくりした。度肝ぬかれた。
その巨大さに。
美術の資料集や画像で見ても、実際の大きさってなかなか想像できない。『夜警』が置かれている部屋は、
『夜警』と、『織物商組合の幹部たち』という2作品しか飾ってないんです。ほかの部屋とちがって真っ黒でスタイリッシュな空間に、
レンブラントのあの何とも言えない浮遊感のある2作品が、対面にかけられている。
はぁーーーーーーーー(ため息)。
なぜ、あんなに迫力があるのにあんなに繊細でいられるの?レンブラントはよく「光と闇を自在に操る」って言われます。
でも、光がどうの闇がどうのなんて講釈は、もはや無意味。『夜警』を見上げる。
絵のなかの静寂に引き込まれる。
時間が止まる感覚。
部屋に誰も感じない。そう思った瞬間、ざわついた喧騒へ戻される。
人がいる。現実にハッとする。
引き込まれそうなのに、そうさせてくれない。『夜警』は、画面を構成している登場人物とかは
決して派手ではないし、構図自体もどこか
「はいはいレンブラントねそうだよね光と影のアレね」と
もうその手は知ってますよと、うがった見方をしてしまいがちだけれど。でも、『夜警』の前に立つということは、とんでもなく強烈な体験なんです。
寒気がする。それくらい感動する。
浅い予備知識が、気持ちいいくらいあっさり吹き飛ばされる。
たまんないです、あの感じ。
過去にこんな絵を描いた人がいたんだ、そのことに単純に驚くし、
レンブラントが、完成した『夜警』をこうして眺めたように
わたしもその前に立っているんだ、と思うと、足がガクガクする。大きな絵は、大きいってだけですごくいいなぁ。
涙腺が崩壊寸前だぜ。ちっくしょうレンブラントのやつ!
すばらしい絵を残してくれやがった!
ありがとうございます!ありがとうございます!!
って結局泣いてその部屋をあとにするのでした。対して、
「おや?」って感じで力が抜けたのは『モナリザ』でーす。
実際にルーヴル美術館に飾られているところは映像などで
とても有名だけど、本当に、ガラスケースに入ってるんだよねー。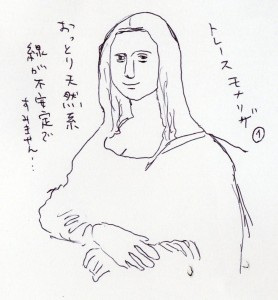
しかも、なんかね、ちっちゃいんですよ。
想像していたより小さくて、ふっと消えちゃいそう。
そういう意味では、現存していることが奇跡的な感じがします。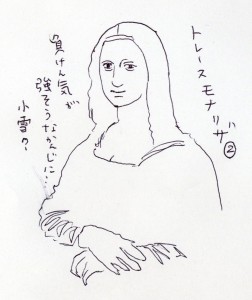
しっかしさ、パリのルーヴル美術館にしても
ニューヨークのメトロポリタン美術館にしても
ロンドンの大英博物館にしても
なんであんなに広いんですかって。見きれるかーい!!!
ミイラ見て終わるわ!(@大英博物館)
サモトラケのニケとか、片腕のないミロのビーナスとか、
ハイ、載ってましたー!!!!世界史の資料集載ってましたー!!!!(資料集大好きだからテンションUP)
って叫び出しそうなものたちが普通にゴロゴロあって。
目に贅沢すぎてそれが贅沢なのかどうなのかもはや混乱する状態。だからね、もちろん日本で歴史的な名画の展覧会を見られるって
すばらしいことだと思いますよ、思うけど、
→そこまで広くない会場に人が殺到。
→「絵の前で立ち止まらないでくださーい」って言われ続ける。
→イライラする。
→吐きそう。
ね、わたしには全然性にあわないんです。あとは、レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』。
『最後の晩餐』はミラノの教会にあるんです。
門外不出なので実際にそこに行かないと見られない。
サンタ・マリア・デッリ・グラッツェ教会。
そこの食堂の壁画として描かれたのが『最後の晩餐』です。
事前予約が必要だということで、
インフォメーションセンターにおそるおそる公衆電話から電話をかけたけど
「ボンジョルノ~??」から先のイタリア語がわからず、
英語でもうまく話せなくて、結局予約できずじまい。せっっかくミラノにいるのに!!!
それでも、教会にだけは行こう。見られなくても。
ということで、けっこう朝早い時間にサンタ・マリア・デッリ・グラッツェ教会へ行きました。
そこで、受付の人に「リザーブしていないのだけど」と聞いてみたら、
昼の回なら入れると言われ超ラッキー!!!!
ひゃっほーい!
その場で予約を入れてくれました。いやー早く行ってみるもんだー。1グループ10人ずつくらいで
そのサンタ・マリア・デッリ・グラッツェ教会の敷地を歩いて見て回る。
そしてラストに、『最後の晩餐』のある食堂へ。わたしが行ったときは、『最後の晩餐』は絵を修復したあとで、
とても鮮やかな美しい姿をしていました。食堂は、石造りで寒く、自然光と絵に影響のないわずかな照明だけ。
薄暗く、静かな食堂の壁面に描かれたそれは、ほんとうにドラマチックだった。人を黙らせる絵でした。
一瞬の情景を閉じ込めたようであり、
今まさにそのあとのドラマが展開しそうであり、
「この中にわたしを裏切る者がいる」と言うキリストの顔を見ているうちに
まわりの弟子たちの表情が変わってしまいそうで、
どこからも目を離せない。この絵のすべて、テーブルの上のパンや葡萄酒や
テーブルクロスや背景の窓や弟子の表情すべてに、「何か」が起こりつつある。
すべて同時に起こりつつある。
わたしはただ、果てしない時間をかけて生起しつつある、
『最後の晩餐』のほんの一瞬の画だけを垣間見たにすぎないのかもしれない。圧倒されて、しばらく絵の前で呆けてました。
10分ほどたち、退出を促される。もうその場にいることはできない。
あとのグループと入れ替わりで、食堂から出ると、
外はもちろん、おだやかな日差しがさしている現代のミラノ。食堂へこれから入る人と、食堂から出てくる人は、まったく表情が違う。
あの絵が、人に言葉を飲み込ませるから。
わたしは、みぞおちあたりに重たい衝撃が残ったままでした。で、ピッツアマルゲリータ、プレーゴ!
そのあと地元の食堂で「ぜんぜん晩でも最後でもない晩餐」を。
つまり、たらふく食べるのでした。動かない歴史的な名画のために、自分が動く。
そこへ行く過程(+食事)が、絵を見る体験なんです。ごっつあんです!!! -
ビューティーなソング 合唱の回
いきなりですが、みんな校歌は歌えますか。今でも。
もちろん歌えますよねー。どんだけ練習させられたかって。白亜かがやく 山の上
つどう ひとみも 晴れやかに
きたえ みがいた 意志強く
あすの 日本を 担います
たのしい ●●小学校はい、これ小学校の時の校歌(3番)ね。
日本を担う小学校だったんですねー。
スケールでかいよね!天空はるか 風清く
光みなぎる 丘の上
ここ武蔵野の 中央に
はつらつ集う 明朗の
若人我ら 眉挙げて
平和の道を いざ進まん
●中 ●中 われらが母校はい、これ中学校(1番)。
とたんに男クサイ感じになりました。
言葉も「若人」とか「いざ進まん!」とか、かなり暑苦しい。
眉、太そうだよね!
走れ夕日に向かって!飛ばせさわやかな汗!いつも半袖!そう青春!
ふう。羅列しただけで息があがるわ。
mixiだtwitterだfacebookだっていうのが当たり前の今、
この歌詞に共感できる中学生はいるのだろうか。
かと言ってはつらつ招待 コミュニティ
若人我ら オフ会で
平和の道を リツイートwとか変えてみたところで、まったく共感できないけどね!
校歌1行目にご注目~!
天空「はるか」!イェイ!露もゆたけき むさし野の
草も皆がら はゆるまで
質素をむねと むらさきの
花の香高く われ咲かむはい、うってかわってこれ高校の校歌(1番)。
なんて奥ゆかしい歌詞なのだろう!!!
「花の香」だよ!「質素」だよ!
校風があらわれますよねー。集まる生徒の人柄もねー。
いやいやそれほどでもー。
伝統のある女子高だったもんで。わたし、合唱とか好きでした。
いくら大声だしても怒られないっていうね。
ソプラノだったけど、あまり上手くはなかったなあ。
腹式呼吸はできたから声はデカかったです、ハイ。中学の時に、アッピーというあだ名のディーヴァがいたんですね、
アッピーはソプラノで、声も高いのにしっかりしてて、
オペラ歌手みたいに美しい高音のまま
ウワワアアンっていうビブラートをきかせられるという。
わたしの声がスルっとしたそうめんだとしたら、
アッピーの声は超一級品のツヤッツヤのうどん!
コシがあってなめらかで強くて光ってる!
その当時はオペラに対する知識も特になかったけれど、
アッピーがうまいのは横で聴いていて、それくらい肌で感じた。
彼女は輝いていたなあ、合唱のとき。
合唱は、え、あの人実はうまいじゃん!とか、
意外な発見があるおもしろいステージだったわけで。いつもは先生を茶化したりしてふざけてる男子が
低音がすごく響くから、気の進まないまま合唱団に選抜されたりね。
ちょっと不良みたいな女子が、アルトでいい声で歌ってたり。
好き好きーそういう展開~。そうそう、NHKの全国音楽コンクール見たことありますか?
あれねーすごいんですよみんな。顔が!
いや変な意味じゃなくてね。
合唱部の独特の、目の見開き具合、口の開け方、動き、恍惚の表情。
もう、ゆれるゆれる。ぐわんぐわんゆれる。
歌は喉だけじゃどうにもならない、
深くて美しい声をだすために、全身を使う!
そして、合唱部員の笑顔は真剣すぎてたまに怖い!
さすが全国区!目が離せない生徒ばっかりだぜ!
でも、みんな鳥肌立つくらいうまいのね!自分がその時代歌ったなかで思い出深いのは、
定番ですがやっぱり「大地讃頌」かなー。
三送会(三年生を送る会)とかだったりして、歌う時が。
クライマックスの、母なる大地を アー
讃えよ大地を アーとかグッときました。気持ちが盛り上がってくのが好きでした。
あと、谷川俊太郎作詞の「魂のいちばんおいしいところ」。
出だしがアカペラですごくきれいな曲!かみさまが だいちと みずと たいようをくれた
歌詞がほかの合唱曲と違って、詩的でした。そりゃあたりまえか。
ぜひ聴いてみてください。
それはとても簡素な言葉で書かれていて、
そのまま歌っても、ピンとこない。そうして あなたは 自分でも気づかずに
たましいの いちばん おいしいところをくれたこんな透明な歌詞だから。
歌う自分の気持ちがまんま反映される。
ごまかしがきかない。
何も考えずに歌うと、ほんとに歌詞が死んじゃうんだよね。
歌詞が透きとおったままで、いかに気持ちをのせて、伝わるように歌うか。当時は「気持ちをこめて」歌うことがとても難しかった。
きれいに歌うだけじゃダメで、気持ちがこめて歌えって言われてもー!?
そういえば、柿沼先生(音楽)は「歌詞をちゃんと読んで。考えて」って言ってたなあ。
先生!いま、ようやく歌詞の大切さがわかりました!
・・・遅。もはや合唱とは縁遠い日々。
久しぶりに合唱曲とか探してみると、これ歌ったー!!!っていうのが
たくさんあっておもしろい。
「旅立ちの日に」とか「走る川」とか「時の旅人」とか「春に」とか「聞こえる」とか「IN TERRA PAX」とかね。合唱曲はけっこう、いやかなりいい。
でも今それを聴くと、懐かしいと同時に、なんか照れる。
卒業アルバムを見ているような
Tシャツinでハイウエストの自分を見るような
こそばゆい感じっていうか、恥ずかしい感じも若干する。
でもさでもさ、そうじゃなきゃ合唱曲と言えなくない!?ちょっと前の話だけど、
ある中学校で「GR」ではじまって「eeeeN」みたいな名前のグループのね、
すごくヒットした歌を卒業式で歌ったらしい。まあキセキですが。
それ、どーよ。どうですかみなさんは。わたしだったら絶対×5億くらい嫌。
だってつまんないじゃん!流行った曲ってだけじゃん!
ハモれるの?混声合唱なめんなー!!
でもアンジェラ・アキなら許す!
「手紙~拝啓十五の君へ~」なら許す!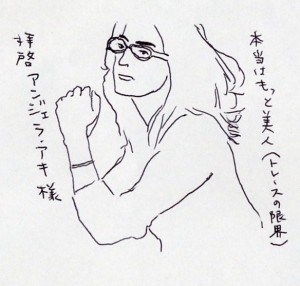
でもでも!卒業式は断固!「旅立ちの日に」であり、「巣立ちの歌」だーーーー!!!!
ちょっとテンションあがったので歌詞のせますね。「旅立ちの日に」 1991年
白い光の中に 山並みは萌えて
はるかな空の果てまでも 君は飛び立つ
限りなく青い空に 心ふるわせ
自由をかける鳥よ 振り返ることもせず勇気を翼に込めて 希望の風に乗り
この広い大空に 夢を託して
(中略)
今 別れの時 飛び立とう 未来信じて
はずむ 若い力 信じて
この広い この広い 大空に「巣立ちの歌」 1965年
花の色 雲の影
懐かしい あの想い出過ぎし日の 窓に残して
巣立ちゆく 今日の別れいざさらば さらば先生
いざさらば さらば友よ美しい 明日の日のため
いざさらば~のところでピアノがジャンジャンジャンって駆け上がる感じとかたまらん!
他にも「仰げば尊し」ありますが。個人的にはこの2つが好きだよねー。
ていばんバンザイ!定番こそ心に残る!
ずっと歌い継がれてきた歌はどれも最高さ!!
流行りのJ-POPは打ち上げのカラオケでどーぞっ!!はあ~もう検索してピアノの伴奏はじまっただけで涙が・・・。
広くて天井が高い体育館。
だれかの咳払い。
清楚で可憐な女子のピアノ伴奏。
空気の間を満たしていく声。
指揮者はちょっと動きが単調なクラスメート。
隣には、ディーヴァのアッピー。まだガリガリだったわたし。
その頃から比べたら・・・増えたよ体重 アー!!!!!!!!!
超えたよ大台 アー!!!!!!!!!以上、my「大地讃頌」でした。おあとがよろしいようで。
-
ビューティーなソング 母の回&父の回
寝ても覚めても白ご飯のことを考えていると思われているビューティーですが、
そんなことないよね。最近は歌のことを考えていたのだ!
じゃじゃーん!
だれかが歌っているとそれが耳に残っちゃって、
結局自分も歌っちゃうってことあるよねー。
うんうんあるあるー。
それは当然のことだが歌がうつっているのだー!
最近わたしがうつって、無意識に口ずさんでしまうのは
そう!宝塚のミュージカル『エリザベート』のナンバーです!!!!「エ~リ~ザベ~ト~泣かない~で~おやすみ~わたしの~うでの~なか~で~」(トート)
3時間のDVDの見過ぎで歌詞覚えちゃうっていうね。
歌いたくなるいい曲たちなんだよう。ミュージカルは曲が命!
「あなたには~たよら~な~い~~。・・・出ていって!」(エリザベート)
そのミュージカルを観たあと、
マネしたくなるかどうか!?でミュージカルの良し悪しがわかるよね!
あと自分のハマった度がわかるよね!でも、ずっと憶えてる歌ってありません?
J‐POPとかじゃなくて。わたしは、もう十数年前に聞いた歌を、いまだに憶えてます。
それは絵本のなかにでてくる。
タイトルは「ぞうのたまごのたまごやき」。
そこにでてくる一節、ぞうが たまごを うむなんて
ぼくらは きいた ことがないという部分なのです。
この部分ね、忘れられないんです。
それは、母が歌ってくれたからなんですね。
もし、異星人に連れ去られて脳の記憶リセットボタンをポチっとされても、
これは歌えそうな気がする。
ってくらいからだになじんでるのさ。もちろんミュージカルみたいに朗々と歌い上げるわけじゃなく、
節とリズムがついてるだけ。
もともと絵本に、「ここは歌って」とか「♪」がついているわけじゃない。母は、ぜんぜん自分の感覚で歌ってくれたんです。
お姉ちゃんも、その絵本を母に読んでもらっていて、歌を知ってる。
だから同じように歌える。同じ音程。同じリズム。どの絵本よりも、その絵本はわくわくした。
長新太の、色が鮮やかにあふれてる絵がすばらしかったのもあるけど、
母の歌が、やっぱり好きだったのかもなー。
絵本を子どもに読むときは、ぜひ歌ってください!
だって、ずーっと憶えてるし!記憶消されても歌えるし!(たぶん)。母は、絵本をかなり楽しんでいたと思う。
自分が『雪の女王』好きだったから、そればっかり読んでくれたり。
しまいには自分のものにして、わたしの本棚からは消え去りました。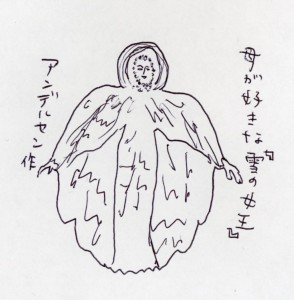
『てぶくろをかいに』では、わたしはこどもながらに、
母の「おててがさむいよう」という子ギツネのセリフに涙したものです。
ていうかもう、そこしか記憶にないよね!
いまでも、『てぶくろをかいに』の話になると、
懐かしいわ~あれ好きだったの~特に「おててがこごえちゃうよう」の場面、
と、絶妙にセリフをアレンジして再現してくれます。ちなみに父は、寝る前に、お話を聞かせてくれました。
登場人物はその回によって増減があったけど、
太郎、次郎、花子の3人のみ!
花子にいたっては、登場回数がかなり低かった気がする。父はわたしの隣で、気難しい顔を少しだけやわらげて、話し出す。
こんなふうに。太郎は、道で次郎と出会った。
「やあ、次郎くん」
「やあ、太郎くん」
・・・・・・・・・・・・・・ドンデンドンデンドンデン!完!
っていう。
数秒!
っていう。
ほんと短かったんだよねー。
しかも、謎のエンディングテーマ「ドンデンドンデンドンデン!」。なんだろう、これ。
でも、このテーマ大好きなんですよねー。
本当は「次回を乞うご期待!」のテーマなんだろうけど、
そのあとまったく次回につながらず、強制的に1話完結でした。もちろんお姉ちゃんも、父からこのドンデンストーリーを聞いていた。
二人とも、そのお話に夢中だった。
太郎、次郎、レアキャラ花子。
花子がでてくるとこんな感じ。太郎と次郎は、あそんでいた。
そこに、花子がやってきた。
花子は、走り出した。
「待っておくれよ、花子さん!」
太郎は、花子のあとを追った。
・・・・・・・・・・・・・・ドンデンドンデンドンデン!あれ、次郎は???
花子、なぜ突然現れそして走り出す???
不可解すぎて逆に目覚めるわ!っていうね。話はじめるぞーと言われたことはないんです。
わたしがお話きかせてきかせてーと言った記憶もあまりない。寝るまでの、永遠にのびていきそうな不思議な時間。
まだ電気はついていて、
ふとんの上で、父が隣でひじをついて横になっている。
わたしは、お気に入りのキティちゃんのタオルケットに
くるまって(この頃から可愛かったんだね!わたし!)なんとなく、ぼんやりしていて。
そんなとき、おもむろに、話ははじまるのだった。ほんの一瞬だけ、想像の世界に登場する太郎や次郎や花子。
ぜったいに名前を呼び捨てにしない、太郎や次郎や花子。
ちょっとしゃべり方が古風な、太郎や次郎や花子。聞いているときは、自分よりすこし大人の、中学生くらいだと思っていた。
お話はすべて学校の外のできごと。
夢うつつに想像した太郎と次郎は、昔の中学生みたいな学ランと角帽姿。
でも、窮屈な学ランを男らしく脱いで、
きっと白いTシャツっていうか肌着?だったはず。
ヒロイン花子は、淡い色の花柄ワンピース!まるで小津安二郎の世界。
ぶ厚くて難解なドイツ語の研究書ばかり読んでいるそんな父が、
わたしとお姉ちゃんに聞かせてくれたベリーショートストーリー。
はてしなく続いていきそうだった。
太郎も次郎も花子も永遠に、中学生のままで走り回っていそうだった。そして、いつまでも耳に残る「ドンデンドンデンドンデン!」。
もしかしてどんでん返しがあるぞって意味・・・?
でも1話完結だったよね・・・?
いまだ謎!ぶっきらぼうな、なげやりな、あっという間のドンデンワールド。
でも、わたしははっきりと、太郎や次郎や花子を知っている。
太郎と次郎が親友で、花子は二人のアイドルであること。そして、父はいつも眠そうだったこ・・・・・・zzz