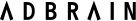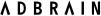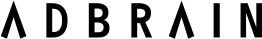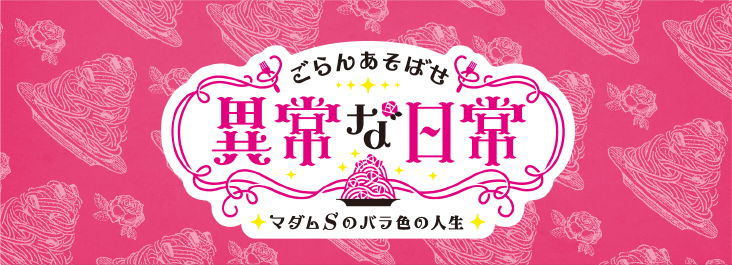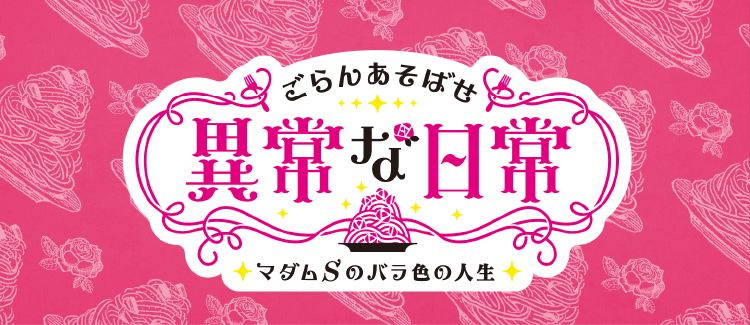-
レオ様の回
あー映画観に行きたい。
週に1回は映画館に行かないとだめですね、やっぱり。けっこう前ですが、ギャツビーの映画を観たのです。
『華麗なるギャツビー』。恥ずかしながら他に書籍や映画にふれていないので、
ギャツビー的なるもの、に接したのはその時が初めてでした。ギャツビーを演じたのはレオナルド・ディカプリオです。
みなさんにとってディカプリオがどういう存在かはわかりませんが、
わたしにとってディカプリオは「スイートフェイス」です。甘い。甘すぎる。なんだあの甘い顔は。
外国産のお菓子のように胸焼けする甘さではなくて、
外国産のなかでも上質で上等で
これならいくらでもいただきたいわムッシュ
ウィマダム
って言いたい感じの甘さ。だから、わたしは別に興味なかったんですディカプリオ。
むしろ苦手でした。
だってロミオなんだもん。乳くさいんだもん。
昔も昔、映画『ロミオ+ジュリエット』のロミオでしたよね。(1996年公開)
今回のギャツビー同じ監督の作品なんだなぁ。その頃、あ~なんて甘いイケメン(その当時イケメンという言葉はなかったと思いますが)
だろうと思って、アメリカマジ怖いと思っていました。
イケメンという言葉がなかった頃、わたしたちはイケメンたちのことをどう呼んでいたのでしょう。
ディカプリオに限って言えば、「レオ様」でした。レオ様かぁ・・・
そのあと満を持して『タイタニック』。(1997年公開)
これら作品の取り上げ方でおわかりかと思いますが、
ディカプリオに関してはまったく浅い知識しかありません。わたしがディカプリオって名前も可愛いねーゲヘゲヘという
馬鹿みたいな感想しか抱けなくなっていた最近、
『ジャンゴ 繋がれざる者』を観たのです。タランティーノの映画を映画館で初めて観たのですが、
タランティーノ面白いです。
観終わったあと、口いっぱいに銃弾を詰め込まれる感じで、しばらくしゃべれません。
その映画で、ディカプリオは悪役でした。
それもどうしようもなく残虐非道で、下衆な悪役。
救いがたいほどの下の下。
でもね、それが魅力的だったんです。
あのスイートフェイスでキレた悪役をやられるとハマるハマる。ディカプリオの魅力は、「狂」であり「凶」でこそ発揮されるのだと知りました。
話がようやく先頭に追いつきました。
そうです、ギャツビーなディカプリオの話です。ギャツビーなディカプリオは、一言でいうと、「おっさん」でした。

映画の年齢設定としては32歳かそこらだったはずですが、
もっと、可愛いおっさんでした。そして、わたしは気づいたのです。
「おっさんなディカプリオこそ、わたしが求めていたディカプリオだ」と。いつまでも甘いディカプリオの顔。
おっさんでも甘いディカプリオの顔。でも、ディカプリオはもう、ロミオではありませんでした。
蛇足ですが、わたしはロミオという役は、
「年齢的に精神的にロミオそのものの役者」が演じてもまったくドラマ性がないと思います。
つまんないでしょ。
ロミオと同一化するだけでは、ロミオ以下にしかならないでしょ。
「ロミオを全力で生き抜くあまりロミオでなくなる」という現象こそがロミオであり、
役を演じることで結果的に役が剥がれてしまう激しい運動そのものが、
死へ求心していくロミオという存在に説得力を与えることができます。ディカプリオがロミオを演じたとき、ディカプリオは奇跡的にロミオそのものでした。
だからつまらなかった。ロミオから逸脱していなかったから。
レオ様イケメン様でしたけど。でも今、ギャツビーを演じるディカプリオは、
見た目はロミオマスクのままでも、中身はロミオ失格でした。
もうね、おっさんでした。だから、すばらしかった。
そのことにどんなに心躍ったか。
嬉しかったなぁ。これからどんどん年を重ね、どんどん老けていくレオ様。
そのことがわたしは幸せでなりません。ディカプリオは老けてこそ、老けてこそなのです。
じいさんという言葉以外に形容する言葉がなくなった時に、
「好きな俳優:レオ様」とフェイスブックに書き足したいと思います。
フェイスブックやってませんけど。わたしの愛する宝塚でも、『グレート・ギャツビー』として舞台化されています。
今いちばん観たいギャツビーはもちろん、蘭寿とむさんのギャツビーです。絶対いい男なんだよ・・・蘭寿ギャツビー。
真剣に観たいです、ランジュビー・・・。 -
かぶく回
夏です。暑いです。汗だくです。
私事で恐縮ですが、わたしは宝塚ファンです。(知ってるよっていうね)
宝塚が好きで、宝塚を愛してます。
その生粋の宝塚ファンのわたしが・・・遂に歌舞伎に!明治座に、行ってまいりました。
いや、素晴らしかった。
歌舞伎、素晴らしかった。今回非常によいお席で観させてもらったので、
んもう白目むきっぱなしでした。宝塚の舞台は女性しかいません。
同じように、歌舞伎の舞台には男性しかいません。
宝塚では「男役」が、歌舞伎では「女形」が、それぞれ性を越境するわけですね。
その仕方が、こうも違うとは。驚きでした。歌舞伎を観て強く印象に残ったことは、その力強さでした。
様式美に変換されているとはいえ、
舞台に、中村勘九郎が一人立つ、その時の圧倒的な雄々しさ。
ああ、受け継がれるとは、伝統とはこういう力なのかと思いました。勘九郎の「見得」は重さで言えば1tくらいありそうな様式美でした。
それは、代々見得をきってきた歌舞伎役者の、
そしてこれからも見得をきりつづけるであろう歌舞伎役者の、
「技」の歴史、その集積を見ているようでした。
勘九郎は父親の見得をずっと見ていたのだろうなと。歌舞伎はすべてが様式美です。
すべて型があり、型のままです。でも型のなかで役者が燃えている。
わたしは『実盛物語』を勘九郎で観ましたが、
勘九郎の実盛は、若鷹のように強く美しかったです。
そして、七之助。
よく、男が演じる女形は女より女らしく見えると言われます。
わたしは女形を生まれて初めて、生で観ました。七之助の女形は、とにかく、妖しかった。
そして、闇がありました。近づくとその真っ黒な腕がにゅうっと伸びてきてつかまれてしまいそうな。
女性らしかった、とか女そのもののようだった、とはあまり思いませんでした。
それよりも、「恐ろしい」と思いました。宝塚の男役は、夢の世界からやってくる王子様のようですが、
歌舞伎の女形は、闇の世界からひらひらと飛んでくる蝶のようです。闇を飛びまわる蝶。
七之助に漂う闇の雰囲気は、正体のつかめない感じはいったい何なのだろうと、
ずっと考えていました。七之助の女形は、とても冷え冷えとしたものを持っていると思いました。
それが、異様なまでに妖しい翳りとなって、劇場の空気を冷やすのです。宝塚の男役を「男にしか見えない」と形容するのが、
わたしはあまり好きではありません。言い得ていないような気がするのです。男役は、女性が思う「理想の男の姿」を演じている。
だから、それはいつまでもリアルにならない架空の概念なのです。そんな男は現実にはいない。
精神分析で言えば「対象a」です。
対象aは、見えていても追いつくことのできない、逃げていく一点。
いつまでも手に入らないからこそ、その対象が欲望を駆り立てるわけです。歌舞伎の女形も、「女にしか見えない」わけではない。
女形は、女という概念が濃密に凝縮された存在です。確かに艶めかしく、美しく、色気がある。
でもその七之助の身体を、その核を見定めようとしても、できないのです。
飛び回る蝶は常に姿を変えていて、いつまでも焦点が合わないのです。歌舞伎の圧倒的な強さ、ますらおぶり。
伝統、格式、芸、すべてにおいて強靭でした。そして、宝塚の男役、娘役という存在が、
いかに儚いものであるかを、思い知りました。お花畑。
揶揄を含めてよく宝塚はそう表現されますが、その通りだと思います。歌舞伎はまったくお花畑ではない。
歌舞伎ほど強固な芸術もないだろうと思いました。基本的には、歌舞伎の女形は引き算で、宝塚の男役は足し算のような気がします。
でも、七之助が自分からただ男性性を引いただけでは、魅力的な女形にはならない。
そこに強さが必要になる。性を転換する強さ。
男でも女でもない、現実世界にまったく存在しない女形を、
0の存在を、そこに成立させる強さ。
かぶく強さ。宝塚の男役も同じです。
わたしの好きな男役さんは花組トップスターの蘭寿とむさんですが、
彼女が自分に男性性を足しても、観客を求心できる華々しい男役にはならない。
そこで、そう、魔法の粉ですね(違います)ここでも、重力に逆らって逆立ちで生活するような、
流れる滝を逆流して上昇しようとするような、大きな力の転換が必要です。反逆と言ってもいい力。
世界を納得させるだけの、跳躍。その、肉体が概念へ命がけで飛躍する姿を、わたしはやはりまぶしいと思うわけです。
涙がとまらないわけです。
並大抵の努力ではできないことでしょう。歌舞伎を観たことで、宝塚への愛もまた深まりました。
そして、歌舞伎は絶対に観るべきものだと思いました。ではみなさん、夏は歌舞伎座でお会いしましょう。
-
記憶の回
先日、母と姉と三人で目白をぶらぶらしていたとき、
母が突然、立ち止まりました。通りに面した、洋服の仕立て屋さんの前でした。
「こういうお店を持つのが、お父さんの夢だったの」
と自分に語って聞かせるように、母は言いました。
母の父は、下町の小さな仕立て屋さんで、
生地などはお店に置いていなかったそうで、
注文を受け、生地を買いにいき、それを仕立てていたとか。母から聞く昔の話は、わたしとは直接つながらない遠くの風景だけれど、
母という存在から伸びていく母個人の記憶の枝葉は、
わたしにもどこかしら懐かしさを感じさせます。
娘のわたしにとっても、とても興味深いものです。お店の前で立ち止まった母の後ろ姿が、
店の奥で仕事している父の姿をじっと見つめる、まだ幼い少女に見えました。突然そばにいる人間との関わりが途切れ、
自分が、自分の記憶の中の景色をつながる。わたしにも経験があります。
この間、久しぶりに、大学時代によく行っていた映画館で、
高校から大学まで一緒だった親しい友人と、映画を観ました。トマス・マンの小説をルキーノ・ヴィスコンティが映画化したものです。
わたしは、彼女と映画を観ること自体が久しぶりでした。
そして隣に座ったとき、ああこういうふうに、過去にも隣に座って映画を観たなと、
心のなかに淡く記憶が広がりました。映画は、ある中年の芸術家が、遠く離れたベニス(ヴェネツィア)の地で、
世にも美しい16歳の少年(タジオ)に一目ぼれをする、というまぁ、お耽美な話です。
映画を観ればよくわかりますが、とりあえずタジオ、美形です。
美少年の原型っていうのはこのタジオなんだろうなぁ。
おもしろかったです。プラトニックラブで。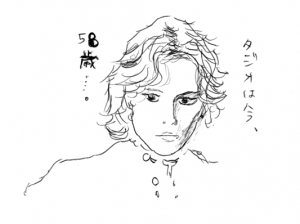
駅から大学までの道は、歩いて10分~15分ほどあります。
3分の1ほど行ったところに、その映画館はありました。
いわゆるミニシアター、単館系の映画館です。駅前は学生でごった返し、いくつものグループがそこここにできて、
点灯し続けるネオンを音声化したような喧騒でした。映画を観終わったあと、近くのイタリアンで食事をし、いろいろな話をしました。
飲み会でもなく、二人でお酒を飲んで話すというのは、不思議でした。
お互いにしょっぱい時代を過ごしたなぁという照れと、懐かしさ。
会計をするときに「いいよ出すよ」と多めに出そうとするところに、
二人とも社会人になったのだなぁと小さな感慨を覚えたり。駅まで帰るときも、いっそう人混みは増し、
人々のざわめきが交差点を埋め尽くしていました。その時に、ちょうど大学方面から帰るかっこうで駅を見て、
すごく奇妙な気がしました。磁場がゆがんでしまったようで、ぐらぐらした感覚に襲われました。
大学を卒業してもうずいぶんと時間が経つのに、
駅前に広がる光景が、ひどく親しげに、生々しく感じられたからです。
まだ社会に属していない、お気楽でモラトリアムな大学生に
一瞬にして戻ってしまったような気がしたのです。大学時代の4年間という今にしてみれば膨大な時間は、
わたしのなかで泡のように消えてしまっているはずでした。
もちろん4年間には4年間なりの密度と、できごとと、変化があったけれど、
それはもう何もかも終わってしまったことだと思っていました。なのに、そのすべてが未決のままわたしの背後に、
大使館の敷地にあるちいさな黒い森のように、
ひっそりと残されているような気持ちになったのです。振り返ったら、本当に大学1年生から、また4年間をやり直さなければいけない。
もう一度、一からたどらなければいけない。そんな気がしました。「もう10年だよ」
彼女の声がして、わたしは我に返りました。
「そうだね」
高校時代から、そう、もう10年経つのです。
お酒を飲んだせいで、少し酔っていたのかもしれません。
酔うと、だいたい人はセンチメンタルジャーニーに旅立つものです。
記憶には、そういうあまのじゃく的なところがあるのです。
人を、混乱させて、困らせてやろうというような。
小さなこびとのような。みなさんは、村上春樹の新作は読みましたか?
100万部売れる小説というのは、一体どんな小説なのか。
村上春樹の新作だけが異常に売れる社会は、一体どんな社会なのか。
なぜ村上作品の森にはこびとがいるのか。でも、村上春樹が出す本はこれからもベストセラーでしょう。
わたしは、今の新刊の続編、パート2が出版される気がしています。ぜひ、自分で本屋に行き、手に取り、買って、読んでみてください。
まぁ・・・学生時代ってのは、すべからくしょっぱいもんだと思います。 -
花粉症にはならない回
サッチャーが亡くなりました。

世界の教科書、もっとも混迷をきわめる現代史で、異様な存在感を見せていた鉄の女が・・・。
現代史のモノクロの記録映像に繰り返し出てきた、
その人物がまだご存命だったことに軽く衝撃を受けつつ、
悲報を知りました。天国にはものすごい数の世界史的著名人が集合していることになり、
天国史を早くだれか、ドストエフスキーでも、プルーストでも執筆しないと、
非常にもったいないことになるのではないかと思っています。
いつか召された暁には、書いてみたいですね、天国史。話は変わりますが、わたしは、花粉症じゃないんです。
はい。それだけです。今年も桜は満開でしたね。春の嵐でもう葉桜になってしまいましたが。
わたしもぶらぶらとお花見をしました。
あの狂乱とも、狂宴とも思える人々の高揚した雰囲気を見ていると、
満開の桜には、人を惑わす妖気があるように思えてなりません。坂口安吾の『桜の森の満開の下』も、そんなお話でした。
春になると、ぜったいにこの小説を思い出します。
最後の場面がとても静謐で、儚く、背筋がぞっとするほど美しいので、
ぜひ読んでみてくださいね。春は、別れの、そして出会いの季節。
かく言うわたしも、大勢の、本当に大勢の諭吉(紙幣)と別れを告げています。
みんな・・・どうして黙って出て行ってしまうんだ!!!!!
新しい諭吉との出会いは・・・まだ遠そうです。高校生から大学生へ変わるときの別れが、一番さびしかった記憶があります。
慣れ親しんだ教室、先生、そして友達。
それぞれの進路が決まり、もうまったく別々の道を歩いていくんだなと、
決定的な別れなんだなと、どこか甘い痛みを抱えながら春を過ごしていました。でも、大事なことはそんなに覚えていないのです。
黒板にたくさんの色のチョークで、「忘れない」「ありがとう」など
青春真っ盛りのメッセージを描いたのは中学生だったか。
それとも高校三年生だったか。
今、戻りたいかと聞かれると・・・戻りたくない気がします。
もう繰り返せない、取り戻せないことが、愛おしいのだとわかるからです。わたしの好きな宝塚にも、「別れ」があります。
タカラジェンヌが宝塚を卒業する、退団。
毎公演必ずいるわけではないですが、多い時には10名弱やめてしまうこともあります。
その公演で退団してしまう退団者の方を見送るのは、やはりさびしいもの。ファンにとって、宝塚は、
「あなたを愛している」「わたしもあなたを愛している」
という愛を交換し合う場です。退団は、その交換が終わってしまうということ。
愛を受け取り、また愛を送っていた相手がいなくなってしまうのは、
とても、さびしいものなのです。宝塚ではでも、別れ方としては「円満」かもしれません。
別れは相手(ご贔屓)から告げられますが、
ファンはご贔屓が卒業するその日まで、精一杯、諭吉にがんばってもらい、
ご贔屓の姿をたくさん目と心に焼き付けて、お別れをします。
手切れ金という言葉が一瞬浮かび、円満でもないような気がしましたが、
ご贔屓のためならお金だって時間だって惜しくないのが、ファンというものです。毎年20倍を超える難関を突破し、
タカラジェンヌになるための音楽学校へ入学してくるおとめたち。
熾烈な競争を勝ち残り、「スター」となれるのは、本当にごくわずかです。在団中「通行人」「男A」「女B」ばかりをやったタカラジェンヌだっているでしょう。
そのおとめは、退団後にいったいどのような人生を歩むのでしょうか。卒業する生徒は、宝塚の名物でもある「大階段」を呼ばれる26段の階段を降りてきます。
大階段のてっぺんに行くためには、その裏にある「陰段」をのぼります。
大階段には、ショーの最後にトップスターだけが立てる「0番」という場所があり、
卒業するタカラジェンヌは、皆その「0番」に立ちます。
そして、一番まぶしいスポットライトを浴びます。その時の気持ちは、いったいどのようなものなのでしょうか。
もしかしたら、そのおとめにとって、やめるその時に浴びるスポットライトが、
いちばんまぶしいものかもしれない。宝塚には俗に「自画自賛ソング」と呼ばれる歌があります。
「タカラジェンヌに乾杯!」やら「ああ宝塚わが宝塚」やら
「私はフェアリー」やら「フォーエバータカラヅカ」など、
自分たちをほめたたえる歌が多く存在します。それがまた・・・いい歌なんですけどね(笑)
宝塚は、夢の舞台です。
タカラジェンヌというのは、現実に存在しているけど、とても不思議な存在です。
お客さんに夢を見せるために、
人生のもっとも充実すべき青春のすべてを舞台に懸けて、去っていく。
だれもが、去っていきます。
その美しい夢の跡だけが、わずかに残るだけです。
だからこそ、わたしはやっぱり、そのことを讃えたくなるのです。
タカラジェンヌに栄光あれ!と叫びたくなるのです。ああ。
そんなこと考えてたら目と鼻から大量の水分が。。。よく、同じ公演を何回も観て楽しいの?と聞かれますが、
楽しいです。(即答)
それ以外の答えはないです。
むしろ、まだ出会ってないそこのあなたが、
人生において重大な損失をしているのではないかとさえわたしは思います。
あ~もったいない。もうすぐ本格的に、春ですね。
諭吉との別れも、まるで夢の世界のできごとのように感じますが、
通帳を見てリアルに夢からさめる今日この頃です。 -
オチない回
みなさんは落語を聞きに行ったことがありますか?
わたしはここ2年で、3回落語を聞きに行きました。
少な!!!!立川談春
立川志らく
柳家小さんです。
落語の詳しいことはまったくわからないのですが、
落語、おもしろいよね~。母は落語が好きでね、よく一人で新宿の末広亭に行ったり、
落語のCDを聞いたりしていて、
わたしに「いかに面白かったか」を話してくれるんですが、
その話がびっくりするくらい面白くないの(笑)あれ、なぜなんでしょうね。
面白さを伝えられないっていうのは。わたしもよくあるんです。
すごく面白いことに遭遇して、もういてもたってもいられなくて、
ばばばばばーっと話すんだけど、「で?」
って言われること。
母の落語話も、
話している母自身は、その時の情景を思い出してるから爆笑なわけ。
もう箸が転げてもおかしいってくらいに。でも聞いてるわたしはポカーンなんですよ。
落語ってほんとに面白いのかな・・・って疑ってしまうというものです。で、そんなふうに敬遠していた落語でしたが、
試しにということで落語に誘ってもらって、行ったんです。
そしたら楽しいのなんのって。
いや~落語ってすごい。生ってすごい。古典落語と新作落語とありますが、
わたしはわりと古典落語が好きです。
って、まだ3回しか行ったことないのに言うよね~。「話芸」なんですよね。
芸なの。
プロなんですよ。当たり前なんですけどね。
言葉だけなのにものすごくドラマチックで、
わたし、志らくの「抜け雀」という話で泣きそうになりました。で、あまりに感動したので美容室でいつも担当してもらっている男の人に、
一席かましてみたんです。抜け雀をね。
「・・・」
最後のオチを話して反応を待つこと30秒・・・。
「・・・えっと最後のはこれとこれがかかっててつまり」
ぬわーーーーーーーー!!!!!
こらえきれずにオチの解説をしてしまったああああああ。
蛇足この上ない!
ばかっ!わたしのばかっ!でも、これにはワケがありまして。
わたし、「抜け雀」の最後のオチが、わからなかったんです。
恥ずかしっ子現代っ子。オチはだいたい、Aという言葉とBという言葉が同音異義語でかかってて、
その見事なかかり具合を最後に聞いて、「おお~あっぱれ~!」となるんです。
そのオチが腑に落ちたときの感動ったらないですよ。
こんな快感があったのかと・・・!
快感で体に電気が走ります。震えます。マジです。でも、「抜け雀」はそのオチのかかり方がわからなくて、
終わったすぐそのあとでウィキで調べて(もはや情緒なし)、
そこで、ああそうだったのかと。
感動の波再び。ね~。
志らくのトークをちょっと聞いたんですが、
師匠の談志が、ある方のお葬式に行ったとき、
きったねぇジーパンみたいの履いて(志らく談)、
そう、みなさんの中のイメージの通りのあの談志スタイルで、
正装なんかしないわけですよ。
で、こう仏さんの前に立って、こうぞんざいにバッバッてお焼香して、「・・・あばよ」
って一言つぶやいて去ってったとか。
痺れるぅ!ね~。
わたしが朝出社して、タイムカード押して、
「・・・あばよ」
って一言つぶやいて帰ってったら乙ですよね~!
はい、オチなくてすみませんでした!(スライディング土下座)