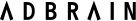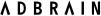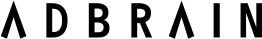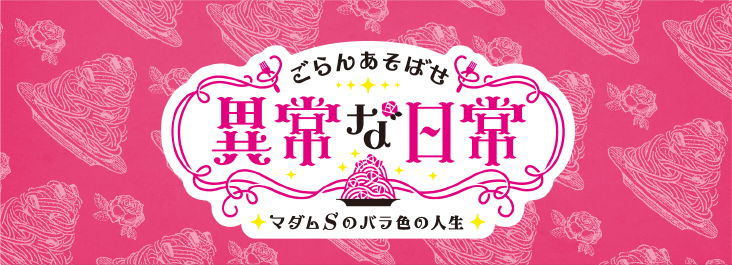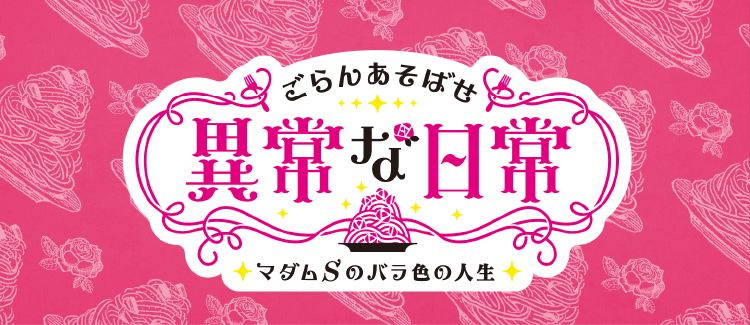-
「走らせている人」たち
コピペ、リニューアルしましたね。
いいですよ、リニューアルは。
たまにはリニューアルするものですよ、人はね。
リニューアル、サッカーで言えば移籍ですね。
話題は、やはりこの人。

バルセロナで長く活躍してきたイニエスタが
ヴィッセル神戸へ移籍と聞いたときには、
なんで!?という気持でしたが長いサッカー人生、
一度くらい日本でのプレーがあってもいいのかな、
KOBE Beefはおいしいですよね…。FWをよく走らせている人、イニエスタの話かと思いきや、違います。
これは、少し前にTwitter上で話題になって、
わたしも自分の身を振り返ったことなのですが、
日経新聞に作家の村田沙耶香氏が寄稿していた
「走らせている人」たち、の話です。冒頭の村田氏の言葉をすこし引用してみましょう。
数年前、友達の家に大勢で集まって宴会をしていたとき、
1人の子が皆を見回しながら、
「皆、車や電車で窓の外に人間を走らせているじゃん? 赤信号とか駅で停(と)まったとき、その人間、どうさせている?」と言った。「あー、どうだったかなあ」と考え込む人と、
「待って待って、人間走らせるって何!?
え、それ、皆やってるの!?」と動揺する人と、
リアクションは真っ二つに分かれた。これを読んでいるみなさんの反応も、きっと分かれているでしょう。
あなたは「走らせている人」でしたか?
子供の頃から、わたしは、ごっこ遊びはよくしていました。
ほかの子と遊ぶときは、遊具で延々同じことを繰り返したり、
だれかが鬼になって孤独な思いをしたりと、理不尽さがつきまといます。
ごっご遊びに関しても、
自分が構築したストーリーの共有から始めなければならず、
それがたいそう手間取る上に、
共有したはずのストーリーをいとも簡単に忘れてしまう、
あるいはハナから知ったこっちゃないわという友達の幼稚な横暴のせいで、
自分の物語を完璧かつ美的に上演したいわたしの欲望は
いつも満たされませんでした。当然、いつからか、ひとりで遊ぶことが常になりました。
ひとりなら、そういったストレスがないばかりか、
物語の不都合も華麗にスルーできるし、
だれかが迎えに来て物語が途中で頓挫しても、
後日好きなところからまた再開することができます。たいてい、ホットな主人公とクールな相棒の友情モノか、
特殊能力のある5人グループの冒険潭が中心でした。ごっご遊びは、基本的に自分がすべての役をやる、いわば一人芝居です。
だから、だれかにそれがバレた日には
自分で考えだした(もちろんどこかで見たり読んだりしたものの流用)
設定やら名前やらの恥ずかしさで憤死するほどだったし、
絶対に他人には知られてはならない危険な遊びでした。子供ながらにカモフラージュのためだったのか、
わたしはバスケットボールやサッカーボールなどの球遊びをしながら
ごっご遊びもする、というかなりの上級者テクを使っていました。そのせいで注意が散漫になり、
マンションのベランダや他人様の家の庭へよくボールを飛ばしていました。そういうロンリネス劇団ひまわりな子供時代を過ごしていたので、
ほかのキャラクターを世界に存在させて動かすというより、
自分がそのキャラクターになって空想の世界で動くことが好きだったのです。わたしは「走らせている人」ではありませんでしたが、
その代わり、「透明なミジンコを追いかける人」でした。は?と思ったそこのあなた、よーく子供の頃を思い出してください。
宙に、ちっちゃなミジンコが浮かんでいるのを、見たことはありませんか?
それは、目の端でしか捉えることができません。
あっいたと思うと、
ピュン!と横移動して目の端からギリギリアウトしてしまう。透明だから向こうの障子や砂壁は目に入るのに
どうしても全貌は目にとまらず、
捕まえようと思っても、手は虚しく宙をつかむばかり。大学生の頃、
透明ミジンコの話に「わたしも見たことある」とノッてくれた
ゴスロリ系ファッションの哲学科の女の子は、今も元気にしているでしょうか。忘れていた懐かしい木造の思い出がよみがえってきて、
最近、それを家族と話すときに
ロンリネス劇団ひまわり時代のテンションが一瞬戻り、
若干鼻息が荒くなってしまい
いい大人がふんふん言ってしまってちょっと恥ずかしかったです。みなさんも、恥ずかしいかもしれませんが、
走らせている人だったか、透明ミジンコを追いかける人だったのか、
こっそり教えてください。この記事を書いてしばらく経った日、
わたしはネットで衝撃的な記事を見つけました。昔、無我夢中で追いかけていた透明なミジンコ、
あのノスタルジックな現象のことを
「飛蚊(ひぶん)症」という病気だと注意喚起する医者が現れたのです。なんという夢ぶち壊し野郎でしょう。
しかもその記事内容、読めば読むほど腑に落ちることばかりで、
危うくわたしの青春時代の思い出が一つ消えかけるところでした。みなさんはそんな煽り記事に惑わされず、
自発的に眼科を受診し健康に留意して過ごしてくださいね。Users who have LIKED this post:
-
いろいろあるよねーそだねー
始まってみたらテレビの前に座ってドキドキしながら見るものな〜んだ。
そうです、オリンピックです。
金、銀、銅。
それぞれの色の輝きをどう感じるでしょうか。
銀を「残念な結果」と言ったり、銅を「歴史的快挙」と言ったり、
報道の姿勢、国(というなんだか漠とした総体)の思惑、
どの選手を応援するかという個人的な感情等々、いろいろなものに影響されます。
順位というものが相対的であるのと同じように、
その価値は絶対的なものではありません。
「金より価値のある銀」とある人は言うでしょう。
「金以外は無意味だ」とまた別の人は言うでしょう。
わたしは、オリンピックを見るとどうしても画面の向こうの4位の選手に、
世界で4番目なんだから十分すごいじゃん、と話しかけてしまうのですが
みなさんもそんなことある?
冬季オリンピックは雪の中や雪の上などで行われるものが多く、
真っ白な世界に選手のウェアのカラーが映えて綺麗でした。
世界にはたくさんの色がある。
それは幸福なことだとわたしは思います。
メダルの色は3色ですが、国旗ひとつとってもわかるように、
世界が多様であることをその色は教えてくれている気がします。
何色も、何十色もあるということの複雑性、その多幸感。
色えんぴつが好きです。
眺め、コレクションする楽しさ。
減っていってしまうのは決まって好きな色でした。
デザインプロダクションにいるのに、
「図工」という授業にはあまり楽しい思い出がありません。
とにかく絵の具が苦手でした。
準備するもの、後片付けがあるものが苦手なのです。
したがって書道もいやでした。
墨汁、半紙、すずり、文鎮……小学生のわたしにとっては
大がかりな旅行の準備くらい用意するものが多く感じられ、
授業の前日は気が滅入ったものです。
転機が訪れたのは中学生の頃。
相変わらず後片付けは嫌で嫌で仕方ありませんでしたが、
アクリル絵の具という画期的なものと出会いました。
それまでの水彩絵の具は、画用紙の上で意図しないにじみ方をして
ほとほとわたしは手を焼きましたが、アクリル絵の具はそうではなかったのです。
隣の絵の具と色がにじまない。画用紙もべこべこにならない。
なんてすてきな描き心地なのだろう。
わたしは、その頃からお手本の絵を見ながら同じ絵を描く、という行為が好きで
『もののけ姫』のサンの絵を描き宮崎駿の解説をするポスターを作りました。
でも、その絵に突出した独創性はありませんでした。
オリジナリティは「もののけ姫」や「サン」や「宮崎駿」にはありますが、
それをトレースするだけではただトレースしたに過ぎない。
アクリル絵の具の乾く音が非情にもわたしに告げます。
「ただのモノマネじゃん」
学校教育は、本物以上に本物に見える、もしくは独創性がある、
その二択にしか評価を与えてくれません。
同じものを同じように描こうと思った結果そうならなかった不思議な歪みを
面白いもの、味のあるものだと見てくれる視線は存在しませんでした。
サンの顔の不自然さ、色づかいの甘さ、上の下のような「もののけ姫」のものまね絵は、
ただの「◯」をもらって終わっていきました。
そこで教師のだれかから、あるいは今のようにSNSで知らないだれかに、
「いいね」をもらえたら、わたしはデザイナーになっていたかもしれません。
「宮崎駿」は明朝体で大きく描き、真っ黒に塗っていました。
いかにも『エヴァンゲリオン』に影響を受けすぎていて恥ずかしいです。
明朝体に憧れる中二病(昔はそんな言葉ありませんでしたが)を作り出した
エヴァンゲリオンは罪深いアニメです。
やっぱり、デザイナーにはなれそうにありません。
それでも多少なりともデザインの目は養われるもので、
昨年、ある舞台を観劇した際に遭遇したできごとを伝えたくて
持てる全てのデザイン力でそれを描いたところ、
「だてにデザイン会社に勤めていないね」と褒められました。
ありがとうございます。自信が出ました。棒人間でしたけど。
なにかができないからこそ、できるなにかがほかとは少し違うものになる。
それが時には、その人らしさになるでしょう。
というわけで、これからもトレースをがんばります。
夢はそうですね、個展を開くこと、にします。
4年後の冬季オリンピックまでに間に合うでしょうか。
トレース界を代表して晴れやかな気持ちで表彰台にのぼりたいです。
その前に、本業のコピーライティングもがんばります。 -
いぬのきもち飼い主知らず
今更感満載ですが、あけましておめでとうございます。
年賀状をくださったみなさま、ありがとうございます。自分では出さないくせに来るとうれしい年賀状です。
デザイナーの描くさまざまな「いぬ」を拝見し、
興味深く思うとともに、柴犬の少なさに驚きました。
少ないどころか、ほとんど柴犬はいなかったのではないだろうか。
ゴールデンレトリバー一人勝ち、いや一頭勝ちだった気がします。
柴犬、どうしていなかったのだろう。
なんだか「いぬらしすぎる」と思われたのかも。
だって柴犬、見るからにいぬじゃないですか。
いぬ、でしかないじゃないですか。
いぬ内での人気格差に思いをはせつつ、
今年もよろしくお願いします。わたしが最も「いぬ」に恋していたのは、小学生の頃でした。
よく遊ぶ近所の年下の子が、いぬを何頭も飼っていたのです。
その子の家には屋上にいぬ小屋があり、元気な子犬たちが駆け回っていました。
わが家では母の「だれが面倒を見るの?」という強大な封印の呪文があり、
いぬへの想いはいつもその呪文の前に敗れ去っていました。
往生際の悪いわたしは母に連れられていく本屋で
これ見よがしにペットコーナーへ赴き、いぬの飼い方を熟読。
母は知ってか知らずか、こちらに寄ってきません。
しびれを切らしたわたしはさまざまないぬが載っている本を手に取り、
ベロを垂らした愛くるしい姿でこちらを見つめるパグのページを
飽きもせず眺めていました。
それから、ようやく本屋での自分の用事を済ませた母、出現。
「飼ったら、だれが面倒を見るの?」
とどめのいちげき! びゅーてぃーは ひんしのだめーじをおった!
またも敗れ去る名もなき勇者…いぬへの道のりはかくも険しいものか。わたしはトカゲ好きな少女、でもありました。
カナヘビ、というトカゲのなかまも好きで、飼ったこともあります。
母は露骨に嫌そうな顔をしていました。
いまはその気持ち、よくわかります……。
それに、わたしは飼うのはいいものの、
掃除や餌やりといった世話を忘れる無責任な子供だったので、
いぬでも同じことが繰り返されるのでは、
という危惧が母にはあったに違いありません。
自分のめんどうくさがりな性格をなんとなく理解していたわたしは、
母の「飼ったら、だれが面倒を見るの?」が、
「この前飼ったトカゲも全然世話をしなかった」という怒りの鉄槌に
だんだん変わっていく様子を間近で見、いぬを飼うことはあきらめました。結婚した姉が小さないぬを飼い始めた、と聞いたときはだからひどく驚いたものです。
キャンキャンと鳴き、飛び跳ねる子犬。
フローリングの床で滑り、よくよく壁に激突しながら、
平気な顔でまた走る人間よりずっと小さな、暖かい生き物。
タイピング上級者のように早く脈打つ鼓動や
お菓子についてくるおもちゃのようなピンクの舌に、
わたしは理解が追いつきませんでした。
普段、似たような背格好の人間を見慣れているからでしょうか。
動物園にいる動物たちのスケールにびっくりするあの感覚を、
姉が飼った小さないぬにも感じました。
命は人間だけのものではなく、命のかたちは一つではない。
そんな当たり前のことを、彼らは気づかせてくれます。そうですね、いつかインスタグラムに
おしゃれな感じでいぬの画像をアップしたいです。インスタ映えです。
その時はみなさま、いいいぬね!略していいね!をお願いしますね。今年最初のトレースはめざましい活躍を見せる14歳の張本選手。
彼おなじみの「チョレイ」をぜひ生で聞いてみたいものです。
-
2017年、最後の話。
年の瀬です。
寒いです。
こんな寒い日はこたつでみかんを食べながら
どうです、マンガでも。姉妹の関係性はいろんなケースがあると思うのですが、
わたしは姉の影響を強く受ける妹でした。
姉が買ってきたマンガを読み、姉が買ってきた雑誌を読み、
姉が買った小説を読んでいました。
あるいは、母が私たち姉妹に読み聞かせてくれた絵本も同じでした。
姉は本が好きで、姉が欲して買いそろえた本は
自然とわたしも読むことになります。
最初に手にした本は「こまったさん」だったか「ズッコケ三人組」だったか
はたまた「アラビアンナイト」だったか・・・。
けっこうな大人になるまで、
わたしの文化圏は姉の作ったものの中におさまっていました。その中のひとつ、マンガの話をしましょう。
姉のマンガで印象的だったのは『絶愛』です。
今で言うBLというジャンルですが、
当時はジャンルのことなど理解しないまま読んでいました。
音楽業界のスターとスポーツマンの苦しく壮絶な愛…そうですまさに「絶愛」。
姉というのはえてして早熟なものですね。
いち早く、単純な異性愛を描かないマンガにも進出していました。
わたしが青山剛昌の『YAIBA!』や『名探偵コナン』を読みふけっている時、
姉は岡崎京子の『リバーズエッジ』を読んでいるような好みの差がありました。本棚には本だけ、マンガはマンガの棚へ。
そういうすみ分けがなされましたが、
姉は特に気に入ったマンガは本とともに棚に並べていました。
『11人いる!』『ポーの一族』『トーマの心臓』など
萩尾望都のマンガがそこに揃っていたのを憶えています。
大和和紀の『あさきゆめみし』や
高河ゆんの『アーシアン』『源氏』などのマンガも後に加わりました。
その中の一つだった日渡早紀の『ぼくの地球を守って』は
“前世”や“転生”という連載当時キャッチーだった(!)題材で描かれています。
わたしは姉の本棚の上段にあるそれらのマンガを読んで育ちました。
マンガ遍歴を見ていると姉は宝塚歌劇を通ってもよさそうなのに、
まったく興味を示しませんでした。
まわりの友だち、付き合う人も変わっていく高校時代、大学時代を経て
わたしの「カルチャー」は姉の文化圏から少しずつ離れ、
姉離れしていった気がします。宝塚を好きになったのは社会人になってからですが、
広大な原野を歩きながら自分で開拓していく感覚が面白く
わたしは宝塚にすぐにのめり込みました。
立派な「ヅカオタ」となったそんな折、少女マンガを変えたとさえ言われる
記念碑的作品を宝塚が舞台化するという知らせが。そう、『ポーの一族』です。
演出を担当するのは単行本1巻の巻末あとがきを担当しているほどの
「ポーの一族ファン」である小池修一郎。
彼はあまりにも『ポーの一族』が好きすぎて
似たような吸血鬼の物語をオマージュとして以前宝塚で舞台化しました。
念願かなって、彼自身の脚本と演出による
『ポーの一族』が来年元日に宝塚大劇場にて開幕、
2月から3月にかけては東京宝塚劇場にて上演されます。
わたしはこの一報を聞いたとき、
久しぶりに、実家で、姉と邂逅したような不思議な気持ちになりました。
幼き青春だった姉の本棚が目の前に立ち現れ、そこに立っているような、
部屋に差し込む陽の光の中で小さなほこりがゆっくり舞うのを見るような、
感傷的な気分でした。姉と『ポーの一族』を観る幸運な日があるといいのですが、
今回は予定が合わなさそうで残念です。
でもいつか、一緒にDVDを観たいなと思います。
そして色あせた思い出の1ページを懐かしく繰ることができたら。さて今年のトレース納めは、後輩をシメて角界を締め出されたこの人が登場。
なんとなくペンの陰影も薄くなってしまいました。
来年も、どうぞよろしくお願いします。
-
「場所が、ないからなぁ」
秋は、あったのでしょうか。
72時間ホンネテレビで元SMAPの三人(元SMAPって)と
森くんとの再会を食い入るようにパソコンで見たり、
トランプ来日による警備の厳戒態勢を感じたりしていたら、
いつのまにか秋を通り越して冬になってしまいました。
毎年同じことを言っている気がします。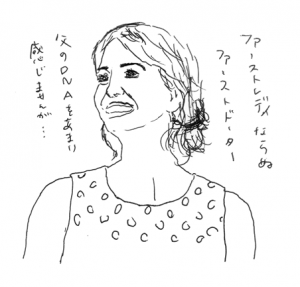
同じこと、と言えば。
昔、実家に柱時計がありました。
子供の頃、柱に掛かっていた1mくらいある柱時計を見上げていました。
ほこりをかぶったその時計が、ゆっくりと、
知らぬ間に針を動かした時のギシッという音をいまでも憶えています。
わたしがその時計の存在を気にするようになった時には
すでに現在時刻とは合っていなかったので、
その柱時計はいつからか現在を刻むのをやめ、
柱時計自身の時を刻むようになっていました。
幼いわたしは、時間がちがうよ、壊れているよと父に抗議しましたが、
「巻けば、なおるよ」とか「手巻きだから、な」とかなんとか
言いながら父が巻こうとする気配はいっこうにありませんでした。
父は時計が正しい時を打つ、ということを大切にしているのと同じくらい、
時計が正しくない時を打つ、ということも普通に認めているようでした。家を建て替えた時、その柱時計は処分されてしまいました。
わたしは、父がその時計を残そうとしなかったことが意外で、
また、どこか残念な気持ちにもなったのです。
壊れちゃったんだ、と非難とも落胆ともつかないつぶやきを
父の前で吐いたことがありました。
父は、「巻けば、使えるよ」とどこかで聞いたようなことを言い、
さしたる感傷もなさそうに仕分けしていました。小さい頃は、時間になるとよく「◯◯しなさい」と言われました。
お風呂に入りなさい、早く寝なさい、早く起きなさい。
家にいると時間は思っているよりずっと早く過ぎていき、
ある時間以降は命令を伴うのが煩わしくてしょうがありませんでした。
時間は自分の動きを制限する縄のように窮屈なものに感じられ、
そんな時いつも、デジタル表示される時刻の無慈悲な正確さを疎ましく思ったものです。ある時、デジタル時計の表示が乱れていることに気がつきました。
もうその頃には携帯電話があった頃でしょう。
わたしは何の変哲もないデジタル画面に映る数字がぼんやり薄くなったり、
数字の一部が欠けたり満ちたりを繰り返したりするさまを、呆然と見つめていました。
それは、柱時計が自分の時間をマイペースに打つ
どこか優雅でさえあった動作とは似ても似つかない、
病的な、神経質な痛々しさを感じるものでした。
父は「参ったなあ」と言いながら、
背面の電池パックのフタを外し、新しい電池に入れ替えます。
新しい命を吹き込まれたデジタル時計は、
まるで新入社員のようなピカピカの輝きを放つ黒々とした数字を映し出しました。現実の時から離れ、自分の時を刻むだけだった晩年の柱時計を
どうして父が捨ててしまったのかはわかりません。
でも、わたしは時計を触る父が好きです。
たまに、黒いルーペを目にはめて、時計の裏や文字盤を見ていました。
そういう時に一瞬のぞく真剣な職人の顔は、まるで知らない人のようで、
父には父の人生があるのだと、父には父の時間が流れているのだと、
当たり前のことに今さら気づかされ、胸にひゅっと風が吹きます。
わたしが追いつけない何十年かがあって、一緒に歩いてきた何十年かがある。柱時計は、わたしの知らない父を知っているのです。
やっぱり、捨てないで取っておいてほしかったな。
今度、実家に帰ったら柱時計の話を聞いてみたいです。
わたしが知らない、父の人生のことを。